神戸製鋼の組織ぐるみの検査データ改ざん事件。現場の「品質力」劣化の背景は。モノづくり日本の凋落を象徴(藤井良広)
2017-10-16 22:01:43

神戸製鋼所は神戸市の代表的企業だ。旧鈴木商店にルーツを持ち、筆者も神戸出身者として、子どものころ、その名を聞くと一種の畏敬の念を覚えたものだ。「シンコウ」勤めになった同級生も多い。その会社の検査データ改ざん事件が世間の耳目を集めている。
(写真は、90度の角度のお辞儀で謝罪をする神戸製鋼の川崎博也会長兼社長)
「Kobe」が世界の注目を集めるのは、1995年の阪神淡路大震災以来かもしれない。自然災害の悲劇と人為の不祥事。いずれも、心が痛む。しかも、今回は相次ぐ報道によって、一過性のミスではなく、現場ぐるみ、組織ぐるみの改ざんであったことが明るみになった。モノづくりの「Kobe」はなぜ、「壊れてしまった」のだろうか。
「日本のモノづくりが、どこかおかしい」と感じ始めたのは、10数年前だった。神戸製鋼と同じ鉄鋼業界の雄、JFEの東日本製鉄所千葉地区(千葉市)で2004年に、水質汚濁防止法の基準を上回るシアン化郷物などの高アルカリ水の違法排水と、データの改ざん事件が発覚した。10数年間も続いていた不祥事は、同社本社にとっても寝耳に水で、現場が「この程度の汚染は実質的に問題ない」と長年判断してきたという。
JFEの「現場主導の不祥事」に続いて、2006年に判明したのが、神戸製鋼の加古川・神戸両製鉄所での事件。大気汚染防止法の基準を超えて、ばい煙や窒素酸化物、硫黄酸化物などの汚染物質を排出しながら、測定データを長年にわたって改ざんしていた。今回の検査データの改ざん事件の予兆ともいえる不祥事だった。

両製鉄所では、ボイラーから排出する汚染物質の濃度を自動的に記録・測定する記録計を装備していたが、濃度が基準値に達しそうになると、記録計のペンを浮かせて記録が残らないようにする通称「ペン浮かし」の技術を現場が“開発”していた。排出量が急増して「ペン浮かし」では間に合わない場合は、基準値超過を記録した記録紙の当該部分を切り取って破棄し、後で手書きのデータを張り合わせる「現場工夫」も編み出した。そうした不正をなんと30年近くも続けていた。
ばい煙情報の改ざん発覚は、全社の規律見直しのきっかけになるはずだった。だが、そこで編み出された「負の現場工夫」は、その後、是正されるどころか、さらに神戸製鋼全体に行き渡ってしまった。まるで、病原菌のように。
日本のモノづくりの強みは、開発力だけでなく、現場の一人ひとりが、自らの目と経験と責任感とで、製品の性能、品質等を見極める「品質力」によって底支えされてきたとされる。単に量を売るだけではなく、購入者の使い方や安心にまで心を配る現場の気遣いも含まれる。ところが、この現場の意識が、「この程度なら許容量の範囲」と基準に満たない製品を合格扱いにしたり、今回のように「基準に合わないようならデータを書き換えればいい」と改ざんを是とする「負」に転じてしまうと、「品質力」は一気に崩壊してしまう。
問題は、どうして神戸製鋼の現場力が、逆方向に回転してしまったのか、という点にある。一つ一つの製品に対する自分自身の納得やこだわり、職場でのチームワークによる連帯感、仕事への誇り、あるいは働き甲斐――。こうした現場の強みを維持してきた力が弱まっていたとしか思えない。それも一工場だけでなく、全社的に弱まっていた。神戸製鋼の現場から「働き甲斐」が消えていたようにも映る。

今回の衆院選挙の大きな争点に、アベノミクスの評価がある。安倍政権が誕生してからの金融緩和策等で、企業業績は回復した。だが、消費は盛り上がらず、デフレはいまだに解消できない。企業が溜め込んだ内部留保をどう吐き出させるかが論点にもなっている。
企業業績の回復は統計的に明らかだから、景気回復感が盛り上がらないのは、その配分に課題があるとの見方は正しいだろう。働きに見合った賃金が得られないと、消費に回せないだけでなく、人は働く気力を減退させる。下請け企業も同様だ。企業業績回復のある部分は、現場の合理化、人員削減等によるコストカットでもたらされているとすると、その分も、現場の士気を低下させてきた可能性がある。
企業の人事評価にも構造的な課題がある。本社のキャリア社員と、工場現場のたたき上げ社員とのギャップは、かつては平等的な賃金配分と、本社の現場尊重によって、バランスが保たれていた側面がある。だが、多くの大手企業がグローバル展開する中で、国内現場よりも、海外拠点での生産性向上に経営の視点がシフトしている。
現場での合理化はグローバル水準にサヤ寄せされ、賃金配分も平等型から変化しつつある。かつての現場の余裕は消え失せ、現場は自らが手掛ける製品に思いを寄せるよりも、目の前の対応処理に追われ、仕事へのプライドを失っていく。一人ひとりの働き甲斐は逃げ水となって遠ざかり、企業ブランドを支えてきた「見えざる品質力」の手応えは定かでなくなってしまう。
ことは神戸製鋼だけの問題ではない。直近でも、無資格の従業員による完成車検査の常態化が発覚した日産自動車、子会社の富士ゼロックスによる海外での不正会計処理が見つかった富士フィルム、新人社員が過労自殺した電通、社員のいじめ自殺訴訟を提起された三菱電機など、企業現場のいびつな構造が相次いで発覚している。http://rief-jp.org/ct6/73464
グローバル競争が加速化する渦中で、多くの日本企業において、これまで土台としてきた「健全な労使関係」が綻び、負の現場判断での取り繕いがボロボロと、剥げ落ちているように映る。その大きな要因として、伝統的な日本企業の強みを維持しながら、グローバル戦略を展開できる能力のある経営者がほとんど見当たらない、という経営力の課題も浮き上がる。

日本の企業経営者が、企業の社会的責任(CSR)に正面から取り組むようになったとされるのが、モノづくりの変質が見え始めた前後の2003年。経済同友会が第15回企業白書で「『市場の進化』と社会的責任経営」を世に問うた。以来、同年は「CSR元年」と呼ばれてきた。同友会のCSR宣言を強力に推進したのが、当時の代表幹事の故小林陽太郎氏(当時、富士ゼロックス会長)だった。
そのころ小林氏にインタビューをしたことがある。「日本のCSRの特徴は何ですか」との問いに対して、同氏は「企業の基本モデルには業種に関係なく、顧客が必ずある。その顧客に対して、その企業ならではのサービス・商品を従業員が提供し、そこから利益を上げ、株主に還元する。このモデルはあまり変わらない。大切なことは、こうした複数のステークホルダーを視野に入れ、それぞれを満足させる経営を果たすことだ」と明快に語った。
小林氏は2年前に亡くなった。御存命ならば、「CSR元年以来、日本企業にCSRはどれほど定着したか」と聞いてみたい。上述の不祥事企業の一つに、富士ゼロックスの親会社の富士フィルムが名を連ねたことは、同氏にとって痛恨の極みだったのではないか。「企業の基本モデルを果たせていなかった」と反省されたか。
神戸での「遠い記憶」がよぎる。筆者が40数年以上も前の学生時代。神戸の山奥にポツンと立つ町工場で、1週間ほどアルバイトをしたことがある。仕事の内容は、ウレタンマットを薄く裁断して、アジアのどこかの国に輸出する、という仕事場だった。長田の町工場で製造された厚さ3センチほどのマットを、5枚か6枚かに機械で裁断する。だが素人がやると、厚みがばらばらになったり、ひどい場合は、穴が開いてしまう。そうした不良品は輸出できない。
しかし、年長のバイト仲間が「梱包すればわからないから、これぐらいでいいよ」と、適当に不良品も混ぜて梱包したことがあった。すると、われわれの雑な作業を見透かしたかのように、たたき上げの副主任格の責任者が、おもむろに積み上げた梱包の山を下ろして、解体し始めた。中のマットを一枚一枚、点検するためだ。
「やばい」と仲間同士で顔を見合わせたのも後の祭り。彼は、不具合製品を全部、取り除き、一言も言わずに、別の作業に向かった。それだけだった。町工場の品質力はそうした職人気質の社員によって支えられていた。今はその工場がどこにあったかもわからないほど、周辺は開発が進み、住宅地に変貌している。
それから半世紀近く。現場力と経営力がともに揺らぐ日本のモノづくりの現状を象徴するかのように、「Kobe」の名を関した大企業の苦闘が続いている。
(藤井良広)
藤井 良広 (ふじい・よしひろ) 大阪市立大学卒、日本経済新聞元編集委員、上智大学客員教授。一般社団法人環境金融研究機構代表理事。神戸市出身。






















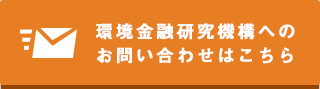








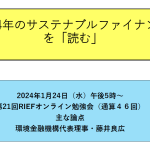

 Research Institute for Environmental Finance
Research Institute for Environmental Finance