原発、やらせ、インサイダー疑惑…不祥事続く経産省の病巣(各紙)
2011-08-04 22:39:54

経済産業省への信頼が大きく揺らいでいる。東京電力福島第1原子力発電所の事故で、「安全神話」を掲げてきた同省の権威は失墜。事故が収束しないなか、傘下の原子力安全・保安院の審議官が女性問題で更迭され、現職キャリア官僚のインサイダー取引疑惑も発覚した。さらに先週末には保安院がプルサーマル発電に関するシンポジウムで「やらせ質問」を中部電力に依頼していたことも明らかになった。官僚個人のスキャンダルにも、政策の破綻にも通じる「病巣」がこの組織にはありはしないか。
■看板政策の担当者に疑惑
まずはインサイダー疑惑を見てみよう。渦中にあるのは前資源エネルギー庁次長(1981年入省、52歳、6月22日付で大臣官房付)。証券取引等監視委員会は、前次長が2009年2月ごろから妻名義の口座で行っていた半導体大手エルピーダメモリ株の売買について調査を進めている。
同社はリーマン・ショック直後の08年秋ごろから業績が急速に悪化。09年6月22日に改正産業活力再生特別措置法(産活法)の適用を申請し、所管の経産省が同30日に同法適用を認定している。
この産活法適用認定でエルピーダ再建は大きく前進した。ほぼ並行する形で日本政策投資銀行が優先株(300億円)を引き受け、民間金融機関や政投銀による協調融資(1100億円)も決まって、同社の信用不安が一気に収まったからだ。09年2月初めに593円だった株価は、同6月末には1045円まで回復している。
前次長は当時、商務情報政策局担当の審議官でエルピーダ経営陣から報告を受け、政投銀や民間金融機関と直接交渉していた。
産活法は「100年に1度の危機」といわれたリーマン・ショックを克服するために当時の麻生政権が打ち出した目玉対策の1つ。90年代以降に急ピッチで進んだグローバル化や規制緩和で、産業界への影響力低下が著しかった経産省にとっても、存在感を見せつける格好の機会だった。その「看板政策」の直接の担当者がインサイダー取引で私腹を肥やしていたとしたら、モラルハザードも甚だしい。
実は、今回浮上しているインサイダー疑惑とまったく同じ構図の事件が6年前に起きている。05年3月、経産省の現職キャリア官僚が産業活力再生特別措置法(産業再生法)の適用を前提に04年に実施されたカメラメーカー、チノンのTOB(株式公開買い付け)計画の情報を事前に入手、同社株を売買したとして証券取引法違反(インサイダー取引)容疑で告発され、05年10月に東京地裁で有罪判決を受けた。
さらにチノンTOBを巡るインサイダー事件が明らかになった3カ月後、もう1つ経産省幹部が絡んだ株式スキャンダルが発覚している。同省大臣官房企画室長(発覚後に諭旨免職)が04年、職場の裏金を使って当時の産業再生機構による支援計画が進んでいたカネボウ株を売買、約200万円の運用益を上げていた。裏金は大臣官房企画室が同省所管財団法人の調査研究費の一部をプールしたもので金額にして約2900万円に上った。
■熱血官僚は今…
かつて城山三郎氏の小説「官僚たちの夏」の舞台になった通商産業省は経産省の前身。城山氏が描いたような熱血官僚が産業政策を主導し、敗戦から高度成長を果たす「日本株式会社」の成功の礎になったのは間違いない。しかし、それもせいぜい1980年代まで。以後は政策の失敗や不祥事が目立つ。
例えばエネルギー政策。経産官僚にはオイルショック後の約40年間、日本のエネルギー政策を支えてきたという自負がうかがえる。だが、負の側面も無視できない。
「輸入原油の3割を自主開発原油に」と、通産省主導で石油開発公団が設立されたのは第3次中東戦争の4カ月後の1967年10月。78年に石油公団に名称を変更、2001年までに2兆844億円を投融資し、293社の開発会社を設立したが、このうち軌道に乗ったのはわずか13社。杜撰(ずさん)な資金管理が問題になり、01年に就任間もない小泉純一郎首相が廃止を決定した時には「確定損失と回収不能見込額が合わせて1兆4000億円を超える」とされ、国会などで激しい批判を浴びた。石油公団の資金源になったのは石油特別会計。大蔵省(現財務省)のチェックが入らない、通産省の「つかみガネ」だった。
話はこれで終わらない。石油公団は2005年に廃止されたが、公団の出資比率が50%以上だった有力な石油開発会社は一部再編され、相次いで株式を上場。そこに経産省の大物OBが続々と天下っている。石油資源開発の棚橋祐治会長、渡辺修社長はいずれも元通産省事務次官。国際石油開発帝石の黒田直樹会長は元資源エネルギー庁長官、北村俊昭社長は元経済産業審議官といった具合だ。
さらにチノンTOBを巡るインサイダー事件が明らかになった3カ月後、もう1つ経産省幹部が絡んだ株式スキャンダルが発覚している。同省大臣官房企画室長(発覚後に諭旨免職)が04年、職場の裏金を使って当時の産業再生機構による支援計画が進んでいたカネボウ株を売買、約200万円の運用益を上げていた。裏金は大臣官房企画室が同省所管財団法人の調査研究費の一部をプールしたもので金額にして約2900万円に上った。
■熱血官僚は今…
かつて城山三郎氏の小説「官僚たちの夏」の舞台になった通商産業省は経産省の前身。城山氏が描いたような熱血官僚が産業政策を主導し、敗戦から高度成長を果たす「日本株式会社」の成功の礎になったのは間違いない。しかし、それもせいぜい1980年代まで。以後は政策の失敗や不祥事が目立つ。
例えばエネルギー政策。経産官僚にはオイルショック後の約40年間、日本のエネルギー政策を支えてきたという自負がうかがえる。だが、負の側面も無視できない。
「輸入原油の3割を自主開発原油に」と、通産省主導で石油開発公団が設立されたのは第3次中東戦争の4カ月後の1967年10月。78年に石油公団に名称を変更、2001年までに2兆844億円を投融資し、293社の開発会社を設立したが、このうち軌道に乗ったのはわずか13社。杜撰(ずさん)な資金管理が問題になり、01年に就任間もない小泉純一郎首相が廃止を決定した時には「確定損失と回収不能見込額が合わせて1兆4000億円を超える」とされ、国会などで激しい批判を浴びた。石油公団の資金源になったのは石油特別会計。大蔵省(現財務省)のチェックが入らない、通産省の「つかみガネ」だった。
経産省は石油資源開発では持ち株比率34%、国際石油開発帝石では18%の筆頭株主(2011年3月期、名義は経済産業大臣)。杜撰な管理をとがめることもできたはずだ。石油公団廃止は結局、利権をしっかり握って手放さない官僚の焼け太りを招いた。
■無駄遣いの怪物
ただ、エネルギー政策での無駄遣いといえば、石油公団の1兆4000億円が可愛く見えるほどの「怪物」が控えている。
2003年に電気事業連合会が約19兆円のコストがかかると試算した核燃料サイクルだ。使用済み核燃料を再処理し、燃料に再び利用する工程だが、核燃料を有効活用しようという政策の是非はともかく、その杜撰な見通しには問題がある。
これまでに2兆円超を投じて建設した青森県六ケ所村の再処理工場では処理し切れず、全量再処理の工場新設を含めると費用が膨れ上がり、50兆円近くに達するとの見通しも出ている。使用済み核燃料のうち、高レベル放射性廃棄物の最終処分場が決まらず、日本の原発が「トイレのないマンション」と揶揄(やゆ)されていることも深刻な問題だ。
さらに、燃やせば燃やすほど燃料のプルトニウムが増え、「夢の原子炉」と呼ばれた高速増殖炉でも、これまで1兆円近くを投じた原型炉「もんじゅ」が度重なる事故やトラブルで計画が難航。7月半ば、高木義明文部科学相が「存廃問題」に言及、その後慌てて発言を訂正する一幕もあった。
動力炉・核燃料開発事業団(現日本原子力研究開発機構)が発足した1967年に、高速増殖炉の実用化は80年代半ばが目標とされた。その後、目標は何度も繰り延べされ、2005年には「2050年ごろの導入を目指す」と改められた。この「空手形」乱発の経緯からは、血税からなる国費を投入しているという意識がほとんど感じられない。
「20代から30代初めくらいの職員は使命感が旺盛なのに、30代後半の課長補佐くらいになると、まるで人変わりしたように省益ばかり口にするようになる」。経産省に出向経験のある大手金融幹部はこんな指摘をする。大手精密機械メーカーの元社長は「少なくとも1970~80年代の通産省には『これは』と思う人材がそろっていた。その後、日米摩擦などで行政指導が批判され、自由化が進むなかで権限が縮小して官僚たちは大切な何かを失っていったのでは」と解説する。
むろん、経産省の官僚がことごとく劣化しているわけではない。前資源エネルギー庁次長のインサイダー疑惑が明らかになると、同省内から「何でこんなことをしたのか」「情けない気持ちでいっぱい」といった声が次々と上がった。
東日本大震災で壊滅的な打撃を受けた岩手県陸前高田市の食品会社社長は「東北経済産業局の中堅幹部が即断即決で必要な措置を次々に引き受けてくれた。経産省にもこんな人がいるのだと強く印象づけられた」と振り返る。
■大物OBの存在感
2003年に核燃料サイクルの巨額費用が表面化した際、経産省の一部の若手官僚が電力自由化に動いたが、電力業界や当時与党の自民党からのプレッシャーで押しつぶされた「事件」もあった。
挫折感を味わった若手の中には、経産省を去った者もいる。捲土重来(けんどちょうらい)を期すのではなく、経産省に見切りをつけたのは「大物官僚がOBになってからも省内人事を左右するような組織の土壌に絶望感を覚えたから」(関係者)という。
通産省時代から、この省では「10年に1人の逸材」と呼ばれるような実力者が君臨して恣意的な人事を行い、退任して天下った後も省外から影響力を行使するような「歪(ゆが)んだ構図」が指摘されてきた。
実力者のパワーが衰えると、次の大物が現れ、それまでの路線を覆す。その結果、激しい人事抗争が起き、正論やモラルがしばしば置き去りにされる。実力者の意に沿わなければ、優秀な人材も登用されず、上役の顔色をうかがう内向きの体質が強まる――。そんな歴史の積み重ねが現在の惨状ではないだろうか。
1980年代に米商務省審議官として半導体摩擦などで日本の官僚と対峙したクライド・プレストウィッツ氏はその著書「日米逆転」(ダイヤモンド社、88年)の中で、友人の通産省幹部の口から「(日本の)企業が通産省の助言を尊重するのは、通産省に優れた情報と分析力が備わっているからだ」との本音を引き出したことを紹介している。「優れた情報と分析力」に敬意を表し、人々が耳を傾けるのは当然のこと。その能力が劣化し、さらにモラルも失ったままでは国民の信頼を回復するのは難しい。

- そびえたつ経産省本館は頑強だが、内部は病巣が蔓延し崩壊状態?
;p=9694E3E6E2E7E0E2E3E2E0E7E3E5






















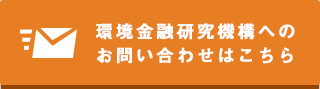








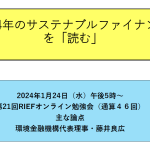

 Research Institute for Environmental Finance
Research Institute for Environmental Finance