「環境金融」の「不易流行」 (西川綾雲)
2016-05-16 15:02:45

運動論としての「環境金融」のスタートを求めるとすれば、ひとつは1989年のエクソンバルディーズ号の原油流出事故に端を発する「バルディーズ原則」の制定、もうひとつは1992年の「国連環境計画金融イニシアチブ(UNEP FI)」の発足のふたつをあげることができると思う。
「バルディーズ原則」は生物圏の保護、天然資源の持続的な利用、廃棄物処理と削減、持続的なエネルギー利用、環境リスクの低減、環境保全型製品・サービスの提供、環境修復、市民への環境情報の公開、環境問題担当取締役の配置、年次監査報告書の作成と公表という「環境保全に関して企業が守るべき10の倫理原則」から成る。
特徴的なのは、これを公表した「環境に責任を持つ経済主体の連合」(CERES:セリーズ)は単なる環境NGOではなく、環境保全を推進する投資家グループだった点だ。原則を受け入れた企業に投資して、環境保全型の企業活動を支援するという運動を展開したのだった。
UNEP FIについては、国連側の運動と捉えるのか、金融機関(当初は特に銀行セクター)の運動と捉えるのか、その発端について議論の余地があるところだろうが、筆者は前者(国連)の目的意識を軸に、後者(金融機関)がそれに呼応するかたちで発足したというのが、ほぼ実態だったのだろうと想像している。
1992年は、リオで初めての「地球サミット」が開催された年であり、国連環境計画(UNEP)は金融セクターに経済社会が持続可能性配慮に舵を切るための「梃子」の役割を強く期待したのだろう。1991年に、ドイツ銀行、HSBC、Natwest、Royal Bank of Canada、Westpacなどが集まって、持続可能性配慮に関する自己宣言文書の作成と公表に動きだすのは、環境NGOなどの外部プレッシャーに振り回されるよりも、先行的な取組姿勢をアピールすることが賢明との判断があったのであろう。
それから、ほぼ25年。四半世紀の歳月が経過した。皮肉にも、地球と社会に関する持続可能性がますます脅かされている状況のなかで、「環境金融」という運動論は、「市場化」と「制度化」のふたつの潮流に飲み込まれてきているように見える。
「市場化」のシンボルは「責任投資原則(PRI)」の普及だろう。2006年に、当時の国連のコフィ・アナン事務総長がこれを提唱したとき、この6つの原則を支持するアセット・オーナーや運用機関などが10年間で世界中で1,500を超えることを予想した人は必ずしも多くはなかっただろう。
ただ実際には、インベストメント・チェーンという力関係を的確に捉えるとともに、クリアリング・ハウスなどの実務的なファンクション提供を実現することによってPRIはUNEP FIの数倍の存在感を有する組織となった。と同時に、多くの賛同機関は「運動に参加している」という意識よりも「商売のために有益だから」という意識でPRIに賛同を表明し、コストを負担しているともいえるだろう。それでも、「数は力」である。一種の業界団体(Trade Association)のような色彩を帯びながら、PRIは賛同機関の利益を擁護しつつ、今後も業界標準を先導していくことになるのだろう。
一方で「制度化」のシンボルは金融安定理事会(FSB)を機軸とする最近の動向だろう。各国の金融行政の総本山ともいえるFSBが「気候変動と金融安定」の関係を口にしだしたというのは、劇的な変化だ。こうした動きは、例えば銀行セクターに「仮に将来、気候変動の物理リスク、賠償補償リスク、移行リスクが、当局の行う資産査定に反映されたとするなら」という想像を容易に呼び起こす。その現実味は、持続可能性配慮に関する自己宣言を行うのとは、全くレベル感を異にするものだといってよいだろう。
FSBが発足させた「気候関連財務ディスクロージャー・タスクフォース」に衆目の関心が集まるのも無理からぬところだ。年内に成果を取りまとめるとされている作業は「任意参加で一貫性のある気候関連財務リスク情報の開示を進める」、「一般事業会社向けと、金融機関向けの2つの開示枠組みを検討する」というものだが、これを額面どおりに受け取る人ばかりではない。
企業側の情報開示の枠組みとしては、これまで冒頭で示したCERESの延長線上に位置づけられるGlobal Reporting Initiative(GRI)や、当初、気候変動に特化したCarbon Disclosure Project(CDP)、会計士業界が中心となったInternational Integrated Reporting Council(IIRC)などが議論を牽引してきたが、金融安定理事会の登場で一挙にリーダーシップが入れ替わる可能性もある。
さらに、「環境金融」の「制度化」に向けたエビデンスとして、UNEPがFIとは別に数年前に発足させた「UNEP Inquiry」の存在がある。ここでは、グリーンファイナンス(金融の意思決定に環境要因が適正に統合されること)に関する制度及び市場の障壁を明らかにすることが主眼に置かれているが、G20という政治的ビークルとも連携を果し、先進国と途上国の双方で進む「環境金融」に関連する法制度や規制枠組みを包含しつつ、将来像を描こうとしている。
こうしてみると、「不易流行」は世の中の常。運動論としての「環境金融」もその例外となることはできないようだ。ただ一方で、商魂たくましい金融エリートや、功名心に溢れた政治家・官僚に「環境金融」の「市場化」と「制度化」を任せておけば、予定調和的に地球と社会に関する持続可能性の劣化を少しでも食い止められるというのは楽観的に過ぎる。
折しもこの5月、ながらく空席が続いていたUNEP FI代表のポストに、国連環境計画からエリック・アッシャー(Eric Usher)氏が就任した。新代表には、メンバーの数を競うなど他のイニシアチブとの影響力競争に埋没するのではなく、ステークホルダーからの期待の表明とそれに呼応する先駆的金融機関の先行的取組姿勢のアピールの場という組織の原点を、是非、確認して貰いたい。
「市場化」と「制度化」が進むとしても、既存の社会経済システムを批判的に捉え、それを超克しようとする運動論としての「環境金融」が存在しなければ、それはすぐに形骸化したものに終わってしまうに違いないのである。
西川綾雲(にしかわ りょううん) ESG分野で20数年以上の実務・研究両面での経験を持つ。内外の動向に 詳しい。






















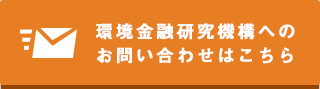








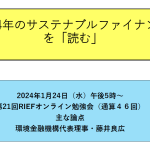

 Research Institute for Environmental Finance
Research Institute for Environmental Finance