書評:「ダイナミック・サステナビリティ」後藤英樹著(Amazonペーパーバック)
2025-02-09 12:29:45

本書は長年、サステナブルファイナンス分野のコンサルタントや実践活動を展開してきた著者の最新のとりまとめである。タイトルの「ダイナミック・サステナビリティ」について、著者は「日本企業の経営課題から紐解く、『ゲームチェンジ』を勝ち抜き、持続可能な成長を生む経営・企業財務・ガバナンス」との副題を付している。
本書は、「サステナビリティ(持続可能性)」というグローバルな『ゲームチェンジ』に直面している企業社会の、現在の状況と将来の展望を見据えるものだが、著者の視点は、改訂「日本再興戦略」以降の10年に及ぶ企業改革の課題を検証し、評価をまとめるという時間軸を考慮した内容だ。その中で著者は、すでにいくつかの企業において、自社が関連する環境・社会課題解決型事業を自ら拡大することで、持続的成長への機会を生み出し、ダイナミックな事業転換につなげていこうとする複数のアプローチが起きている点を強調している。
日本企業がサステナビリティに取り組むきっかけとなった要因の一つは2015年の「金融庁コーポレートガバナンスコード」とされる。これを踏まえ、多くの企業はサステイナビリティに対する「迅速かつ果断な」意思決定の導入を目標に企業統治改革に取り組んできた。しかし、その途中成果としては、IMDの2023年の国際競争力ランキングによると、日本企業全体の評価は「企業の機敏性」で最下位の64位であることが示すように、大きな変化はみられていない。
日本企業全般については、受動的、形式的なサステナビリティ対応が特徴的とされ、内外のESG投資家を中心として、依然、批判も多い。しかし著者は日本企業が抱える「転換」の課題においても、変革をドライブし、サステナビリティを実現するうえで、企業自身による能動的でダイナミックな事業転換を通じて創出する環境・社会価値を確実にしようとする動きが起きている点を指摘する。著者は、そうした動きを踏まえ、「サステナビリティを体現するダイナミックな環境・社会価値の実現」を企業が経営の柱に据えることを求めている。
本書の構成は、ESG投資の本質や規制動向の展望と地政学的側面の議論(第1、2章)を踏まえ、現状の各企業の統制偏重のコーポレートガバナンス改革と取締役会のスキルセットの検証(第3章)、成長投資を回避し、株主還元に奔走する低PBRなどファイナンスの課題(第4章)、囲い込むキャリア形成に固執する人的資本活用、M&Aや戦略的組織運営(第5章)などと続く。日本企業の「経路依存性」という共通課題から、サステナビリティへの高い貢献ポテンシャルと創造性も持ちながらも、それを実現できない日本企業の幅広い経営課題を分析している。
米国のトランプ政権の発足により、ESGをめぐる国際的イニシアチブの後退・混乱が起きている。著者は「しかし、メガトレンドとしての底流に大きな変化はないだろう」と見通す。ただし、サステナビリティの地政学的側面はさらに強まり、経済的利害関係に基づく「トランジション(移行)」に関する相克などは激しさを増すとみている。そうした流動的な環境下で、企業がネガティブな展開を乗り越えて、戦略的な「ゲームチェンジ」の勝者として生き残るには、ダイナミックに環境・社会価値を生む本質的なアプローチを自ら見出す必要性を示している。
各論点での著者の指摘としては、成長投資が回避され、実質無借金企業が上場企業の4割となる中、積極的な環境・社会課題解決型事業の模索へCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)活用の推奨や、コーポレートガバナンスでは、独立性を高めたモニタリング型経営(ボード2.0)の導入の課題を克服して、投資プロを加えるボード3.0を超える、企業ごとの主要な経営課題に焦点を置いた専門委員会の活用等を提唱している。https://amzn.asia/d/7x6zei3
著者紹介:後藤英樹(ごとう ひでき) S&Pの事業法人格付アナリスト、ゴールドマン・サックス証券金融戦略部長、クレアンESGアドバイザリーコンサルタント、トーマツ気候変動/ESGアシュアランス室 マネージングディレクターなどを経て、現在は医療・看護・介護ベンチャーの「ナインツリーホールディングス」代表取締役社長。









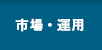




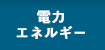







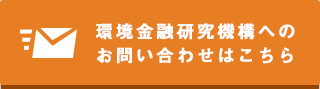










 Research Institute for Environmental Finance
Research Institute for Environmental Finance