|HOME
|10.電力・エネルギー
|福島第1原発、地震直後の24時間。事態をより正確に把握しておくための問題整理(WSJ) |
福島第1原発、地震直後の24時間。事態をより正確に把握しておくための問題整理(WSJ)
2011-05-19 21:50:42
ウォール・ストリート・ジャーナルが福島第1原発事故の発生後24時間を検証したところ、災いが重なった結果、当初あり得ないとみられていた水準まで事態が悪化したことがわかった。以下はその詳細。
冷却装置の手動停止
東京電力が16日に発表した文書によると、1号機の非常用復水器は、作動していたとしてもとぎれとぎれだった。同社幹部によると、本震直後、津波が起こる前に、炉内圧力の変化を制御するために復水器のバルブが手動で閉鎖されたようだという。バルブ再開にはバッテリー電源が必要だった。しかし、非常用バッテリーが津波で損壊したためバルブは開けられなかった公算が大きい。
バルブが閉鎖されていなければ、状況は違っていたかもしれない。冷却装置がないため1号機の温度は当初想定より急速に上昇し、より深刻な打撃をより早くにもたらした。東電は今週、1号機の問題が当初考えていたよりもかなり深刻だと認めた。新たな分析によると、本震のわずか5時間後に急速な燃料溶融が始まった可能性があるという。12日午前6時50分には、圧力容器の底に燃料がたまっていた公算が大きい。
オフサイトセンターが孤立
政府の緊急対応は、福島第1原発から車で15分の場所にあり、原子力安全・保安院 (NISA)が運営する「オフサイトセンター(福島県原子力災害対策センター)」で行われることになっていた。しかし、センター立ち上げを担当していた横田一磨氏が現場に到着して、電話線も携帯電話も使えないとわかった。衛星電話も機能しておらず、非常用発電機の燃料ポンプは故障。初期の重要なときに、センターは外部から隔絶されていたわけだ。
東電の非常用通信システムは動いていた。同原発の地震シェルターは津波被害を免れたため、ここの発電機で東京とのテレビ電話回線や特別な社内電話システムに電力を供給した。しかし、保安院のオフサイトセンターがオフラインだったため、政府は東京から危機対応を指揮し、情報を東電本社に頼ることになった。後にシグナルが交錯し、フラストレーションを引き起こした要因である。横田氏自身は、展開を把握するためにスタッフを原発に送り返すはめになった。保安院の発電機は12日午前2時ごろまで復旧しなかった上、1日たたないうちに燃料切れとなった。
2号機と1号機の冷却装置
東電は11日午後8時35分、福島第1原発の深刻な問題を示す最初の兆候とみられる事象を政府に報告した。2号機の非常用冷却装置が停止しているようだ、と。保安院の専門家は、同機の燃料が午前1時頃までに溶融し始める可能性を示した。午後9時23分には、政府が同原発から半径3キロ以内の住民に避難指示を出した。福島県は待ちきれず、この30分ほど前に指示を出している。
ただ、現在わかっているように、本当の問題は1号機にあった。同原発のエンジニアによると、真夜中前には、2号機では冷却装置が再開していたが、1号機では止まっていた。東電は最近になって、1号機の燃料棒がこの頃に露出していた公算が大きいと認めている。
清水社長の東京到着に遅れ
会社の決まりによると、放射性物質を含む蒸気の放出を決定するのは東電の清水正孝社長だ。しかし、東電のエンジニアや政府がこの決定に至った頃、同社長はまだ名古屋にいた。午後9時半頃、自衛隊に東京への移送を要請。社長を乗せた自衛隊機は名古屋を離陸したが、北沢防衛相の拒否を受け引き返し、午前12時13分に名古屋に着陸した。この頃、1号機の炉内圧力は憂慮すべき数値に達していた。
放射性物質の大気放出
これほど深刻な危機があり得ないと思われていた証拠に、東電は非常用ベント管に放射性物質除去用のフィルタを設置していなかった。ただ、日本の監督当局はベントが必要なほどの高い圧力への対応を迫られることになるとは考えていなかったため、完全なベント装置の設置は任意とみなされていた。これは、ベント実施で大量の放射性物質が放出されることを意味する。ベントに先立ち、政府は避難区域を前夜の3キロから10キロに拡大した。東電はベントの遅れについて、避難を考慮したことが大きいとしている。
福島県の原発安全担当者、片寄正巳氏は、原子力をかじったことのある者としてベントがいかに急務であるかは知っていたが、地元の行政担当者としては、どうぞ放射能をまき散らして下さいとはとても言えなかったと語った。知らせを聞いた知事は、ただうなずいたという。
注水の問題
東電の作業員はベント中に注水を増やせるかどうか確かめたかった。ベントにより水が水蒸気の形で放出されるほか、水の沸点は圧力が高いほど高いため、ベント中に水位がさらに下がって冷却問題が悪化する恐れがあった。しかし、東電幹部によると、それにも支障があった。通常であれば注水を行っていたはずの消防車のうち少なくとも1台が津波で流されていた。作業員が1号機に消防ホースをつないだときも、注水に問題があったという。
東電は、同機への真水注入を12日午前5時46分まで開始できなかった。作業は午後3時頃に打ち切られ、その30分後に水素爆発が起こる。注水量は80トン前後だった。
代わる代わる作業
1号機は、ベントのバルブを手動で開けるために作業員が中に入ったときには放射線量が非常に高くなっていたため、非常に短時間での作業員交代を余儀なくされた。シフトマネジャーは平均的な年間被ばく量の100倍の放射線を浴びた。東電の文書によると12日午前9時15分にはバルブが4分の1開いていた。放射線量が高かったため、第2のバルブの開放も遅れたと幹部は語る。
保安院の記録によると、この日は計18人が被ばくしたが、健康被害は報告されていない。シフトマネジャーは頭痛を訴え医師の診療を受けたが、その後帰宅した。
記者: PHRED DVORAK And YUKA HAYASHI
http://jp.wsj.com/Japan/node_238560
冷却装置の手動停止
東京電力が16日に発表した文書によると、1号機の非常用復水器は、作動していたとしてもとぎれとぎれだった。同社幹部によると、本震直後、津波が起こる前に、炉内圧力の変化を制御するために復水器のバルブが手動で閉鎖されたようだという。バルブ再開にはバッテリー電源が必要だった。しかし、非常用バッテリーが津波で損壊したためバルブは開けられなかった公算が大きい。
バルブが閉鎖されていなければ、状況は違っていたかもしれない。冷却装置がないため1号機の温度は当初想定より急速に上昇し、より深刻な打撃をより早くにもたらした。東電は今週、1号機の問題が当初考えていたよりもかなり深刻だと認めた。新たな分析によると、本震のわずか5時間後に急速な燃料溶融が始まった可能性があるという。12日午前6時50分には、圧力容器の底に燃料がたまっていた公算が大きい。
オフサイトセンターが孤立
政府の緊急対応は、福島第1原発から車で15分の場所にあり、原子力安全・保安院 (NISA)が運営する「オフサイトセンター(福島県原子力災害対策センター)」で行われることになっていた。しかし、センター立ち上げを担当していた横田一磨氏が現場に到着して、電話線も携帯電話も使えないとわかった。衛星電話も機能しておらず、非常用発電機の燃料ポンプは故障。初期の重要なときに、センターは外部から隔絶されていたわけだ。
東電の非常用通信システムは動いていた。同原発の地震シェルターは津波被害を免れたため、ここの発電機で東京とのテレビ電話回線や特別な社内電話システムに電力を供給した。しかし、保安院のオフサイトセンターがオフラインだったため、政府は東京から危機対応を指揮し、情報を東電本社に頼ることになった。後にシグナルが交錯し、フラストレーションを引き起こした要因である。横田氏自身は、展開を把握するためにスタッフを原発に送り返すはめになった。保安院の発電機は12日午前2時ごろまで復旧しなかった上、1日たたないうちに燃料切れとなった。
2号機と1号機の冷却装置
東電は11日午後8時35分、福島第1原発の深刻な問題を示す最初の兆候とみられる事象を政府に報告した。2号機の非常用冷却装置が停止しているようだ、と。保安院の専門家は、同機の燃料が午前1時頃までに溶融し始める可能性を示した。午後9時23分には、政府が同原発から半径3キロ以内の住民に避難指示を出した。福島県は待ちきれず、この30分ほど前に指示を出している。
ただ、現在わかっているように、本当の問題は1号機にあった。同原発のエンジニアによると、真夜中前には、2号機では冷却装置が再開していたが、1号機では止まっていた。東電は最近になって、1号機の燃料棒がこの頃に露出していた公算が大きいと認めている。
清水社長の東京到着に遅れ
会社の決まりによると、放射性物質を含む蒸気の放出を決定するのは東電の清水正孝社長だ。しかし、東電のエンジニアや政府がこの決定に至った頃、同社長はまだ名古屋にいた。午後9時半頃、自衛隊に東京への移送を要請。社長を乗せた自衛隊機は名古屋を離陸したが、北沢防衛相の拒否を受け引き返し、午前12時13分に名古屋に着陸した。この頃、1号機の炉内圧力は憂慮すべき数値に達していた。
放射性物質の大気放出
これほど深刻な危機があり得ないと思われていた証拠に、東電は非常用ベント管に放射性物質除去用のフィルタを設置していなかった。ただ、日本の監督当局はベントが必要なほどの高い圧力への対応を迫られることになるとは考えていなかったため、完全なベント装置の設置は任意とみなされていた。これは、ベント実施で大量の放射性物質が放出されることを意味する。ベントに先立ち、政府は避難区域を前夜の3キロから10キロに拡大した。東電はベントの遅れについて、避難を考慮したことが大きいとしている。
福島県の原発安全担当者、片寄正巳氏は、原子力をかじったことのある者としてベントがいかに急務であるかは知っていたが、地元の行政担当者としては、どうぞ放射能をまき散らして下さいとはとても言えなかったと語った。知らせを聞いた知事は、ただうなずいたという。
注水の問題
東電の作業員はベント中に注水を増やせるかどうか確かめたかった。ベントにより水が水蒸気の形で放出されるほか、水の沸点は圧力が高いほど高いため、ベント中に水位がさらに下がって冷却問題が悪化する恐れがあった。しかし、東電幹部によると、それにも支障があった。通常であれば注水を行っていたはずの消防車のうち少なくとも1台が津波で流されていた。作業員が1号機に消防ホースをつないだときも、注水に問題があったという。
東電は、同機への真水注入を12日午前5時46分まで開始できなかった。作業は午後3時頃に打ち切られ、その30分後に水素爆発が起こる。注水量は80トン前後だった。
代わる代わる作業
1号機は、ベントのバルブを手動で開けるために作業員が中に入ったときには放射線量が非常に高くなっていたため、非常に短時間での作業員交代を余儀なくされた。シフトマネジャーは平均的な年間被ばく量の100倍の放射線を浴びた。東電の文書によると12日午前9時15分にはバルブが4分の1開いていた。放射線量が高かったため、第2のバルブの開放も遅れたと幹部は語る。
保安院の記録によると、この日は計18人が被ばくしたが、健康被害は報告されていない。シフトマネジャーは頭痛を訴え医師の診療を受けたが、その後帰宅した。
記者: PHRED DVORAK And YUKA HAYASHI
http://jp.wsj.com/Japan/node_238560






















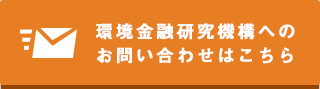










 Research Institute for Environmental Finance
Research Institute for Environmental Finance