|HOME
|走るタイヤからも給電 狙いは電気自動車の低廉化 ボルボ、豊橋技術科学大学が研究成果を披露 (各紙) |
走るタイヤからも給電 狙いは電気自動車の低廉化 ボルボ、豊橋技術科学大学が研究成果を披露 (各紙)
2012-07-31 17:38:54
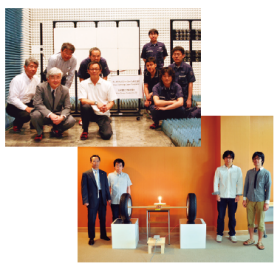
各紙の報道によると、電気自動車(EV)向けワイヤレス給電技術に関する研究開発が活発になっている。スウェーデンVolvo(ボルボ)社が同グループのアジアにおける研究開発拠点として2012年に東京に設立した ボルボテクノロジー・ジャパンと、豊橋技術科学大学がそれぞれ、最新の研究成果を2012年6~7月に発表した(図1)。
ボルボテクノロジー・ジャパンと、豊橋技術科学大学がそれぞれ、最新の研究成果を2012年6~7月に発表した(図1)。
現在、EVの普及を妨げている主要因の一つが、大容量のリチウム(Li)イオン2次電池を搭載していること。Liイオン2次電池のコストはEVの車両価格の3分の1程度を占めると言われている。搭載する容量を抑えれば、走行距離は短くなってしまう。こうした課題を解決する方法の一つとして、ワイヤレス給電の適用が検討されているのだ。
充電の手間が少ないワイヤレス給電を用いて充電回数を増やし、その分だけ2次電池の搭載容量を抑える狙いである。
■レクテナの効率は約84%
ボルボテクノロジー・ジャパンは日本電業工作と共同で、4m離れた場所へ10kW級の電力を無線伝送する技術を開発した(図2)。マイクロ波を用いたワイヤレス給電方式を採用する。同方式はこれまで、電磁誘導方式や磁界共鳴方式などに比べて電力伝送効率が低いのが大きな課題とされてきた。それを今回、高効率な「レクテナ」を開発することで差を縮めた。

図2 10kW級の高効率レクテナを開発 京都大学生存圏研究所の電波暗室で、電力伝送実験に成功した(a)。開発したレクテナの出力は1個当たり約1.3kWで、16個の素子を組み合わせている(b)。
レクテナは、アンテナ(antenna)と整流回路(rectifier)が一体となった、電磁波を直流の電力に変換するデバイスである。日本電業工作はレクテナ開発で高い技術力を持つ企業。今回、10kWの大出力ながら約84%と高い変換効率を達成するレクテナを開発した。
この数字には、レクテナ分野で長年研究を進めている京都大学 生存圏研究所 生存圏電波応用分野教授の篠原真毅氏も、「良くても60%台の効率だったので、80%以上を実現したのは驚き」と目を丸くする。
今回開発したレクテナは、1個当たり約1.3kW品を8個組み合わせている。使用するマイクロ波の周波数は、2.45GHzである。
Volvoグループでは、ワイヤレス給電技術をまずはトラックやバスなどの商用車に適用する構想を描いている。レクテナは「車両の天井側に取り付けることを検討している」(ボルボテクノロジー・ジャパン 代表取締役の外村博史氏)という。
バスやトラックの天井は平坦で、レクテナを設置しやすい。しかも、人や動物などを含めて異物が間に入ってしまう可能性が低い。
■実際のタイヤでの給電に成功
一方、豊橋技術科学大学の研究グループが注力しているのは、走行中のEVへのワイヤレス給電だ。開発を主導する同大 電気・電子情報工学系 波動工学研究室 教授の大平孝氏は「電車のように外部から電力を供給できれば充電の手間はなくなる。しかも、搭載する2次電池を大幅に小容量化できる」と意義を語る。
同グループは、タイヤを介して電力を伝送する手法を2011年に提案している。ミニカーでの原理検証は済ませていたが、今回初めて実際の自動車用タイヤでの実験に成功した。
今回の実験では、路面に見立てたアルミニウム(Al)板に約30MHzの高周波電流を流し、Al板の上にある二つのタイヤの間に取り付けた白熱電球を点灯させた(図3)。タイヤは市販の状態から手を加えていない。Al板から電球までの電力伝送効率は「80%を超えている」(大平氏)とする。
同研究グループは、電界結合方式と呼ばれる技術を用いている。道路に金属板を敷き詰めてタイヤの中のスチール・ベルトとの間にコンデンサを形成し、変位電流(高周波電流)を通すことで電力を伝送する。
注意すべき点は、通常の高周波電源をそのまま接続してもほとんどスチール・ベルトにエネルギーが伝わらないこと。高周波電源からの電力の大部分がタイヤ表面で反射してしまうからだ。そこで、電源とタイヤの間にLC回路を挿入し、高周波電流を再度あえて反射させた。二つの反射の位相を180度ずらして相殺した。
2012年度内に大学公開で1人乗り電動カートを試作して、走行実験を実施する計画。実用化に関しては「最初は走る場所が決まっている工場内などで導入することになると思う。5年以内での実現を目指す」(大平氏)と意気込む。
 ボルボテクノロジー・ジャパンと、豊橋技術科学大学がそれぞれ、最新の研究成果を2012年6~7月に発表した(図1)。
ボルボテクノロジー・ジャパンと、豊橋技術科学大学がそれぞれ、最新の研究成果を2012年6~7月に発表した(図1)。
現在、EVの普及を妨げている主要因の一つが、大容量のリチウム(Li)イオン2次電池を搭載していること。Liイオン2次電池のコストはEVの車両価格の3分の1程度を占めると言われている。搭載する容量を抑えれば、走行距離は短くなってしまう。こうした課題を解決する方法の一つとして、ワイヤレス給電の適用が検討されているのだ。
充電の手間が少ないワイヤレス給電を用いて充電回数を増やし、その分だけ2次電池の搭載容量を抑える狙いである。
■レクテナの効率は約84%
ボルボテクノロジー・ジャパンは日本電業工作と共同で、4m離れた場所へ10kW級の電力を無線伝送する技術を開発した(図2)。マイクロ波を用いたワイヤレス給電方式を採用する。同方式はこれまで、電磁誘導方式や磁界共鳴方式などに比べて電力伝送効率が低いのが大きな課題とされてきた。それを今回、高効率な「レクテナ」を開発することで差を縮めた。

レクテナは、アンテナ(antenna)と整流回路(rectifier)が一体となった、電磁波を直流の電力に変換するデバイスである。日本電業工作はレクテナ開発で高い技術力を持つ企業。今回、10kWの大出力ながら約84%と高い変換効率を達成するレクテナを開発した。
この数字には、レクテナ分野で長年研究を進めている京都大学 生存圏研究所 生存圏電波応用分野教授の篠原真毅氏も、「良くても60%台の効率だったので、80%以上を実現したのは驚き」と目を丸くする。
今回開発したレクテナは、1個当たり約1.3kW品を8個組み合わせている。使用するマイクロ波の周波数は、2.45GHzである。
Volvoグループでは、ワイヤレス給電技術をまずはトラックやバスなどの商用車に適用する構想を描いている。レクテナは「車両の天井側に取り付けることを検討している」(ボルボテクノロジー・ジャパン 代表取締役の外村博史氏)という。
バスやトラックの天井は平坦で、レクテナを設置しやすい。しかも、人や動物などを含めて異物が間に入ってしまう可能性が低い。
■実際のタイヤでの給電に成功
一方、豊橋技術科学大学の研究グループが注力しているのは、走行中のEVへのワイヤレス給電だ。開発を主導する同大 電気・電子情報工学系 波動工学研究室 教授の大平孝氏は「電車のように外部から電力を供給できれば充電の手間はなくなる。しかも、搭載する2次電池を大幅に小容量化できる」と意義を語る。
同グループは、タイヤを介して電力を伝送する手法を2011年に提案している。ミニカーでの原理検証は済ませていたが、今回初めて実際の自動車用タイヤでの実験に成功した。
今回の実験では、路面に見立てたアルミニウム(Al)板に約30MHzの高周波電流を流し、Al板の上にある二つのタイヤの間に取り付けた白熱電球を点灯させた(図3)。タイヤは市販の状態から手を加えていない。Al板から電球までの電力伝送効率は「80%を超えている」(大平氏)とする。

同研究グループは、電界結合方式と呼ばれる技術を用いている。道路に金属板を敷き詰めてタイヤの中のスチール・ベルトとの間にコンデンサを形成し、変位電流(高周波電流)を通すことで電力を伝送する。
注意すべき点は、通常の高周波電源をそのまま接続してもほとんどスチール・ベルトにエネルギーが伝わらないこと。高周波電源からの電力の大部分がタイヤ表面で反射してしまうからだ。そこで、電源とタイヤの間にLC回路を挿入し、高周波電流を再度あえて反射させた。二つの反射の位相を180度ずらして相殺した。
2012年度内に大学公開で1人乗り電動カートを試作して、走行実験を実施する計画。実用化に関しては「最初は走る場所が決まっている工場内などで導入することになると思う。5年以内での実現を目指す」(大平氏)と意気込む。






















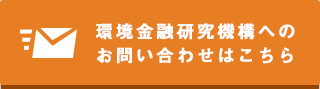










 Research Institute for Environmental Finance
Research Institute for Environmental Finance