北海道庁、釧路湿原周辺で大規模太陽光発電所(メガソーラー)開発を進める大阪の「日本エコロジー」社に対して「工事中止」勧告。強制力無し。「後手」に回る自治体、環境省の対応(各紙)
2025-09-03 01:18:32

(写真は、NHKニュースから引用)
各紙の報道によると、北海道庁は、道内の釧路湿原周辺で大規模太陽光発電所(メガソーラー)を建設中の大阪の再エネ事業者「日本エコロジー」社に対し、森林法で定められた許可を得ずに工事を進めたとして、建設予定地のうち森林区域での工事中止を勧告した。森林法では、民間が管理する森林に太陽光発電施設を作る際、土地の広さが0.5haを超える場合、知事に開発許可を申請することが定められている。しかし同社は、現場の森林は法定面積以下として、知事の許可を得ずに工事を進めてきた。今回、道と釧路市による現地調査の結果、開発面積は0.8haを超えることが分かったとしている。
北海道の勧告には法的な強制力や罰則はない。ただ、道によると、2日時点で森林区域での工事は止まっているとしている。建設予定地の森林区域以外での工事については、勧告の対象外。道は同区域での工事の現状については把握しておらず、事業全体の行方は、依然、見通せない状態となっている。
釧路湿原はラムサール条約の保護地でもあり、絶滅危惧種のタンチョウやオジロワシの生息地としても知られる。そんな自然豊かな釧路湿原での大規模な太陽光発電事業の建設に、有名人らがネット上で問題提起したことから、社会の関心が高まった。
釧路市内ではすでにメガソーラー約20施設が造られ、さらに約10施設の建設が計画されるという。市の担当者によると「湿原周辺は平らで工事がしやすい。日照時間が長く、雪が比較的少ないことから太陽光の適地でもあるため、設置が増えている」と説明している。国立公園内の地域は自然公園法で保護されているものの、公園区域外の周辺部は希少種が生息している場合でも十分な規制はなされていないのが実態だ。

自然の豊かさと、経済活動とは両立が難しいのは現実でもある。釧路市自体、これまで道内外の事業者による太陽光発電事業を実質的には受け入れてきた形でもある。市は自然保護と再エネ開発のバランスをとるとして、2023年7月に、太陽光発電施設に関するガイドラインを施行した。ガイドラインでは、希少野生生物保全に向け、事業者に対して有識者や専門家に助言・指導を求めることや、住民説明会の実施などを要請する内容になっているという。
しかし、同ガイドラインにも強制力はなく、メディアによると、市環境保全課は「ガイドラインにそぐわないことを理由に工事の差し止めなどはさせられない」と答えているという。さらに市は今年6月、福島市に続いて全国2例目となる「ノーモア メガソーラー宣言」をし、「自然環境と調和がなされない太陽光発電施設の設置を望まない」と発表している。
そのうえで、9月には一歩進めて議会に太陽光発電建設を規制する条例案の提出を予定するという。だが、これまでの同市の対応状況をみると、「ガイドライン」や「ノーモア宣言」等の法的拘束力のない「アピール行動」をとっている間に、いくつもの開発計画が実現している。なぜ、道も市も、もっと早く強制措置を伴う条例制定を打ち出さないのか、という疑問が出てくる。
ガイドラインや「宣言」等で、事業者が自主的な対応をとることが見込めるならば、それもいいだろう。だが、計画中を含めて約30件もの事業が進む現状を踏まえると、結果として、地元自治体自体が太陽光発電事業の開発を受け入れており、ガイドライン等は、それをあいまいにする措置ではないかとの疑問を禁じ得ない。確かに自然が豊かでもそれだけでは雇用も税収増も大きくは見込めない。観光資源にはなるが、保護を前提とする自然公園の場合、観光のための開発も制限が必要になる。
一方、太陽光発電などの再エネ事業は、自然改変を伴うが、エネルギー面では化石燃料エネルギーからの転換を進めるもので、そのための開発については、一定の「正当性」を主張できる面もある。こうしたことから、地元自治体だけではなく、北海道自体も、経済対策として、再エネ促進をGX戦略と絡めて掲げ、再エネ開発に力を入れている実態がある。
北海道に存在する豊かな自然はその存在が「当たり前」のように扱われ、改めて「保護・保全」の意識が希薄になっているのかもしれない。環境省自体が地球全体の保全のために求められている自然環境・生態系保全についての責任感が希薄な感じがする。浅尾環境大臣は2日の閣議後の会見で、今回の問題を問われて、「いずれの自治体も、環境配慮が十分ではない太陽光発電施設の建設問題への対応に苦労していて、国に対して制度的な検討を含め対応を求めていることが確認できた。関係する法律を所管する省庁が多岐にわたることから、地域の意見を関係省庁にも共有し、国としてどのような対応ができるか検討していきたい」と述べたとされる。
社会問題化して初めて「自治体の対応を確認できた」というのでは、環境保全を担当する中央官庁の長としての問題意識の低さを自ら吐露しているようなものだ。国際的には2022年の国連生物多様性条約締約国会議「COP15」で、2030年までに各国は自らの国土と海洋の少なくとも30%を自然保全の対象とする「30-by-30」目標等23の目標の設定で合意している。https://rief-jp.org/ct12/131095?ctid=
それ以来、3年が経過しており、主要な自然保全地域が抱える課題の把握と、共通する政策対応を打ち出すことが中央官庁には求められている。ところが、浅尾氏は、すでに政府レベルで推進されているべき「制度的な対応」について、「関係する法律を所管する省庁が多岐にわたることから、地域の意見を関係省庁にも共有し、国としてどのような対応ができるか検討していきたい」と、これからの課題のように述べている。
自然を保全し、国土を未来世代に伝えていく役割を果たさないのならば、環境省には存在意義はない。同省だけでなく、この国の役人、官庁は、どこを向いて仕事をしているのか、誰のために政策を講じているのだろうか、という疑問が、ここでも出てきてしまう。
(藤井良広)
https://japanecology.co.jp/company/greeting/
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250902/k10014910371000.html
https://www.tokyo-np.co.jp/article/422896
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC026YT0S5A900C2000000/?type=my#AAAUAgAAMA






















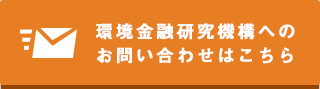










 Research Institute for Environmental Finance
Research Institute for Environmental Finance