ベトナムでの三井物産系の海底ガス田開発事業。国際協力銀行と3メガバンクの協調融資に対して、アジアの環境NGOが「ネットゼロ宣言に反する」と共同声明。「座礁資産リスク」も(RIEF)
2024-07-18 01:04:33

(写真は、開発が進むベトナムの「ブロックBガス田」事業)
三井物産子会社の三井石油開発がベトナム南部で展開する天然ガス開発事業に、国際協力銀行(JBIC)と三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)等の3メガバンクが総額8億3200万㌦(約1300億円)の協調融資を決めた。これに対し、東南アジアの環境NGO等が、日本、ベトナム両国が表明しているネットゼロ宣言に反すると非難する共同声明を公表した。同事業はベトナムの国営石油ガス会社(PVN)主導で、三井石油開発は事業会社に24.62%を出資する。開発する天然ガスは日本に輸出するのではなく、海底パイプラインでベトナムの火力発電所に「移行燃料」として供給する構想だ。
共同声明を公表したのは、Center for Energy, Ecology, and Development(フィリピン)、グリーンピース・タイ、「水の権利を求める人々の連合 (KRuHA)」(インドネシア)、「化石ガスと公平な移行に関する東南作業部会(Southeast Asia Working Group on Fossil Gas and Just Energy Transition)」、トレンド・アジア(インドネシア)の各グループ。ベトナムのNGO等は政府の弾圧への懸念から表面に出ていない。
「ブロックBガス田」は、ベトナム南部キエンザン省沖合200数10kmの水深77m地点の大陸棚にある。天然ガスの推定埋蔵量は1070億㎥。開発したガスは海底パイプラインで陸上まで輸送し、ベトナム南部の中心都市のカント―市で開発中のオモン電力コンプレックスに供給する計画だ。同事業は2000年代に、米メジャーのシェブロンが開発を進めたが、開発したガスの引き取り価格でPVNと折り合えず、事業から撤退した経緯がある。

同発電所群は4つの発電所で構成され、発電容量は合計3810MW規模となる。うち一つ(660MW)はすでに建設済みで、他はまだ計画段階。総事業費は100億㌦(約1兆5600億円)超とされる。三井石油開発が参加しての事業化は2016年に始まった。当初は2020年第2四半期(4~6月)の操業開始の予定だったが、供給先の発電所事業が遅れ、現在の供給開始時期は2026年とされている。
一方で、ベトナムは2023年5月に発効した第8次国家電力開発基本計画(PDP8)により、2050年のネットゼロ達成目標を立てている。また、2030年の中間目標を踏まえ、31年以降はガス火力依存を減少させるとしている。このため、同ガス田開発も現行の予定通りに26年からの生産開始ができた場合でも、5年後には供給量は削減に向かい、最長でも24年で生産終了になってしまう。
さらに現状では天然ガスの火力発電の発電コストは電力小売価格(電気料金)よりも高いことから、環境NGOだけでなく、関係者の間でも事業の採算性に疑問が示されていた。今回の事業・ファイナンスのゴーサインは、開発したガスをPVN及び、事業に参画しているタイのPTT子会社などが一定価格での買い上げ保証をつけたとみられているが、同事業の継続性への懸念は払しょくされておらず、協調融資をする金融機関は「座礁資産リスク」を抱えることになる。

JBICを筆頭とする日本の金融機関の協調融資は、三井石油が趣旨する「モエコベトナム石油(MVP)」「モエコ南西ベトナム石油(MSVP)」「MOECO Southwest Vietnam Pipeline B.V.」の各関係会社に対して、JBICがそれぞれと融資金額約1億6700万㌦、1億6100万㌦、8700万㌦を限度とする貸付契約を結んだ。MUFG等のメガバンクは協調融資として、3行合計で、それぞれ3億3500万㌦、3億2200万㌦、1億7500万㌦を供給する。
アジアの環境NGOらは共同声明において、「ブロックBガス田」事業を推進することは、ネットゼロ目標を宣言している日本とベトナム両国政府の公約と矛盾するほか、国際エネルギー機関(IEA)が2021年に、世界の気温上昇を1.5℃以内に抑えるパリ協定の目標を達成するには、新たな油田・ガス田を建設すべきではないとした報告にも反するとしている。
さらに、天然ガスは 「移行燃料 」とされるが、実際にはCO2よりも温室効果係数の高いメタンを排出する。大気中に放出されたメタンは20年間で、CO2の80倍も温暖化を加速する影響を及ぼすため、「グローバル・メタン・プレッジ」では、メタン排出量を2020年の水準から少なくとも30%削減するための国際共同行動を宣言しており、日本やベトナムも100以上の参加国とともに、この誓約にコミットしている。にもかかわらず、両国が今回のガス田開発を推進するのは「言動不一致」と指摘している。
また日本は2022年のエルマウ(独)でのG7サミットで、2022年末までに化石燃料への国際的な公的融資を打ち切ることへのコミットをしている。しかし、今日に至るまで、日本は化石燃料プロジェクトに資金を提供し続けており、この公約に真っ向から反している、としている。
今回の協調融資を主導するJBICは、現在、東南アジアで開発が進むガス・プロジェクトの最大の資金提供者とされる。2016年から2023年までに33億㌦を拠出している。このため、共同声明は、今回のベトナムでの新たなガス田事業への日本の開発支援は、日本主導の「アジア・ゼロ・エミッション共同体(AZEC)イニシアティブ」と並んで「偽りの解決策」への需要を製造し、緊急かつ必要なクリーンエネルギーへの移行を妨害するだけ、と非難している。
こうした指摘に加えて、環境NGOらは、すでに東南アジアでは、2023年の時点で328GWの再エネ事業計画が推進されている。このうちベトナムは、パリ協定後の再エネ事業稼働で東南アジア全体の半分以上に相当する17.6GWを担っている。こうした状況を踏まえると、日本の官民は、化石燃料関連の事業化とファイナンスをこれ以上続けるのではなく、再エネ等の自然エネルギーの導入と統合に資金を振り向けることで、脱炭素化の機運をさらに高めるべきだ、としている。
http://www.mekongwatch.org/PDF/rq_20240709_Eng.pdf
https://www.jbic.go.jp/ja/information/press/press-2024/press_00038.html









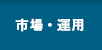




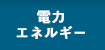







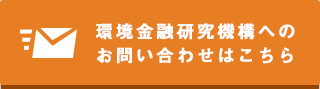










 Research Institute for Environmental Finance
Research Institute for Environmental Finance