サステナブルファイナンス~日本の状況に対する大いなる憂鬱~(西川綾雲)
2022-11-06 20:43:35

三つの構成要件と人々の合意
ESG投資やサステナブルファイナンスという言葉が世上を賑わしている。さらに足元では、トランシジョンファイナンスという言葉に大いに脚光が集まってきた。用語が明瞭に定義されないまま、話し手が都合のいいように、これらの言葉を使っていることで大きな混乱が生じているという指摘もあるが、筆者の理解は以下のようなものだ。
ESG投資、サステナブルファイナンス、トランシジョンファイナンスは、そのいずれもが、①気候変動は経済活動、人々の健康・財産・生命を脅かす深刻なリスク要因と認識すること、②その影響を緩和するため、経済社会を炭素中立化することが目指す到達点だと判断すること、③企業活動や人々の暮らしの劇的な遷移が不可欠であり、金融がその促進の一翼を担えると確信し行動すること、を前提あるいは構成要件としている。
こうした前提に関する一定程度の合意が、政治家や行政などの政策関係者、企業・業界団体など実物経済の担い手、アセットオーナーや最終的な資金の出し手となる市井の人々、そして金融機関や関連する金融関係者の間に成立していれば、サステナブルファイナンスは前に進む。逆に言えば、そこに合意がなければ、一種の言葉のブームだけでいずれは霧散霧消してしまうだろう。この観点から、日本の現状が心配でならない。国として何処を目指しているのか、経済界として何をしたいのか、何をしたくはないのか、それがバラバラで一定程度の合意にも至っていないように見えるからだ。あわせて、何の政策サイドからのシグナル効果を得られずアセットオーナーや金融機関は疑心暗鬼のなかで戸惑っている。多くの人々が莫大な時間とエネルギーを割いていながら、成果を上げられないのでは実にもったいない。

何故、「機会だ」と言わなければならないか
政府は「環境を良くすることが経済を発展させ、経済が活性化することによって環境も良くなるという、環境と経済の好循環の達成に向けた取組を進める」と言う。経済界も「グリーントランスフォーメーション(GX)は成長戦略であり、わが国企業が国際競争を勝ち抜くべく、産業競争力の維持・強化に資することが不可欠」と強調する。コンサルタントも「環境をよくして稼ぐ」と連呼する。勿論、海外でも、グリーンニューディールやグリーンリカバリーなど、気候変動対策を新たな有効需要創出の機会としてマクロ経済政策と結び付けた事例は過去にある。また、「日本人は、理屈では動かない。実利があって初めて動く」という指摘も一見、説得力を持つ。『北風と太陽』の寓話を引用して「気候変動はリスクではなく、機会と言わなくてはダメだ」との諫言を頂戴したことも、一度ではない。
それでも、この論調は「経済的にマイナスであることには取り組まなくてもよい」という発想を同時に誘発しかねない。このことを危惧するのである。「常に時代を風靡しているのは迷信です。 僕らも迷信の中にいるんです」とは評論家・小林秀雄の言葉(1970年8月夏季学生合宿教室)であるが、「経済」、「成長」、「稼げる」が気候変動対策とセットでなければならぬという常識を、迷信として疑ってみる時期にそろそろ来ているのではないか。現実に、危機は迫っている、リスクは高まっているのではないか。危機が回避出来ること、リスクを顕在化させなくて済むことが、最も大きな利を生むのではないか。そう考えるのである。
新たな胎動は始まっている。「The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say: We will never forgive you. We will not let you get away with this. Right here, right now is where we draw the line. The world is waking up. And change is coming, whether you like it or not.(未来の全世代の目があなたに向けられている。もしあなたが私たちを見捨てるなら、私たちはあなたを決して許しはしない。私たちは、何としても、あなたがこのような事態から逃げられないようにする。一線を引くのは今、この時だ。世界は目を覚ましつつある。そして、あなたが望もうと望むまいと、変化はやってくる) 」。グレタ・トゥーンベリが国連気候行動サミットで、こうスピーチしたのは2019年9月23日だった。今年、依然として、世界の温室効果ガス排出量はピークアウトを見通せていない。

足元では、人々のスポーツ・ユーティリティ・ビークル(SUV)のタイヤの空気を抜く国際的なグループTyre Extinguishersや、夜間に店舗の照明を消灯して回るパルクール集団の直接行動が活発化している。今年10月に入って、ロンドン・ナショナル・ギャラリーでのゴッホ《ひまわり》襲撃事件、ドイツ・バルベリーニ美術館でのモネ《積みわら》襲撃事件、オランダ・マウリッツハイス美術館でのフェルメール《真珠の耳飾りの少女》襲撃事件が続けざまに起きた。環境活動団体「Just Stop Oil」への賛同の声は皆無だが、未来世代の不安定な感情が行き場を失っているのも真実だろう。
「日本の若者は理性的で、そんな馬鹿な真似はしない」と評価される。しかし、筆者にはその保証はどこにも見つけられない。さらに、仮に日本の若者が沈黙を続けたとしても、この時代に海外の運動はいとも簡単に日本国内にも入り込んでくる。日本が気候変動対策をビジネス上の機会だとことさら強調する姿勢とのギャップは、今後、さらに開いていくだろう。
果たして、炭素中立化に到達すべきという得心はあるのか
経済社会を炭素中立化することが目指す到達点だと、日本は真に得心しているのか心許ないことがあちこちにあることも気がかりでならない。
2020年10月、日本政府は、「2050年カーボンニュートラル」を宣言した。しかし、それ以降、政府の様々な文書には次のような表現が次々、出現していく。「発想の転換、変革といった言葉を並べるのは簡単だが、実行するのは、並大抵の努力ではできない」、「EUの取組には一定の敬意を払いつつ、パリ協定に向けてはEUタクソノミーによるグリーンの推進だけでなく、トランジションも同時に重要であることを国際的に発信」、「トランジションファイナンスは、着実な低炭素化に向け、移行段階に必要な技術に対して資金供給するという考え方である。グリーンな活動か、グリーンではない活動か、の二元論では、企業の着実な低炭素移行の取組は評価されない恐れがある」。
経済界からも「日本経済の屋台骨を支えてきたモノ作り産業が競争力を失うことなく、カーボンニュートラルを実現するには、国家としての産業政策が求められる」、「ブレークスルーは、リニアで進むのではなく非連続であり、10年、20年単位の研究者・技術者の血のにじむ開発にかかっている。紙の上の議論ではなく、息長いグリーンイノベーションを期待しよう」「チャレンジする企業を、場合によっては鞭打ち、金融からもDivestされることを危惧する」といった声が上がる。
「排出削減困難なセクターにおける省エネ等着実な低炭素化に向けた取組や、脱炭素化に向けた長期的な研究開発等のトランジションに資する取組への資金供給を促進していくことが必要である」という認識のもと、2021年5月、「クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針」が公表されるに至った。
2021年の国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP26)では世界46カ国が脱石炭を目指す声明に賛同したものの、日本は加わらず、2022年5月のG7閣僚会合で、石炭火力の廃止年限が共同声明に盛り込まれなかったは、日本の反対が理由だったと伝えられている。
筆者にとって、衝撃的出来事だったのは、2021年10月8日、国連人権理事会で、「安全でクリーンで健康的で持続的な環境への権利」決議が採択されたときだった。気候変動などの環境被害が人権に悪影響を及ぼし、特に脆弱な立場にある人々を厳しい状況に置かれることを認識し、政府は、環境対策を通じて人権を尊重、保護、促進する義務があるとする決議には43か国が賛成したのだが、4か国が棄権に回った。それが、中国、ロシア、インドそして日本だったのある。「環境権は国際的に認識されたものではない」というのが理由だったと伝えられるが、こうした姿勢が「わが国企業が国際競争を勝ち抜くべく、産業競争力の維持・強化に資する」ことに繋がるとは、決して思えない。
2022年10月、G20に設置されたサステナブルファイナンス作業部会は「2022 G20 SUSTAINABLE FINANCE REPORT」を発行したが、その第1章には「トランジションファイナンスの枠組みの開発」というテーマが据えられた。そこでは、温室効果ガス多排出産業や企業の設備投資や活動に対する支援が限定的で、一部では銀行融資や資本市場へのアクセスが難しくなっていることを認めたうえで、トランシジョンファイナンスが具備すべき22の条件を示した。

興味深いのは、何がトランシジョンといえる活動と投資行動であるかを明確化するにあたり、日本の例を代表とする原則ベース・アプローチと欧州や中国の例を代表とするタクソノミーベース・アプローチがあることを対称化したことにある。当然、日本、欧州、中国がともにG20の加盟国・地域であるので、その優劣には言及していないが、ウォッシュのリスクを回避し、ロックインに繋がらないことが重要であり、パリ協定に整合的である点が必要だと強調している。
このように「日本は別のアプローチを歩む」と位置付けられる様相は、「脱炭素社会の実現に向けた道筋は、各国様々である点を踏まえるべき」と言い続けてきた日本政府や経済界にとって、一矢を報いることができた成果と言えるのかもしれない。しかし、「日本は緩い、日本は甘い」という印象が決定づけられてしまう側面を、同時に忘れてはならないだろう。
「どの港へ向かうのかを知らぬ者にとっては、いかなる風も順風たり得ない」(ローマ帝国の政治家ルキウス・アンナエウス・セネカ)という警句がある。筆者には、日本のサステナブルファイナンスの現状を、実に的確に言い当てている一文として目に映る。経済社会を炭素中立化するという確固とした到着点なしには、金融には何ら的確な意思決定など出来ないのである。
一体、金融に「野心」はあるのか
とはいうものの、日本のサステナブルファイナンスの閉塞感を、経済界や政府の姿勢にだけ帰着させてしまうのは、いささかフェアではない。客観的に見て、金融セクターにおける野心の欠如も否定できないからである。国や企業の視界が、近年、極めて短視眼になっているのと同様に、金融セクターの視界も、同じように短視眼になっている。金融の目利き力とは、5年、10年先の世の中と投融資先に置かれていたのが、不確実性が増しているという口上のもと、精々、四半期先の成果にしか関心が向かなくなっているように見える。人事制度や評価システムのあり方が、この傾向にさらに拍車をかけている。
「金融は、実物経済を反映することしかできない。金融が世の中の変革を牽引するなどという大それた話しは幻想である」という言説が、金融関係者の口から躊躇なく語られるのが現在である。戦後の鉄鋼、海運、自動車などの業界再編を主導し、政府などの方針と対立しても信念を貫いたとされる中山素平氏のような金融人は、もう現れることはないのだろうかと、考えることしきりである。その中山氏には「問題は、解決されるためにある」という名言が残っている。今もし、サステナブルファイナンス、トランシジョンファイナンスという議論に中山氏が参加されていたら、なんと仰るのだろうかと、夢を巡らすが実際は叶わない。
意識レベルが変わらないなら、しんがりを支援するファイナンスでよいではないか
問題ばかりを論っていても生産的ではないので、最後にひとつの提案を試みたい。ちょうど一年ほど前に、大手重工メーカーの幹部の方が「わが社は火力発電のしんがりの役割を担う。しんがりが生きていける仕組みが必要だ」という発言が新聞記事に載った。このセンチメントが、この国の多くの人の本音なのかもしれないと、以来、ずっと気になっている。これに倣うなら「日本は炭素中立のしんがりの役割を担う」と宣言し、しんがりのための資金供給を行うのが、「日本におけるサステナブルファイナンス、トランシジョンファイナンス」だと定義してみてはどうか。そして世界に対しては、「ほかの誰よりも、効率的にこのしんがりを務めて見せる」と高らかにコミットするのである。従来からの主張とは真逆の、しかも本心とは相容れない提案ではあるが、筆者を支配する憂鬱はこれでかなりの程度は解消されるかもしれない、と期待してみるほかないという心境に達している。
衒学の謗りは覚悟の上で、アルベルト・アインシュタインの「今日、世界に存在する問題は、それを作り出した時と同じ意識レベルでは、決して解決することはできない」という有名な一文を、最後に引用しよう。この国では、政治家や行政などの政策関係者、企業・業界団体など実物経済の担い手、アセットオーナーや最終的な資金の出し手となる市井の人々、そして金融機関や関連する金融関係者のいずれもが、意識レベルを変えられずにいる。そのなかで、サステナブルファイナンスを実現しようというのは、どこの国よりもハードルの高い話しだと、近頃、そう思えてならない。
西川綾雲(にしかわ りょううん) ESG分野で20数年以上の実務・研究両面での経験を持つ。内外の動向に詳しい。






















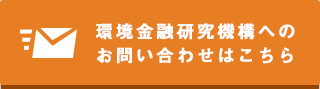










 Research Institute for Environmental Finance
Research Institute for Environmental Finance