米ボーグル原発新設の「ファイナンス論議」が意味するもの(明日香壽川)
2025-03-26 01:36:41

(写真は、米ジョージア州のボーグル原発3号機㊧と4号機=ジョージア電力のサイトから引用)
- はじめに
2024年12月12日の日本経済新聞に、珍しく(?)原発に批判的な記事が載った。内容は、米国において過去30年間で唯一建設が完工し、最後の大型原発となることが確実視されているジョージア州ボーグル原発2基(3号機は2023年、4号機は2024年にそれぞれ稼働)に関して、1)原発新設が総括原価方式でファイナンスされたために電気代が6割〜10割上がって地元住民が文句を言っている、2)建設費用は初期見積もりを大幅に超過して最終的には約2.7兆円/基となり、これは2009年運転開始の日本の最新原発である北海道電力泊3号機の建設費用とされる2900億円の約10倍であり、これからの原発新設はかなり高くつく可能性がある、というものだ(日本経済新聞2024)。
この記事に対して、日本のシンクタンクであり経団連系の産業界に近い方が多く在籍する国際環境経済研究所のホームページのコラムで、1)費用の大きさに関係なく利益が保障される総括原価方式が適用されたとしても、新設原発の稼働でそんな急に電気料金が上がるはずがない、2)コメントした地元住民の電力消費量や季節要因が影響しているのでは?という趣旨の疑義が呈されている(山本2024)。

結論を先に言うと、2基の原発稼働だけの理由で電気代が6割〜10割上がったというのは確かに疑問符がつく。ただし、原発稼働後に稼働が理由で電気料金が数割上がったのは確かであり、かつ1)3号機稼働時の2023年にも電気料金値上げはあった、2)州独自の「原発建設費用回収制度(Nuclear Construction Cost Recovery, NCCR)」によって、着工した2009年から原発新設コストが稼働前にもかかわらず電気料金に上乗せされていた、3)電力会社(ジョージア電力)はコスト超過や工期遅延でも(によって)大きな利益を得ていた、などは事実だと考えられる。
言うまでもなく、これらの事実は、日本における今後の原発新増設やファイナンス方式として導入が検討されている総括原価方式および規制資産ベース(Regulated Asset Base, RAB)モデルのような、発電する前から需要家から建設費用を徴収する仕組みの是非を議論する際には非常に重要である。
また、ボーグル原発は、東芝の子会社であったウェスティングハウス社のAP1000(第3世代プラスの加圧水型炉)である。周知のように、東芝はウェスティングハウス社を買収し、AP1000を世界中に売りこもうとした。しかし、このボーグル原発のコスト超過などを原因として2017年にウェスティングハウス社が倒産した。原発事業の失敗が東芝凋落の大きな一因という意味で日本とも因縁がある。
さらに、これから日本が「次世代革新炉」として原発を新設するとしたら、おそらく同じ第3世代プラスの加圧水型炉となると予想される。すなわち、技術面および費用面に関してボーグル原発と同様の課題に直面する可能性は高い。
このような中、以下では、Duran et al.(2025)などを参考にして、ボーグル原発の3号機および4号機の主にファイナンスにかかわる論点について述べる。
- 主な論点
- コスト超過
初期想定(見積もり)は2基で140億㌦(約2.1兆円)だったのが最終的には2基で368億㌦(5.5兆円)になり、最終的な発電単価は10784㌦/kWhになった(これは、再エネや天然ガスの数倍)。ちなみに、1986〜1987年に完工したボーグル1号機と2号機のコスト超過は1200%だった。事業者のジョージア電力は「ボーグル3号機と4号機は、1号機や2号機のようなコスト超過はない」と主張していたが、結果的には空言に終わった。
- 工期遅延
完工想定は7年だったのが最終的には15年かかった。
- 電気料金値上げ
電気料金は、3号機稼働後に7.85%、4号機稼働後に15.9%、合計で23.7%上昇した。
- 電力会社は最高益
ジョージア電力は、200億㌦以上のコスト超過にもかかわらず、2009年から2023年までに計170億㌦の利益を得た(コスト超過や工期遅延がなかったら利益額はより小さくなっていた)。その源は、稼働後の電気料金値上げと前出の稼働前(建設中)にも適用される「原発建設費用回収制度)」による料金徴収の二つである。
後者は、電力会社の強い要求によって法制化されたもので、稼働前から各電力需要家に建設コストを負担させる仕組み(総括原価方式かつ発電前から建設費用を需要家が支払う)である。これによって、2009年から2023年までの間に、各電力需要家は世帯あたりで約1,000㌦を累積で払っている(約9割を一般家庭の需要家が負担し、電気料金を8〜10%押し上げた)。なお、この「原発建設費用回収制度」は米国でも珍しい法制度であり、州政府などに対するジョージア電力の強いロビイングがあったと思われる。
- ガバナンス
2017年のウェスティングハウス社破産の際、電力事業を監視するジョージア州公共事業委員会の専属スタッフなどはプロジェクト中止を委員に進言した。しかし、最終的には、知事政治任命および選挙で選ばれた5人の委員からなる委員会はプロジェクトの継続を決定した。これに関しては、委員会が「規制の虜」となってしまったと批判されている。実際に、電力会社が得る利益の大きさを決める自己資本当期純利益率(ROE)をジョージア州公共事業委員会は他州の9.5%よりも高い11.9%と設定している(これだけで電力会社は7億㌦の追加的利益)。ジョージア州には、他の州にはある消費者保護機関がなかったことも事業が継続してしまった一因とされている。

- 建設中止となったV.C.サマー原発
一方、2017年7月、ウェスティングハウス社破産を契機に、同社がボーグル原発と同じAP1000の2基建設を進めていたサウスカロライナ州V.C.サマー発電所の原発新設プロジェクトは中止になった。建設開始時の総投資予定額は92億㌦で、完工予定は2019年と2020年だった(その後何度か見直しがあり、最後の完工予定は2022年12月と2024年3月)。完工までの総費用は180億㌦と当初想定の2倍に跳ね上がった。工事の進捗状況が約40%、既に使用された工費が約90億㌦となった段階でプロジェクトが中止された。この90億㌦を回収するために、サウスカロライナ州でも電力会社の要求で法制度化していた前述の「原発建設費用回収制度」によって2009年から2017年にかけて9回の電気料金の値上げがあった。すなわち、発電量ゼロのまま、90億㌦が電力需要家のポケットから電力会社などのポケットに移った。
- 不正
V.C.サマー発電所の場合、虚偽のコスト見積もりという犯罪行為によって、ウェスティングハウス社およびサウスカロライナ州の電力会社の幹部は懲役刑を受けた。
- コスト超過理由
理由として挙げられているのは、1)原発のモジュールは敷地外で建設し、現地に輸送することでコストを削減できる計画だったが実現しなかった、2)AP1000の設計自体が未熟であり、その未熟な設計に対して原子力規制委員会が許可を与えてしまった、3)プロジェクト全体のマネージメントが稚拙であった(3号機で起きたミスが4号機でも起きた。これは、初号機ではないからといってコストダウンになるとは限らないことの証左)、などとされる。
- 電力需要増という建設理由
電力需要増がボーグル原発の大きな建設理由の一つとされた。しかし、実際にはジョージア州の電力需要は20年間大きく変化しておらず、ピーク時需要の3倍の発電設備があった。
- 「原発ルネッサンス」
2005年、米国議会は原発新設に対して新たなインセンティブとなる融資保証や税制優遇などを含む「エネルギー政策法」を可決した。また、この時に原発事故の際の電力会社の保障責任を制限するプライス・アンダーソン法(1957年制定)が延長されたこともあり、多くの電力会社が原発新設を企てた。具体的には、2007年7月から2009年6月までの2年間で、米国原子力規制委員会は新規建設申請18件(28基)を受理し、ボーグル原発とV.C.サマー原発は最初の方に認可を取得した。この状況を「原発ルネッサンス」と業界やメディアは囃し立てたが、結局、着工したのはボーグル原発とV.C.サマー原発の2つのみであり、完工したのはボーグル原発の2基だけだった。結果的に、「原発ルネッサンス」は蜃気楼のようなものだったと言える。
- 第7次エネ基、RABモデル、英サイズウェルC原発
日本政府は2025年1月に閣議決定した第7次エネルギー基本計画において「原発活用」を掲げており、リプレース(建て替え)や新増設にも踏み込もうとしている。その際に導入を検討しているのが、前述の規制資産ベース(RAB)モデル、すなわち建設費用を含む原発の費用全体を稼働して発電する前から電気料金に上乗せして消費者・国民負担とする総括原価方式制度である。
このRABモデルは、数年前に英国において、発電後に固定価格で電力を買い取るファイナンス・スキームでは投資家が十分に集まらなかったことの反省から生まれた。すなわち、英国政府は、事業者や投資家に対してより魅力的なRABモデルを用いたファイナンス・スキームを提供することによって原発新設(サイズウェルCの2基3.2GW)を目指している。2年前から投資家を募集していて、2024年4月に英国政府は55億ポンド(約72億㌦)の政府補助金供与も明らかにした。英ガーディアン紙は、事業者であるフランスの電力会社EDFは、40億ポンド(52億㌦)の民間投資を集めようとしていると報道している(The Guardian 2024年10月10日)。

英イングランド・サフォークのサイズウェル原発(Wikipediaから)
しかし、2025年1月に、サイズウェルC原発の建設コストは2020年の見積もりである200億ポンドから倍増し、400億ポンド(520億㌦)近くになる可能性があることを示したレポートが発表されており(Cour des Comptes 2025)、英ファイナンシャルタイムズ紙も、複数の関係者の発言として同様の数値を示し、かつファイナンスの最終判断は予定よりも大幅に遅れていると報道している(The Financial times 2025年1月13日)。
すなわち、事業者や投資家にとってのリスクが極めて限定的なRABモデルで、かつ巨額の政府補助金がないと原発のファイナンスはつかない。それでも、すでに価格超過が指摘されているサイズウェルC原発の場合、投資家の最終判断がどのようなものになるかはわからず混沌とした状況にある。
実は、まさにRABモデルの原型が、上記で紹介したボーグル原発およびV.C.サマー原発の「原発建設費用回収制度」である。この制度は、これまで述べてきたように実質的には原発の新規建設への新たな補助金制度(原資は電気代および国民の税金)であり、世界の潮流である電力システムの自由化や市場化の流れに逆行するだけでなく、エネルギーに関する国民負担を増大させる可能性が高い。
- 結びにかえて
日本では、これまで、そして今でも原発関連の予算や容量市場や長期脱炭素オークションなどによって、税金および電気料金を原資とする多額の公的資金が様々な形で原発に対して供与されている。その上に、新たにRABモデルが導入されれば、地域独占企業で市場支配力を持つ大手電力会社、関係企業、銀行などの投資家は、巨額プロジェクトである原発の建設によって、たとえ工事遅延やコスト超過が起きても、大きな利益をすぐに長期に渡って安定的に得ることができる。米ボーグル原発のように、工事遅延やコスト超過が起きた方がより大きな利益を得られる可能性もある。
しかし、その代償として、国民は、すぐに、かつ長期間にわたって高い電気料金や税金を支払わなければならなくなる。電気料金が上がることで日本企業の国際競争力は低下し、日本経済に悪影響を与える。原発に伴う事故リスクや核拡散リスクが増大し、今でも行き場が確定しない放射性廃棄物はさらに増える。
このような懸念が単なる杞憂であることを祈る。
<参考文献>
・日本経済新聞(2025)「再エネ高い」は日本だけ?太陽光, 世界でコスト9割減, エネルギーの新秩序・国富を考える(3), 2024年12月12日.
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA051D20V01C24A1000000/
・Cour des Comptes (2025)La filière EPR : une dynamique nouvelle, des risques persistants, 2025.1.24.
・Durand P., Scott K., Carroll G.(2024)PLANT VOGTLE: THE TRUE COST OF NUCLEAR POWER IN THE UNITED STATES, May 2024.
https://www.nonukesyall.org/pdfs/Truth%20about%20Vogtle%20report%20May%2030%20release.pdf
・山本隆三(2024)不思議な日本経済新聞の記事:ジョージア州の電気料金高騰は原子力発電のため?山本所長ブログ:エネルギーの常識を疑う, 国際環境経済研究所, 2024年12月18日.
https://ieei.or.jp/2024/12/yamamoto-blog241218/
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

明日香壽川(あすか・じゅせん) 東北大学東北アジア研究センター教授(同大環境科学研究科教授兼務)。地球環境戦略研究機関(IGES)気候変動グループ・ディレクターなど歴任。著書に、『脱「原発・温暖化」の経済学』(中央経済社、2018年、共著)など。









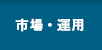




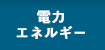







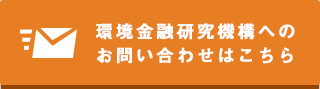










 Research Institute for Environmental Finance
Research Institute for Environmental Finance