アジア各国のサステナブルファイナンス。金融規制当局への調査からの最新動向(下)~カーボンクレジット市場も動き出す。高まる「質」への意識(白井さゆり)
2025-04-07 21:14:08

アジアでは、企業の脱炭素の取り組みを後押しし、気候変動の緩和策を広げる手段として、「カーボンマーケット(炭素市場)」への関心が高まっている。この市場では、温室効果ガス(GHG)の排出削減または除去を「カーボンクレジット」として売買することにより、新たな資金を生み出すことができる。その結果、脱炭素に向けた投資資金の不足を補う効果も期待されている。
一方で、世界的には、ボランタリー(自主的)カーボンクレジット(VCMs)の「質」に対する懸念が強く、政府や金融当局がその質の向上に貢献することへの期待も高まっている。こうした背景を踏まえ、アジア開発銀行研究所(ADBI)は、アジアの広範な地域を代表する12の金融規制当局を対象に、カーボンクレジットおよびその市場拡大に向けた政策に関する調査を実施した。本コラムでは、その調査結果の概要を紹介する(詳細は後述のペーパーを参照)。
カーボンクレジットの情報開示への関心の高さ
世界では現在、大企業を中心に、自社の排出量を相殺する手段としてカーボンクレジットを購入する動きが広がっている。国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が策定した気候関連開示基準では、企業に対して、GHG排出削減目標を「排出の絶対量(グロス)」と「カーボンクレジットなどで相殺した正味排出量(ネット)」に分けて開示することを求めている。また、ネットの目標を掲げる場合には、使用を予定しているカーボンクレジットに関する情報の開示が必要とされる。
カーボンクレジットに関しては、以下のような情報への注目が高まっている:
• クレジットが森林保全などの「自然関連のプロジェクト」由来なのか、あるいは「技術ベースのプロジェクト」に基づくものなのか
• クレジットがボランタリー市場から取得されたものであるのか、その場合、質の高いカーボンクレジットを目指した国際的な基準(たとえば「コアカーボン原則」)を遵守しているのか
• クレジットがパリ協定の「第6条」に基づく国際的な枠組みの下で発行されたものであるのか
ボランタリークレジット(VCMs)は、世界中で多種多様なプロジェクトのもとに、民間の認証制度に基づいて発行されている。しかし近年、いくつかのカーボンクレジットに関する問題(例えば、削減効果の過大評価)や訴訟が起きていることから、「質」への懸念が高まっており、需要の低迷にもつながっている(詳しくは Shirai[2025]を参照)。そうした中、質の向上に向けて注目されているのが、国際組織の 「Integrity Council for the Voluntary Carbon Market(ICVCM)」が策定した10項目からなる「コアカーボン原則(CCP)」である。
ICVCMは2024年から、CCPに準拠した高い信頼性を持つクレジットに対して「CCPラベル」を付与する取り組みを開始した。CCPラベルを取得するには、まずクレジットを管理するプログラムが「CCP適格(CCP-Eligible)」と認定される必要がある。そのうえで、当該プログラムの下で実施されるプロジェクトの方法論(測定・計算ルール)が「CCP承認(CCP-Approved)」を受けると、その方法論に基づいて発行されるカーボンクレジットにはCCPラベルが付与される。たとえば、国際的に知られるVerraやGold Standardといった主要な認証プログラムは、すでに「CCP適格」と認定されており、一部のカテゴリーでは「CCP承認」も得ている。
こうしたトレンドを踏まえて、本調査では、各国の金融当局に対し、「カーボンクレジットを活用した排出削減目標に関して、どのような情報開示を求めているか(または今後求める予定か)」について尋ね、上述のような情報を含めて複数の選択肢を提示した。
その結果、約7割の当局が「自然ベースまたは技術ベース」の情報開示を、約4割の当局が「コアカーボン原則に準拠した高品質なクレジットかどうか」の開示を、推奨または義務化する予定であることが明らかになった(図1参照)。全体のうち約2割の当局は「まだ方針を定めていない」と回答したものの、ほとんどの当局は企業が購入して自社の排出量から相殺するために使用するカーボンクレジットに関して、何らかの情報開示を求める方向にあることが伺える。さらに、グロスとネットの違いに関する当局の理解も、一定程度進みつつあることが読み取れる。

出所:筆者作成
調査ではさらに踏み込んで、VCMsに関して、少なくとも発行体に対してコアカーボン原則などの国際的な原則に準拠したクレジットの使用を求めているか、あるいは今後その予定があるかについても尋ねた。その結果、多くの当局が、クレジットの利用有無に関する情報開示を促す意向はあるものの、国際原則の遵守を発行体に求める方針までは定めていないことが分かった。ただし、2割の当局が「すでにそのような方針を持っている」と回答した点は注目に値する(図2)。

カーボンクレジットの「質」の改善に向けた具体的な取り組み
世界におけるVCMs市場は、これまでに民間主導で発展してきており、ここにはカーボンクレジットの発行体や認証制度の運営者、登録機関(レジストリ)、第三者検証機関、そしてクレジットを取引する市場参加者など、さまざまな関係者が関わっている。最近では、こうした市場の信頼性と透明性を高めるために、政府や金融規制当局も重要な役割を果たせると考えられるようになっている(IOSCO 2024)。
その一つの方法が、国際的に認められたルールやベストプラクティスを取り入れたガイドラインを政府や金融当局が策定することである。たとえば、ICVCMのCCPや、国際組織のVCMI(Voluntary Carbon Markets Integrity Council)が策定した「Claims Code of Practice」などを参考にしたガイドラインが考えられる。ICVCMは、カーボンクレジットの発行側(供給サイド)に対して品質を高める原則を設定する一方、VCMIは、カーボンクレジットを使う企業(需要サイド)が、科学的根拠に基づいたネットゼロへの道筋の中でクレジットをどう活用すべきかを示している。
政府は、VCMs市場の整備に向けて、たとえば自国のクレジット登録システム(ナショナル・レジストリ)を構築し、一定の基準を満たすクレジットを対象とすることで、クレジットの発行・取引・償却の記録を一元的に管理できる。また、クレジットの情報を標準化することで信頼性を高め、質の高いクレジットのみを掲載することで、市場全体の品質向上が見込める。
これまで、VCMsの多くは「相対取引(OTC)」で行われており、限られた企業間だけで取引され、標準化が進みにくい状況であったが、近年は複数の国や地域で証券取引所がVCMs市場に積極的に関与し始めている。また、証券取引所が、VCMsとパリ協定6条に基づくクレジットの両方を取り扱う市場を提供することで、より多くの投資家が参加しやすくなる。
さらに、国の排出量取引制度(ETS)と自発的市場との接続も市場の発展を後押できる。たとえば、政府がETSの対象企業に対し、「自発的市場で発行された一定条件を満たすクレジットで一部排出量を相殺することを認める」といった仕組みを導入することも考えられる。多くの国では5%を上限に一定の条件を充たすボランタリークレジットを使って相殺することを認めている。
こうした背景をふまえ、今回の調査では、政府や証券取引所が自発的カーボン市場の質向上に向けた取り組みをすでに実施しているか、あるいは実施を予定しているかを尋ね、取り組みがある場合は、具体的にどのような施策かも併せて質問した。その結果、①カーボンクレジットに関するガイドラインの策定、②国内のVCMs制度の整備、③VerraやGold Standardなど国際的な認証制度の導入、④炭素税を導入している国では一定の条件を満たすVCMsのクレジットを使って、炭素税の一部負担を相殺する制度の導入等を実施しているとの回答が複数見られた。
「追加性」と「二重計上の回避」への認識の高まり
コアカーボン原則(CCP)は10原則から構成されているが、中でも、「追加性(additionality)」の定義は特に重要だと世界ではみなされている。そこで調査では、「追加性」について国際的に認められた定義(すなわち、カーボンクレジットによる収益というインセンティブがなければ実現しなかった取り組みに基づいて発行されるクレジット)を、カーボンクレジットの基本的な定義として採用しているかどうかを尋ねた。
その結果、約3割の回答者がすでにこの「追加性」の定義を採用していると回答し、さらに17%が今後採用する予定であると回答していることがわかった。一方、約4割の回答者は、現時点ではこの点についてまだ判断を下していないことも示されたが、国際的な原則を重視する当局が半数を超えている点は興味深い(図3)。

もうひとつ、カーボンクレジットの信頼性を損なっているとして指摘される課題のひとつが「二重計上(ダブルカウント)」問題で、二重計上の回避はコアカーボン原則に含まれている。二重計上は、以下のような異なる段階で発生する可能性がある。
• 発行時:1つの排出削減または除去プロジェクトに対して、複数のクレジットが発行されるケース
• 使用時:同じクレジットが、同じ主体または複数の主体によって、登録簿(レジストリ)から無効化することなく重複して利用されるケース
このような二重計上を防ぐことは、カーボンクレジット市場の健全性を保ち、実質的な気候変動対策の効果を担保するうえで不可欠である。このため、カーボンクレジット制度や関連する登録簿では、「対応調整(corresponding adjustments)」を適切に行うことが求められている。パリ協定第6条の下でも、ホスト国と購入国が共同で実施するプロジェクトにおいて、クレジットがどちらか一方でしかカウントされないように調整することが義務付けられている。
そこで、調査では、発行、請求、使用の各段階で二重計上をどのように防いでいるのか、またどのような具体的な措置を講じているかについて質問した。その結果、回答者の3割弱が「国内登録簿の整備」を実施済みの対策として挙げたことが明らかになった(図4)。それに加えて、以下の4つの対策について、それぞれ約9%の回答者が挙げている。加えて、デジタルプラットフォームは世界各国のレジストリ(登録機関)をつなぐ役割も果たせる。
• VerraやGold Standardなどの国際的なレジストリと連携する国内登録簿の整備
• VerraやGold Standardが発行したクレジットの受け入れ
• 使用可能なクレジットに対して適格性に関する基準の設定
• 二重計上の回避原則の遵守するよう発行体に呼びかけ

ボランタリークレジットのデジタルアクセス状況
デジタル技術を活用したカーボンクレジット取引プラットフォームを整備することは、VCMsクレジットの取引を活性化させ、1次市場(発行段階)と2次市場(流通段階)の両方の発展を支えることができる。こうしたプラットフォームを通じて、カーボンクレジットの情報に電子的にアクセスできるようにすることで得られるメリットとしては、次のようなものが想定される。
• 取引の透明性とトレーサビリティ(追跡可能性)が高まることで信頼性の向上
• クレジットの登録から検証・取引・償却までの一連のプロセスの効率化
• コストの削減と手続きの迅速化
• 発行者、購入者、取引者等のより多くの関係者の参加を促進
• より透明で効率的な取引を通じて、市場価格の価格発見機能の向上
世界を見回すとデジタルプラットフォームをもとに、ブロックチェーン技術を使って、クレジットのリアルタイムな追跡やデータの改ざん・二重計上の防止が行われているケースもある。スマートコントラクトの導入により、取引の自動化が進み、さらなるコスト削減と迅速な処理が実現されている。
このような状況を踏まえ、調査では金融当局に対し、「VCMsに関する情報へ電子的にアクセスできる仕組みを提供しているか、または今後提供する予定があるか」について質問した。その結果、回答者のうち、約4分の1が「電子的アクセスを提供している、もしくは提供する計画がある」と回答し、さらに8%が「今後提供する意向がある」と回答している。しかし、約7割は「まだ方針を決めていない」としている(図5)。

まとめ
以上の調査結果から、アジア各国の金融当局は、カーボンクレジットの特徴への理解が高く、VCMsの質の向上が必要であること、国際的な原則や基準の重要性について広く認識していることが明らかになった。またこうしたテーマで本年3月中旬にアジアの金融当局と非公式会合を行い活発な意見交換を行った。
現在、アジアでは東南アジアを中心に、CCPのような国際的な原則およびVerraやGold Standardのような国際的に認知されたプログラムを尊重しつつも、そこでカバーしきれないプロジェクトもあることから、各国独自のVCMsの基準について互換性を高める努力が行われている。各国が個別対応をとることで分断が進めば、カーボン市場の発展が阻害され、アジア域内に十分資本が流入しない恐れがあるからである。他のアジア諸国を含めた議論も行われており、今後さらにアジア域内で率直な意見交換が行われ、アジア全体の市場の発展につながる政策対応を進めていくことが重要である。
その他の参考文献
The Board of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO). 2024. Voluntary Carbon Markets; Final Report, November. https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD774.pdf
Shirai, S. 2025. The Role of Carbon Markets in Facilitating Carbon Neutrality Publication, ADBI Policy Brief No. 2025-6 (April), Asian Development Bank Institute. https://www.adb.org/publications/the-role-of-carbon-markets-in-facilitating-carbon-neutrality
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

白井 さゆり(しらい さゆり)
慶応義塾大学総合政策学部教授。アジア開発銀行研究所客員研究委員兼サステナブル政策アドバイザー。コロンビア大学経済学博士。元国際通貨基金(IMF)エコノミスト。2011~16年日本銀行政策委員会審議委員として金融政策決定に関与。









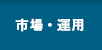




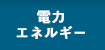







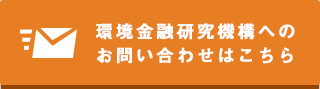










 Research Institute for Environmental Finance
Research Institute for Environmental Finance