第10回サステナブルファイナンス大賞インタビュー⑧特別賞。SMBC日興証券。「ESGサムライ債(円建て外債)」市場で、発行体、投資家の双方に対するリード役として活躍(RIEF)
2025-02-20 12:15:20

(写真は、授賞式で表彰状を手にしたSMBC日興証券の木下氏㊧。㊨は環境金融研究機構代表理事の藤井)
SMBC日興証券は海外の国や企業等による円建てのESG債(サムライESG債)のアレンジで、同市場をリードしてきたことから、第10回サステナブルファイナンス大賞の特別賞に選ばれました。同社のサムライ債市場を担当するグローバル・キャピタル・マーケット本部第二デット・キャピタル・マーケット部長の木下裕之(きのした・ひろゆき)氏にサムライ債市場戦略を聞きました。
――SMBC日興は、今回の大賞で国際賞の対象となったスロベニア共和国のソーシャルボンドを含め、毎年、ESGサムライ債の発行を支援し、同市場の拡大を進めて来られました。その取り組みを評価して特別賞に選びましたが、なぜSMBC日興がこの市場の育成に力を入れて来られたのかを、まず教えてください。
木下氏 : サムライ債は、わが社が力を入れている分野の一つです。これまで、同市場での主幹事リーグテーブルのランキングでは、一貫してトップの地位を築いて来ました。サムライ債市場のリーダーとして、市場のさらなる拡大につながることは何か、あるいは、同市場を通じて、社会的にも意義のあることを実現できるのか、といったことを考えた際に、サムライ債でのESG債発行を支援し、国内の投資家に、ESGサムライ債を広く紹介し続けることが大事だという風に、ずっと思ってきました。
そういう観点で同市場をみると、同債券の発行体には、国もいれば、その国の政府機関などもいます。また、銀行や事業会社などもESGサムライ債の発行体候補です。ただ、やはり国がまずESG債を発行することによって、その国に属する金融機関なども、国が発行するのであれば、自分たちも発行しようということになるので、国にどんどん発行してもらうことがいいのではないかと考えて、各国の当局(財務省など)に働きかけを進めてきました。その結果、これまでにハンガリー、インドネシア、フィリピン、今回のスロベニアなど、多くの国のESGサムライ債の発行を支援してきました。
――スロベニア共和国にESGサムライ債を発行してもらうことを働きかけた際には、同国の財務状況とか、海外での起債の状況などのデータも調べられたと思います。ただ、実際に各国当局が発行するかどうかは、直接コンタクトしないとわからないとも思います。そうした際、可能性のある国や企業には、直接、「セールス」のように働きかけるのですか。

木下氏 : そうです。SMBC日興としての海外拠点は、欧州、米国、アジア、オセアニアなどにありますが、発行体をカバーするという意味では、SMBCグループ全体のネットワークも活用します。当然、銀行と証券との業務の垣根(ファイアウォール)等のルールを守った上になりますが、常に、発行の可能性のある幅広い発行体をカバーしています。特にESG債の場合は、発行体にどのような資金調達ニーズがあるのかを、常に把握するようにしています。
同時に、発行された債券を引き受けて、投資家に購入してもらう必要があります。そのためには、投資家が選好する債券の格付けや、償還年限、さらにはレベル感、つまりクーポン(金利)はどれくらいになるのか、などのポイントをわれわれも分析し、投資家の投資基準に当てはまる発行体は、どういうところなのかということを、膨大な発行体リストの中から、事前に把握する作業を行います。発行体のニーズと投資家のニーズが、このあたりで合うのでは、といった風に、作業を進めていきます。
――SMBC日興でサムライ債を手掛けている担当者は何人ぐらい、いますか。
木下氏 : サムライ債の引き受け担当者としては、東京では私を除いて専門的にみているのが7人です。後は、海外の資本市場で債券を担当している面々が、米国で40人ほどいます。欧州にもロンドン、フランクフルト、パリなどの拠点で、それぞれ担当者がいます。アジアにも香港、シンガポールに債券担当の専門家を置いており、。グローバルで見ると人数は多いです。
――海外の担当者はサムライ債だけをみているわけではないですよね。
木下氏 : そうですね。海外の担当者はサムライ債のほかに、ドル債やユーロ債のほか、ローカル市場での債券の引き受けも業務としています。
――他の日本の証券会社も同様に、債券の引き受け部門にはそれぞれかなりの人を配置していると思いますが、その中で、SMBC日興がサムライ債市場で強い理由はどういう点にありますか。
木下氏 : 債券市場の担当体制については、日本の各証券会社は大体、同じようだと思います。その中で、われわれの特徴の一つは、SMBCグループとして幅広く顧客企業をカバーしているという点です。グループでしっかりと連携してカバーできている、と思っています。
――これまで手掛けてきたESGサムライ債はどれくらいありますか?
木下氏 : 2022年度からのデータですと、ESGサムライ債の発行体はソブリン、金融機関を合わせた市場全体で22年度は5件、23年度が3件、24年度が現時点で7件となっています。このうち、わが社が手掛けたのは、22年度が2件、23年度が3件、24年度が6件で、2018年度から引き受けランキング(SMBC日興調べ)で1位を続けています。
――発行体は、ソブリンと銀行などで違いはありますか。
木下氏 : ソブリンは国なので、ESGの観点では、それなりの起債ニーズなり、資金調達ニーズというのはあると思います。銀行の場合も、ESG関連のレンディングニーズがあるため、ESG債の発行ニーズは相応にあります。
――国の場合のソブリン債のESG債の発行ニーズは、独仏などの主要国においてもそれなりに発行ニーズがあります。実際に独仏などは、グリーンボンド国債なども大量に定期的に発行していますよね。一方で、今回のスロベニア共和国や、アジアの国々とかは、これから発行を増やしていくところだと思います。SMBC日興証券にとってのターゲットは、既存の大規模発行国か、これからESG債発行を掘り起こせそうな国々か、あるいは今後発行が増えそうな途上国などの、いずれに置いていますか。
木下氏 : そこが難しいところです。われわれとしては、いろんな発行体に幅広くサムライ債を発行して欲しいと思っています。しかし、たとえばG7のような主要国になると、円建てのサムライ債はなかなか発行してもらえません。その理由の一つには、サムライ債は円で発行するので、発行後に通貨スワップで必要通貨に替える必要があり、その分、調達コストが高くなってしまうことがあります。また市場規模も関係してきます。
大国の発行になると、一度に調達する金額も大きくなります。そうするとサムライ市場では、ちょっと規模が小さいということもあると思います。投資家の側も、先進国の発行体の場合、条件が魅力的ではないため、日本の投資家はなかなか買いづらくなります。発行体と投資家のニーズがちょうど合うのが、いわゆるエマージングマーケットの発行体による国債であり、今のサムライ債市場には合っているのかな、と考えています。
最近の発行体でみても、たとえば24年のESGサムライ債の発行体は、ソブリンでは、インドネシア、メキシコ、スロベニア、ハンガリー、ルーマニアなどの国々です。政府系機関としては、韓国輸出入銀行(KEXIM)やラテンアメリカの地域開発銀行であるラプラタ河流域開発基金(FONPLATA)なども発行しています。

――ESGサムライ債の主な投資家は機関投資家ですか?
木下氏 : 機関投資家がメインですが、日本の場合は学校法人や宗教法人などもサムライ債の幅広い投資家層になります。基本的に、日本の投資家の多くは、どちらかというと、投資した後、償還期限まで保有し続ける「バイ&ホールド」の投資スタイルをとるところが多いです。
――そこは発行体にとって、安心材料になると。
木下氏 : そうですね、確かに、その点は発行体にとって、「いいところ」だと思います。
――われわれのサステナブルファイナンス大賞の表彰でも、ESGサムライ債の発行での表彰は、2021年にグリーンサムライ国債を発行したハンガリーが一番、最初でした。同国はその後も、同ESGサムライ国債を毎年のように発行しています。一度発行すると、定期的な発行につながるようですね。
木下氏 : そうですね。ハンガリーはその前の2018年に最初のサムライ債を発行しています。
――国が資金調達をする際、その国の社会的課題への予算上での資金配分が前提になると思います。ですので、今回、スロベニアが発行した「ソブリンソーシャルサムライ債」などのESGサムライ債の発行などは、他の国でも似たような発行ニーズがあると思います。そうした予算ニーズを前提とした発行の場合、一般的なサムライ債の方が使い勝手が自由になるのでいいのか、あるいは資金使途を明確化したESGサムライ債が好まれるのでしょうか。
木下氏 : 特にソブリンの発行体(国)の動きをみると、ESGサムライ債を選択する動きは増えていると思います。ただ、ESG債の場合は予算との絡みもあるので、いくらでも発行できるわけではありません。各国の予算編成の状況をみながら、新年度は予算としてどれくらいの債券での起債ニーズがあり、そのうちESG債のニーズはどれくらいか、さらに、それをどの市場で、いくら発行するかということを、発行体が決めていきます。例えば、ドル債やユーロ債、オーストラリアドル債、あるいは中国人民元建てのパンダ債などのマーケットで、どれくらい発行するかを発行体が決めていきます。証券会社はそれらの発行の際の条件等も含めて提案し、発行体はそれらの提案も踏まえて、どの市場でどれだけ発行するかを決めることになります。

当然ですが、わが社は、サムライ債のライバルとなる他の発行市場も意識しています。たとえば発行体にパンダ債で出したいという意向があるようだと、サムライ債のほうがパンダ債やドル債よりも、有利な点を発行体に理解してもらうために、サムライ債を発行する意義やメリットを説明します。サムライ債には通貨スワップのコストが加わりますが、それだけを発行体が重視するのではなく、最近は、発行市場の多様化を重視する発行体が多いです。
――サムライ債のメリットとして、投資家に「バイ&ホールド(投資したら償還まで保有し続けるという意味)」の安定した投資家が多いという点がありますが、それ以外にサムライ債をアピールするメリットは何でしょうか。
木下氏 : グローバルにみると、日本の債券市場も相当大きな市場です。そこに外貨建て債券投資には必ずしもアクセスしていない投資家層が相当数、存在しています。その意味は、発行体はサムライ債市場で新しい投資家層にアクセスできるということであり、資金調達の多様化を図るうえで、サムライ債市場は十分に意義があるといえます。例えば、仮に米国でかつてのリーマンショックのようなイベントが起きて、米国での資金調達が難しくなるような場合、日本市場には相当数の投資家が存在し、市場規模も小さくないので、ある程度のファイナンスはできます。したがって、発行体にとっては、調達市場の多様化は「保険」としての役割にもなるので、重要になってくるかと思います。
――サムライ市場拡大の活動をしている金融機関は、日本の財務省にも、もっと褒めてもらってもいいですよね。褒めてもらっていますか。
木下氏 : (役所とは)業務上、そうしたお話をする機会はありませんが、円の国際化は重要なテーマだと思っています。米国のドル債市場をみていると、海外の発行体がどんどんドル債を発行しています。そのドル債を買う投資家は米国の投資家だけではなく、いろんな国の投資家が買っています。日本の投資家も買います。これはユーロ市場でも同じです。われわれは、円債もいろんな国の投資家に買ってもらうべきと考えています。従来、多くの発行体にとっては、「円債市場=日本の投資家」という発想になりがちでしたが、発行体のみならず投資家の観点でも、一層、円債市場の国際化が進むほうがいいと思っています。したがって海外の発行体にもどんどん円建て外債(サムライ債)市場に来てもらいたいし、発行したサムライ債も海外の投資家にどんどん買ってもらえるようにしたいと考えています。
――そうした発行体、投資家双方にとって今後、サムライ債市場をさらに拡大するうえで、どういう取り組みが必要でしょうか。
木下氏 : 発行体がサムライ債を起債する際、日本語の目論見書を作成する必要があります。海外の発行体にとっては手間とコストがかかります。海外の投資家がサムライ債に投資する場合も言語の問題が生じます。法規制がどこまで緩和されるかで、発行体および投資家の市場参入の度合いは変わってくると思います。ただ、緩和しすぎると国内の投資家保護の問題も出てきますので、バランスをどうとるかが難しいところだと思います。海外の発行体を増やすためには、いろんな柔軟な発想があってもいいのでは、とも思います。
――ESGサムライ債の販売では日本の投資家が中心ですか。
木下氏 : わが社は海外投資家にも働きかけています。地域的にはアジア・欧州の投資家も買手の対象に入ります。米国の投資家は、米国の規制上、サムライ債は買えません。
――今後のサムライ債市場の展開をどうみていますか。
木下氏 : さらに成長していくと考えています。わが社も、そうすべく、マーケットの拡大を考えながら、新しい発行体にサムライ債市場に来てもらうために、ESG債のように、新たな切り口を考えていきたいと思っています。投資家についても、日本の投資家だけでなく、円の国際化という観点で海外の新しい投資家にも来てもらえるように取り組んでいます。マーケットが拡大するということは、発行体にとっても、投資家にとってもいいことであり、わが社にとってもいいことになります。
わが社はサムライ債市場でのリーダーとして、市場の拡大を常に意識し、円の国際化も意識しています。ESGサムライ債は、そうした考えの中から出てくる必然的なテーマの一つです。引き続きESGサムライ債に力を入れていきたいと思っています。
(聞き手は 藤井良広)









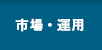




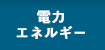







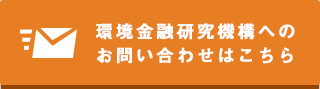










 Research Institute for Environmental Finance
Research Institute for Environmental Finance