第10回サステナブルファイナンス大賞インタビュー⑩優秀賞。三井住友フィナンシャルグループ。日本初の水素投資に特化した「水素ファンド」へ出資・運営に参加(RIEF)
2025-02-26 15:23:59

(写真は、三井住友銀行の理事グローバルバンキング部門、ホールセール部門統括責任役員補佐の金子忠裕氏㊧と、サステナブルソリューション部エンゲージメントグループ上席部長代理の長沢翔太氏㊨)
三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)は、日本初の水素関連分野への投資に特化したファンド「Japan Hydrogen Fund(水素ファンド)」に出資するとともに、同水素ファンドの運営に参画し、サステナブルファイナンス大賞の優秀賞に選ばれました。水素の普及によるCO2排出削減、日本社会・企業への波及、水素関連分野への民間資金のさらなる呼び込みなどのインパクト創出が期待されます。担当者の三井住友銀行理事、グローバルバンキング部門、ホールセール部門統括責任役員補佐の金子忠裕(かねこ・ただひろ)氏に、取り組みの特徴と手ごたえを聞きました。
―― この度の水素ファンドの立ち上げをはじめ、水素事業のインフラストラクチャーの整備は、世界の中でとりわけ日本が熱心に、先行していますね。
金子氏 : 民間企業の水素事業の構築、水素の社会実装の取り組みは2020年12月設立の「水素バリューチェーン推進協議会(JH2A)」が進めています。設立当初は90社程度の任意団体でしたが、今では加盟企業団体数470社と非常に大きな一般社団法人になっています。トヨタ自動車、岩谷産業、それとSMFGの3社が、設立時より会長企業としてリーダーシップを発揮しています。座組(ざぐみ)は、トヨタ自動車が需要サイドを、岩谷産業が供給サイドを、SMFGが金融を担当する形となっています。
日本の水素への取り組みが進んでいるのは、2017年に日本政府が他国に先んじて「水素基本戦略」を打ち出したことが大きいと思います。民間企業も、脱炭素社会を目指す上では水素がカギになる、水素を社会実装していくためには業界の壁を越えて協力していく団体が必要になる、ということでJH2Aの立ち上げに至りました。
水素ファンドの話は、このJH2Aのスタート時から出ていました。設立から3年半余経った昨年8月、ファーストクローズし、それを元手に投資活動がいま足元で始まりました。
―― ファンドの仕組みを採用した理由を教えてください。
金子氏 : 新しいエネルギーインフラが立ち上がってくる局面では、われわれは銀行ですが、銀行が提供するシニアファイナンスのローンだけでは不十分で、出資等のエクイティーやリスクマネーの供給が必要になるということを、JH2A設立時に議論していました。それで水素ファンドを作ろうという話になったのです。このファンドは、水素関連の事業を展開する企業にエクイティーを出す、エクイティーファンドになります。

菅義偉元首相が2020年10月、「2050年にカーボンニュートラルを目指す」と宣言した直後に、経済産業省が開催した「クライメート・イノベーション・ダイアログ」という会議で、水素事業にリスクマネーを供給するスキームとして、ファンドのアイデアを提案し、参加者や経産省から意見を頂いたりしていました。
水素投資に特化したファンドは日本では初めてです。グローバルで見ると、フランスのアセットマネジメント会社が水素投資に特化した「Clean H2 Infra Fund」というファンドを2021年に設立しています。
―― 水素ファンドに対する投資家の反応はどうですか。
金子氏 : 2024年8月にファーストクローズを、12月にセカンドクローズをしました。ファーストクローズでは4億㌦強を集めました。われわれのグループの三井住友銀行(SMBC)もアンカーの1社として出資していますが、ファーストクローズとしては結構しっかり集めることができたと思っています。
このファンドは、今後、2050年あるいはその先に向けて水素の社会実装が進んでいく中において、黎明期のファーストステップであると考えています。今後、例えばより幅広い用途で水素が大量に使われるような世界観では、もっと大きな投資が必要になります。
発電や製鉄に水素が使われるようになると、おそらく使う絶対量がものすごく増えるので、この1号ファンドで終わりではなく、さらに規模が大きい2号ファンド、3号ファンドが必要になると考えています。
―― ファンドに集まった資金は、 まずはどういったところで使われますか。
金子氏 : 1号案件は年明けにアドバンテッジパートナーズ(Advantage Partners)からプレスリリースがありましたが、アメリカのインフィニウム(Infinium、本社:米カリフォルニア州)にエクイティーを出しました。同社は、水素とCO2ないしCOを合成してつくる航空燃料、e-SAF(e-Sustainable Aviation Fuel)をはじめとする合成燃料のデベロッパー会社です。
アドバンテッジパートナーズは、グローバルにざっくり100件ぐらいの投資候補を持ち、その中の有望案件について、すでにいくつかで投資の検討が進んでいて、まもなく2号案件が出る予定と聞いています。
―― 金融面のサポート体制が整いつつあるということですね。
金子氏 : 少しずつ風穴が開き始めた感じです。今回のファンドは基本的に収益をしっかり出していくファンドです。投資対象がしっかりビジネス化できるかというところを非常に厳しく見ています。エネルギー分野のビジネスは、作ったエネルギーの最終的な引き取り手が確実に見えてくる関係に仕上がらないと、ビジネスとして成功しません。その点、e-SAFは、最終的な引き取り手がしっかり見えつつあります。
航空業界の国際機関であるICAO(International Civil Aviation Organization)は、2030年に向けたSAFの導入目標を掲げています。合成燃料のSAFはまだまだ製造コストが高いのですが、廃食油やバイオ燃料からつくるSAFは絶対量に限りがあり、脱炭素を進めていくには合成燃料に頼らざるを得ないと考えています。
――水素は、グリーン水素とかブルー水素とかピンク水素とかグレー水素とか、製造方法によって脱炭素の度合いの違いが区分されることがあります。水素ファンドはどういった水素の製造方法を後押しすることになりますか。
金子氏 : JH2Aとしては、水素1kgを製造するにあたって排出するCO2が3.4 kg以下のものを「低炭素の水素」と呼びましょうと日本政府に提言をしており、色による定義づけはしておらず、基本的に低炭素水素が対象です。1号案件のe-SAFはCO2を排出しないグリーン案件です。

―― 気候変動問題に対処するためのエネルギーインフラの転換には、最終的にどの程度の規模の金融支援が必要になるのでしょう。
金子氏 : 金融業界では、日本の都市ガスがLNG(液化天然ガス)に置き換わった時のことが参考になるのではないかと言われています。ガス会社が腹を決めてドンとやられて、金融機関もサポートに入りました。
LNGタンカーという新しい船がどんどん建造され、対応するインフラが急速に大きくなっていきました。ファイナンスのほうも、LNGが普及していく過程でプロジェクトファイナンスの仕組みが発展していったと聞いております。当時の取り組みとか、LNGに対するファイナンスが、参考になると思います。
銀行の根源的な社会へのバリューとして、銀行が太鼓判を押して融資する産業は何倍にも広がっていく、という信用創造機能があります。新しいエネルギーインフラが広がっていく時は、最終的に銀行の信用創造機能がワークする形に持っていかないといけません。まずはファンドでリスクマネーを供給し、リスクを低減していくことで、シニアなファイナンスも寄り付きやすくなります。その過程が必要だと思います。
―― 水素事業は温室効果ガス(GHG)排出ネットゼロに向けてどの程度重要と考えていますか。
金子氏 : 20年も30年も事業会社で水素事業に従事している人から、過去3回ぐらい水素の波があったが、熱はすぐ冷めたと聞いたことがあります。しかし、今回は2050年カーボンニュートラル宣言が出て、本当に脱炭素を進めないといけなくなったという点で異なります。
その上で、例えば、今世紀半ばまでに脱炭素を実現する日本のパスウェイについて議論する産学連携プラットフォーム「ETI-CGC(Energy Transition Initiative – Center for Global Commons)」の分析では、GHG排出量のネットゼロを2050年に実現するには、エネルギーミックスの中に水素を入れるのが不可欠という分析になっています。水素は、足元は価格が高いが、取り組んでいかざるを得ないアイテムだと理解しています。
IPCC(気候変動に関する政府間パネル:Intergovernmental Panel on Climate Change)の分析も、過去10年でかなり精緻化が進みました。気候変動のサイエンスそのものがブラッシュアップされ、2050年をターゲットとして、地球の平均気温の上昇を抑制していかないといけないことが非常にはっきりしました。これまでCO2は出すよりは出さないほうがいいよね、というレベルだったのが、2050年に向けてどこまで抑えないといけないのかが明確になりました。
脱炭素は、人類が今後何十年間に渡り、しっかりタックルしていかないといけない地球規模の課題だということが明確化しました。水素への注目には波があったと言いましたが、もう本当に本気で取り組まなければならないと考えます。
―― SMFGはいつ頃から水素に注目していたのですか。
金子氏 : 2015年からです。当時「成長産業クラスター」という部署があり、その中で将来成長産業になりそうなところに目をつけ、いくつかテーマを選定していました。その一つが水素でした。
水素に特化したファンドを立ち上げるにあたっては、2015年からずっと水素というテーマにロックオンしてきた経緯から、われわれには金融業界の中で「言い出しっぺ」になり、リーダーシップをとらなければならないとの責任感があると思っています。
(聞き手は 宮﨑知己)









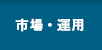




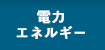







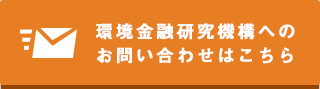










 Research Institute for Environmental Finance
Research Institute for Environmental Finance