「国連環境計画(UNEP)」2024年排出量ギャップレポートで、日本はNDCの達成可能性「低い」と評価。G20の「先進国」中で唯一、「排出量削減策の透明性欠く」との評価も(RIEF)
2024-10-25 17:22:11

国連環境計画(UNEP)は24日、世界各国の温室効果ガス(GHG)排出量の動向を示す「2024年ギャップレポート」を公表した。2023年の世界のGHG排出量は前年比1.3%増の571億㌧で、減少どころか、過去最多の排出量だった。このままではパリ協定で合意した、産業革命前からの気温上昇を1.5℃に抑制する目標から大きく離れ、最大3.1℃になる可能性があるという。排出量の多いG20(主要20カ国)のNDCs達成見通しでは、EUや中国等は達成可能と評価されたが、日本は米国などとともに「可能性は低い」組に分類された。日本の現在の気候政策では、一人当たり排出量は「1.5℃目標」どころか、NDC目標も達成できず、削減政策の透明性も欠いている、とも指摘されている。
UNEPのレポートは、各国の排出量が2050年ネットゼロを目指すパリ協定の目標や、国が公約する削減目標であるNDCsなどと、どれくらいズレ(ギャップ)があるかを示すもの。各国は国際公約のNDCsで「2030年までに年間GHG排出量を42%削減(基準年比)し、2035年までに57%削減するとの目標を掲げている。
しかし、今回対象となった2023年の排出量は過去最多で、依然、世界の排出量は上昇傾向をたどっていることが確認された。現状のままでは各国のNDCs公約は達成不可能だが、仮に達成できても、世界の平均気温は2030年までに2.6~2.8℃上昇し、2050年には最大3.1℃と、「1.5℃」目標の倍以上の上昇になる、としている。
UNEPは、こうした厳しい現実を踏まえながらも「1.5℃の目標を達成することは依然として技術的には可能。そのためにはG20諸国が主導する形で、今日からGHG排出量をすべて削減するための大規模な世界的な取り組みを行う必要がある」と各国に緊急の取り組みに踏み切るよう、警告している。

レポートは各国のNDCs目標の「適格性」を評価する分析もしている。複数の独立研究機関の調査報告書を比較する形での評価では、目標達成が可能との評価が多いのは、中国(5機関が〇、1機関が×)、EU(2機関〇、1機関×)、インド(4機関〇)、トルコ(3機関〇)、ロシア(3機関〇、1機関×)、これに対して、米国は評価報告を公表している7機関すべてが×としたほか、日本(3機関×)で、オーストラリア、ブラジル、インドネシアと同じだった。隣国の韓国は1機関〇、2機関×で、南アフリカと同じ評価だった。
中国やインドなどがNDCs目標の達成見通しで〇が多いのは、NDC自体が低めに設定されていることと、従来からの削減対策があまりとられていないことから、「削減余力」が多いという面もある。ただ、「削減余力」が少ないとされる先進国でもEUなどは達成見通しが高く、化石燃料依存で似た経済構造の韓国でも達成〇とする見通しが一つ出ていることから、日本は気候政策の「本気度」に課題があるようだ。

人口当たりの排出量の比較では、カナダ、オーストラリア、米国、ロシアなどのエネルギー産出国の現行の排出量が1人当たり年間17、8~20㌧前後と高く、非エネルギー産出国は10㌧以下だった。このうち、日本は非エネルギー産出国でも年間8㌧前後のレベルで、欧州のEUや英国よりやや高めになっている。現行政策とNDCsでの削減による水準は、日本はいずれも6~7㌧前後で、「1.5℃目標」「2.0℃目標」の水準には届かない。これに対して、EUや英国はいずれも5㌧前後で、「1.5℃目標」には届かないが、「2.0℃目標」のラインは満たせるレベルとの評価だ。

また各国の2050年ネットゼロに向けた気候政策等の項目別の比較評価では、G20のうち「先進国」に分類される国の中で、日本は5つの評価項目のうち、「達成」は2項目、「部分達成」2項目、「未達」1項目と評価された。EU、英国はすべて「達成」、米国とカナダは「達成」3項目、「部分達成」2項目だった。先進国で「未達」の評価があったのは日本だけ。その項目は、「カーボン排出除去」で、CO2排出量を回収・除去するGX政策の実現可能性に対して、国際的な疑問を付された格好だ。









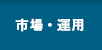




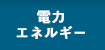







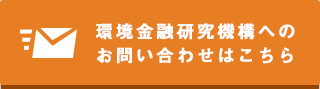










 Research Institute for Environmental Finance
Research Institute for Environmental Finance