第10回サステナブルファイナンス大賞インタビュー⑥NGO/NPO賞。FoE Japan。日本の公的金融機関の支援事業がグローバルサウスの環境・社会・人権等に与える影響等を調査・提言(RIEF)
2025-02-13 21:42:01

(写真は、NGO/NPO賞を受賞するFoEJapan事務局次長の深草亜悠美氏㊧、環境金融研究機構の藤井代表理事㊨)
国際環境NGOのFoE Japanは、日本の公的金融機関である国際協力銀行(JBIC)や日本貿易保険(NEXI)がアジア地域で金融支援する化石燃料事業が環境・社会・人権問題を増大させていることを調査し、提言活動を行ってきたことを評価され、サステナブルファイナンス大賞のNGO/NPO賞に選ばれました。今後も日本の公的金融機関の投融資や、経済産業省が推し進めるアジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)構想やCO2回収・貯留(CCS)事業が、グローバルサウス地域にもたらす悪影響等に警鐘を鳴らす活動が期待されます。FoE Japan事務局次長/気候変動・エネルギー担当の深草亜悠美(ふかくさ・あゆみ)氏に、これまでの実績と今後の方針を聞きました。
――「FoE」 の成り立ちを教えてください。
深草氏 : Friends of the Earth(FoE)は、最初にアメリカで取り組みが始まり、その後、いくつかの国に広がり、さらにグローバルなネットワークを作ろうということで、FoEインターナショナルができ、今は国際的に活動しています。事務局はオランダにあります。FoEインターナショナルのメンバーの多くは、元々、各国で地元に根付いた活動をしていた環境NGOで、FoEインターナショナルが掲げる理念に賛同し、メンバーに加わりました。
こうした成り立ちであるため、FoEインターナショナルは、活動の幅はグローバルですが、組織は地元の状況を第一に考える、グラスルーツ(grassroots:草の根)というか、ボトムアップ(bottom up:現場から上がってくる意見を上層部が積み上げる組織運営方式)の形で運営されています。
各国のFoEメンバーは、オランダの事務局から何か指令が来るとか、資金が渡されるというわけではまったくなくて、それぞれが優先するものにしたがって、お金集めも自分たちでして、活動しています。分散型と言いますか、メンバーがそれぞれの地域に根を下ろしてやっているところが大きな特色です。

ーーFoE Japanは1980年の設立ですね。
深草氏 : FoE Japanは、その他の国のメンバーと設立の経緯が少し違います。FoEインターナショナルのことをよく知る、日本にいた外国の人が、日本にも作らないかと呼び掛け、そこに日本人も含めて何人かで集まって、「フレンズ・オブ・ジ・アース」の日本語訳の「地球の友」という名前で活動を始めました。設立時から、公的金融機関の支援事業の調査と提言に取り組んできました。世界銀行が絡む大型のダム開発や、公的金融機関の金融支援事業が現地で引き起こしている問題について、ほかの団体に先駆けて資金の流れをウォッチし、問題点を突き止めて政府に提言してきました。
ーー国際協力銀行(JBIC)や日本貿易保険(NEXI)の活動については、日本の大手マスコミは十分にウオッチできているように見えません。皆さんは、どうやって調査しているのですか。
深草氏 : 私たちが大事にしているのは、現地の人々の視点に立つということです。事業が行われているインドネシアやフィリピンの市民や団体とまず繋がって、現地の調査をします。そこで得られた声やデータをもとに、JBICなどの公的金融機関に環境社会配慮がどうなっているのか問いただし、改善や撤退を求めるなどの提言活動を行っています。
JBICやNEXIは、遵守すべきガイドラインを持っていますので、それに沿って、もしくは国際的なスタンダードに沿って、提言をします。ただし、それらの環境社会配慮のガイドラインには法的拘束力がありません。それが一つ、大きな課題です。地域の環境NGOや地域住民が「こんな違反がある」とか、「こんな権利侵害がある」と主張しても、JBIC側は「事業者は違反や侵害はないと言っている」として、平行線をたどることもあります。その場合、監督官庁である財務省や国会議員に問題点を伝えます。
私たちが近年、最も注目しているのがエネルギー事業です。海外のエネルギー資源の開発や発電関連事業等。日本の公的金融機関が海外で支援する採掘や発電事業は、日本のエネルギー政策と密接に関係しているで、経済産業省が打ち出す政策もウオッチしています。グリーン・トランスフォーメーション(GX)戦略やAZECに沿った海外でのエネルギー資源獲得事業など、東南アジアでの脱炭素協力事業の中にも、問題事業がたくさんあります。もっとも、エネルギー政策を変えさせるのはハードルが高く、これも課題の一つです。
――日本政府は、自らのエネルギー政策を「地球温暖化防止に最善だ」と主張して、アジア地域に輸出しています。押し付けになっているとの批判もあります。そこから生じる問題を現場からウオッチしているわけですね。インドネシアのチレボン石炭火力発電所2号機に対するJBICやNEXIの金融支援事業の件も、ずっとウオッチしてきましたね。
深草氏 : チレボン石炭火力は長年ウオッチしてきました。現地の方々は1号機による環境破壊を問題視し、2号機の建設に反対していた。そういった声を聞いて、日本政府やJBICに、現地の声を届けていました。そうするうちに、チレボンの元県知事が収賄の罪で起訴されたという汚職のニュースが現地で出たため、JBICにとって事業リスクがあるのではないかと改めて日本政府に伝え、提言を行いました。
――チレボンの問題は地元のNGOやNPOと連携して取り組んできたのですか。
深草氏 : そうです。こちらから主体的に現地の声を聞きに行くこともありますが、地元のNPOとの連携がないと難しいケースもあります。インドネシアのFoEインターナショナルのメンバーは大きな環境団体です。彼らは地元とのつながりが強くて、住民の声を丁寧に聞いています。現地のNGOやNPOから、日本の官民が関わっているようだから協力してくれないかと、コンタクトしてくるケースもあります。

ーー東南アジアの環境問題では日本の公的支援が関係するケースが多いのですか。
深草氏 : インドネシアは多いですね。フィリピンやバングラデシュでもありますが、石炭火力発電事業はやはりインドネシアが多いです。最近も岸田文雄首相の時にAZECが立ち上がって、協力の覚書とか事業の覚書が乱発されました。実際にどれだけ進むか分からないですが、数を見るとインドネシアが非常に多いです。
数年前、G7で、ジャスト・エナジー・トランジション・パートナーシップ(JETP:Just Energy Transition Partnership)という途上国のエネルギー転換を支援する枠組みが立ち上がりました。インドネシアやベトナム、南アフリカなどいくつかの国で進めています。インドネシアは日本とアメリカがリードしており、インドネシアのエネルギー関連事業に対する日本の関心の高さを物語っています。
――日本は途上国の化石燃料事業の存続・延命に力を貸しているなどの批判もあります。
深草氏 : 過去数年でかなり変化がありました。石炭火力発電の案件は減り、代わりにLNGの採掘案件が増えました。ただ、公的な支援という観点では、日本は相変わらずトップクラスで、途上国の化石燃料事業の存続・延命を手助けしています。
――LNGに関しては、先の日米首脳会議で、石破茂首相が米国産LNGの大量購入を「約束」しましたが、すでに日本はLNGのバイヤーとしてものすごく大量に購入していて、自分たちが発電に使う以上に大量に買い込んで、余剰分をアジア等に転売しているとされます。その結果、グローバルレベルでのLNGの採掘需要は日本が加速させている面も強いようです。LNGの採掘拡大については現地ではどうみられているのでしょうか。
深草氏 : LNGの採掘は今、大きなところでは、アメリカ、カナダ、あとモザンビークやインドネシアで拡大しています。言われるように、日本企業は日本国内の発電で使う分だけではなく、他国とのトレーディングのために買い付け量を増やしている面もあります。建前では「日本のエネルギー安全保障上、LNG開発は重要」としていますが、実際はアジアの国々に転売して収益をあげており、化石燃料の取扱いとして、どうなのかと考えると大いに疑問です。
――マレーシアはどうですか。
深草氏 : マレーシアでは、ここ数年にわたり、現地のNGOと連携してかなり力を入れて、CCS(CO2の回収・貯留)事業の問題をウオッチしています。GX政策では、日本が国内で排出したCO2を官民で輸出し、マレーシアの地下に貯留させようとしています。しかし、CCSは技術面での問題があるだけでなく、先進国が途上国に廃棄物(CO2)を輸出するという倫理的な面でも非常に問題があります。さらに、マレーシアの緩い規制を日本の企業が利用し、日本からのプラスチック廃棄物を輸出するなどの問題もあり、自国が搾取される形になっていると考えるマレーシア市民もいるようです。
――CCSの場合、CO2を地下に貯めるのは、ガスや石油を採った採掘跡地に入れるのが一番簡単だと言われています。
深草氏 : CCSの推進者はそういうふうな話をします。ですが、政府資料を見ると、国内にもすごくポテンシャルのある場所があるといったことも同時に書いています。日本はインドネシアのガス田でCCSをやろうとしているので注目しています。
――提言活動の難しさはどこにありますか。
深草氏 : 事業を止めるのはなかなか難しいですが、調査で明らかになった事業リスクを、提言により、できるだけ早い段階で伝えるようにしています。公的金融機関が国民の税金等で集めた公的な資金を、リスクに晒すのはいかがなものかという視点は大きいと思います。

エネルギー事業は大型事業が多く、住民の生計手段への影響は非常に大きい。なので、住民への影響がどうなっているのか、という点が非常に重要だと思います。投融資の契約が締結されてしまってから事業を止めるのは非常に難しいですが、インドネシアやバングラデシュでは、石炭火力発電所の建設が中止になったこともあります。
――提言の際、マスコミにプレスリリースを出していますが、日本のマスコミの反応はいかがですか。
深草氏 : 記事に取り上げてもらうのはなかなか難しいです。ただ、世の中が環境問題で盛り上がっている局面では、取り上げられることもあります。例えば小泉進次郎議員が環境大臣だった時、ベトナムの石炭火力発電事業を問題視して公式の場で言及されました。そういう時はわれわれの活動も注目され、記事に取り上げられます。フィリピンのLNG事業に関して、漁民の方が来日して記者会見をした際も、記事に取り上げられました。国会で質問が出たときは記事になることがあります。
ーー現地の方が来日して記者会見するのがアピールとして効果的なのですね。
深草氏 : はい。チレボン石炭火力の問題についても、現地の人が来日して記者会見をしました。記者会見だけではなく、議員会館を訪問したり、財務省やJBICに直接陳情に行ったりすることもあります。
ーー政府を動かしていくには何が必要だと考えますか。
深草氏 : 気候変動のリスクをもっと周知し、政府のエネルギー政策への提言をもっと積極的に行うことが必要と考えています。エネルギー政策は国民の生活に直結するので、このアングルからもっと色々と発信していきたいと考えています。
――日本のGX戦略は何が問題だと捉えていますか。
深草氏 : グリーントランスフォーメーションと言いながら全然グリーンではないところが問題だと思います。結局、内容としては、今後の10年間で150兆円の官民資金を投じるとしていますが、グリーンが何なのかは定義されてないので、誕生する事業がグリーンなのかわかりません。GX移行債も使う時の環境社会配慮というのがまったくないと思います。国内では原発再稼働、新設も含めて原発推進の色が濃いように思います。
ーー岸田政権は政権末期に原発再稼働本格化の道筋をつけました。今回、石破政権下で策定される第7次エネルギー基本計画はさらに原発の稼働を促進するものになるようです。原発についてはどのようにみていますか。
深草氏 : エネルギー基本計画は非常に重要です。ありとあらゆるセクターのシグナル、指標になると思いますが、では、過去の基本計画が現実に沿っていたかというと、実は乖離があったと思います。第7次計画では、化石燃料への依存や原発依存を、大幅に方針転換すべきだと思います。一方でそれが決まったところで、どれだけ原発についてやれるかというと、新設は非常に厳しいと考えています。昨年1月の能登半島地震で、原発は国民の安全を脅かすものであることがより明らかになったと思います。事故が起きた時に、周辺の住民が避難できるのかという点が、各自治体にとって大きな問題です。コストも追加の安全対策で非常に上がっています。そう考えると、なぜ省エネや再エネがもっと深掘りできないのか疑問です。
ーー皆さんの活動に対して制限や圧力を受けたことはありますか。
深草氏 : 私たちが一緒に活動してるインドネシアやフィリピン、ラテンアメリカ、アフリカの団体に比べると、日本はそこまで酷い状況ではありませんが、「同調圧力」は強いと思います。例えば若者のグループは、私たちと同じことを言っていたとしてもオンラインで攻撃されています。非常に問題です。われわれ、はだからこそもっと声を上げていかなくではいけないと思っています。
(聞き手は 宮﨑知己)
- <東京建物。大規模建築物で日本初となる「ZEH-M(ネットゼロエネルギーハウス・マンション)」認証のマンションを東京・世田谷で竣工。年間光熱費16万円削減(RIEF)
- The Republic of Slovenia, which issued the world’s first Samurai (yen-denominated) sovereign social bond, was awarded the international prize for sustainable finance. Representatives from the Slovenian Ministry of Finance were interviewed in Japan about the background to the bond issue.>









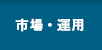




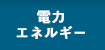







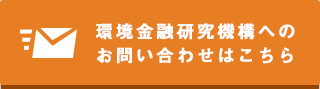










 Research Institute for Environmental Finance
Research Institute for Environmental Finance