第10回サステナブルファイナンス大賞インタビュー⑫特別賞。東京CPB(コミュニティパワーバンク)。バブル崩壊で地域にお金が回らず、市民自ら設立したNPOバンクが20年の活動(RIEF)
2025-03-11 21:59:17

(写真は、サステナブルファイナンス大賞授賞式での写真=東京CPBのサイトから)
NPOバンクの東京CPB(コミュニティパワーバンク)は、バブル崩壊後の2003年に東京で立ち上がりました。デフレで市民や街の活動に必要なお金が回らなくなる中で、日本各地で市民自らが善意のおカネを融通し合う同バンクが相次いで誕生し、活動を続けました。東京CPBはその一つ。20年に及ぶ活動を経て、本年で活動を終了させることで、第10回サステナブルファイナンス大賞の特別賞に選ばれました。CPBの事務局長の坪井眞里(つぼい・まり)氏に話を聞きました。
――市民の手でNPOバンクを立ち上げようと思ったきっかけは何でしたか。
坪井氏 東京CPBの設立は2003年でした。その2年間ぐらい前から準備期間があり、先行して活動をしていた「未来バンク」(東京)、「女性・市民信用組合設立準備会(その後、「女性・市民コミュニティバンク」)」(神奈川)などの活動を学んだりしていました。元々、生活クラブ生協の活動をしていたのですが、神戸の震災への支援活動等が終わって、これからは市民の時代、という機運がありました。1998年のNPO法施行にも組織を上げて取り組みました。生活クラブもいろんな機能を持とうということで、環境活動の一環としてリサイクルショップの組織を作ったり、都市農業を助ける援農の仕組み等も作りました。
生協クラブでは、ワーカーズ・コレクティブという労働者の協同組合でさまざまな起業を始めました。2000年には介護保険法が施行され、福祉関係のNPOがたくさん立ち上がっていました。私たちには「地域でできることは自分たちでやらないといけない」みたいな気持ちがあって、思いも仲間もあるけどでもいつもおカネは足りないよね、という状況でしたね。地域通貨についても学びました。そうしたいくつかの要素から、地域事業を起こす女性たちにもっとお金が行ったらいいよね、という声が高まったのが、そもそもの動機です。
――モデルは米国のCDFI(コミュニティ開発金融機関)ですか。
坪井氏 いえ、向田さんのところです。あそこは、もうできていた。未来バンクもあって田中優さんの話も聞きに行きました。銀行に預金しても、預金者が関与できない資金の使われ方をするのはおかしいね、という問題意識を共有したのと、「女性市民」のほうは、神奈川で活動されていたので、「神奈川でできるのだったら東京でもできるのでは」ということで、皆さんの後からついていった感じです。

市民活動を頑張ってやっていくには、おカネは大事だ、ということで、お金の勉強をして、最初は付け焼刃でしたが、やっちゃいました。
――順調に船出しましたか。
坪井氏 2003年に立ち上げて2004年にまず貸しました。実は、この時に、怪しい人たちに貸してしまい、しばらくへこみました。結局、この1件は焦げ付きました。
――借り手は雲隠れですか
坪井氏 回収のためにその借り手の連帯保証人の家まで行ったり、結構、「鬼」になって取り立てをやりました。借り手の家に行くと、ガスも止められていて、本人は雲隠れでした。書類の住所もウソでした。それをこちらが見破られなかったのですから、われわれの力量不足でした。
――世の中、善意の人ばかりではないので、仕方がないですね。
坪井氏 私たちが、『甘ちゃん』でした。弁護士さんに「どうしましょう」と相談をしたら、弁護士さんから「一応、時効はあるが、最後まで取り立てるのは、出資した人に対する、貸した人の責任ですよ」と言われました。「これからは、知らない人には貸さないように」とも。確かにそうだと思いました。同案件については、5年ぐらい取り立てを続けましたが、どうしても無理ということで、みんなで話し合って損金処理をしました。
――最初に「つまずき」はあったということですが、その後は順調でしたか。
坪井氏 個人は一口5万円の出資金、団体は3口以上で資金を集めて、通常の融資は年1.0%、つなぎ融資は同0.8%で、返済期間は最長5年としました。東京CPBの特徴として、「ともだち融資団」という仕組みも作りました。特定の事業を推進するために、複数の人が連帯で出資者になり、融資金を完済するまで、それらの出資は引き上げないという約束で融資するものです。実質的に融資金額相当分を全て「ともだち」が出資する「100%ともだち融資団」も編み出しました。
もう一つの特徴は、市民自らが融資判断をする「市民審査委員会」によって、金融機関が貸し出すことが出来なかった市民活動などの分野にも、融資を続けた点です。審査委員には金融の経験のある専門家もいましたが、弁当やパンの製造業の方や、福祉の方などもいました。
市民がみんなでお金を出し合って集めた資金を、市民の活動に貸し出しました。20年間で融資件数は114件、融資総額5億8160万円。これに社会的投資2件、2300万円がありました。焦げ付きは、先にご説明した最初のころの1件(400万円)だけでした。
――どういう市民活動に融資されたのですか。
坪井氏 いろんな方々のツテもあって紹介してもらったりしました。たとえば、ホームレスを支援している団体や、引き込もりの人たちと一緒に仕事をする活動をしている団体などもありました。世の中には、社会的に弱い立場の人たちがいることはわかっていました。ですが、東京CPBの活動をする前は、実際にはそうした人たちと、交流したことはありませんでした。実際に会ってみて、大変なご苦労をしていることを目の当たりにし、さらに、その人たちを支援している人たちがいる、ということを知って、これは「希望」だ、という風に思いましたし、そこに東京CPBのおカネを使うことをできたのはよかったと思います。ホームレス支援にも引きこもり支援にも、複数回融資しました。

――それらは回収できましたか。
坪井氏 もちろん。
――そうした事業におカネを回したことは、NPOバンクを立ち上げた手応えがあったということですね。
坪井氏 そうですね。コミュニケーションというか信頼関係を作りながら貸していかなければならないということを学びましたので、借り手の方々はうるさかったとも思いますが、相手の事業所や活動拠点に、しょっちゅう通って、現場を見せてもらって支援を続けました。特にホームレス支援とかは、怪しい人たちの動きもあるようなので、正直に支援に取り組んでいる方々も苦労が多いようですが、われわれも借り手の方々が誠意をもって取り組んでいることを自分たちが納得できるまで、相手の活動の現場にも通ったり、彼らがやっているイベントや勉強会にも参加して、その活動を理解することに努め、出資者にもニュースで報告しました。
――2006年の貸金業法改正の時には、金融庁から市民の手によるNPOバンクも「貸金業者」として扱われ、大変な苦労をされましたね。
坪井氏 同法改正は、多重債務者問題を解決するため、貸金業者の資格審査の厳格化や、貸出先へのチェック体制等を強化するためのものでしたが、NPOバンクも事業者等に融資をしていることから、行政から貸金業者と同じ扱いを求められました。貸金業に参入する条件の強化では、最初の案では、事業者の資金規模を2000万円でした。これでは新たに立ち上げようとするNPOバンクは絶対無理です。金融庁等との交渉の結果、500万円まで減らしました。
一番大変だったのは、NPOバンクも貸金業者と同列で、指定信用情報機関に必ず入って、貸出情報をすべて登録しなければならないという規制の導入でした。私たちの融資で求める連帯保証人の情報も登録が求められたのです。連帯保証人として同機関に登録されると、その方々は、後々、住宅ローン等をくめなくなる可能性があることがわかりました。それで、全国のNPOバンクが連帯して反対運動を起こし、政治家の方々に陳情にも行きました。NPOバンクと一般の貸金業者との違いを理解していただくのが結構大変でしたね。でも結局「特定非営利金融法人」という貸金業法上の特例を勝ち取りました。
――金融庁はそれまで、多重債務対策と、市民のためのNPOバンク対応を、同列で扱う視点しかなかったのですね。欧米では市民の手によるCDFIや協同組合型の非営利金融は、営利の金融業とは別ものとして扱われます。特に、米国ではCDFI等の市民金融には財務省が無コストの補助金を毎年配分し、出資金には税額控除もあります。個人が自分の資産であるおカネを貸す判断は、個人の自由で、個人の基本的権利に関わるものとの理解だと思います。政府は個人及び非営利の地域活動を規制するよりも、むしろそうした個人の資金がコミュニティで円滑に活用されるよう支援すべきという立場です。
坪井氏 貸金業法での取扱主任者の設置義務もNPOバンクにも課されます。同資格を取る試験は結構難しく、試験自体も以前は年4回だったのが、今は1回に絞られ、合格率は低くなっています。キリスト教の教会の信者さんが中心になって信者同士での資金の融通をしていた日本共助組合さんも、取り扱い主任の義務化に対応できず、活動を停止しました。また、金融ADRへの加入の義務付けも残っています。信頼関係の金融だから不要なのだ、と何度も抗議しましたが無視され、貸金業法で厳格に縛られていることはNPOバンク継続の足かせになっています。
――地域の信用金庫や信用組合も、NPO向けの融資事業に取り組むようになっていますが、彼らの活動がNPOバンクの代わりになるのでしょうか。
坪井氏 日本政策金融公庫などもNPO向けの融資に力を入れています。地域の信金・信組などもそうです。ただ、今、金利が上がってくる中で、これらの地域金融機関等のNPO融資やコミュニティ融資が継続されるかどうかは、よくわかりません。営利の金融並みの金利をとったりするようだと困りますね。
――NPOバンクのこの四半世紀の動きは何だったと思いますか。

坪井氏 後世の人たちがどう評価するかわかりませんが、何か「風穴(かざあな)」は開けてきたのかなという風には思います。それは、NPO金融や同ローンなどを市中の金融機関がやりだす一つのきっかけにはなったと思うからです。私たちも、「大きく環境を変えよう」とか、「金融の流れを変えよう」などと言ってきました。もちろんそんなに大きい事はできなかったけれど、金融機関も一応、NPOを事業者としてみることができるようになったのではないでしょうか。
――問題は今の政府ですね。市民の相互扶助や支え合いを金融面では認めようとしていない。市民は昔から「お互い様」でやっているのに。
坪井氏 庶民の間での相互扶助は、二宮尊徳の精神や頼母子講とかで、昔からありますよね。どうも政府は、協同組合的な考え方は嫌いなようですね。
――問題は、市民の側よりも、今の政府の側にあるかもしれない。市民は昔から庶民金融でお金を回してきました。
坪井氏 そうですね。われわれの出資なども嫌われました。金融商品取引法でもいじめられたし、われわれの出資は金融商品に該当すると言われたりもしました。ほとんどボランティアでやっている団体に、1000万円も会計士の報酬を払わないといけないような報告書は出せません。それでここでもロビー活動を最初にやりました。出資して助け合うというNPOバンクのコンセプトを、金融庁の人たちは全く理解していない感じがします。
――今後、皆さんの活動を学んで景気がまた悪くなって、お金が回―なくなった時に、自分たちでファイナンスをやろうと立ち上がる人たちが出てきたとして、そういう人たちへ何かメッセージはありますか。
坪井氏 メッセージですか。「意志あるところに道がある」としか、言う以外にないですね。やはり、それしかないですね。みんながやろうと思ったから、やれたという感じですね。
今は地域や起業などは寄付のお金が回っています。クラウドファンディングですね。返済しなくてもいいので資金の受け手には好評だと思います。でもクラウドは一回で終わりになります。それに対して、出資金なら何回も使えるからそちらのほうがいいと思います。ただ、それを運営していくのが大変なんです。
――でも、やることは大変だとわかっていてNPOバンクに参加され、実際に大変なことに出くわして、さらに、その大変なことを乗り越えてやってきましたよね。
坪井氏 そうですね。その点では達成感あります。こんな何もできない私たちが、一人でやったわけではないですが、人様のおカネを生かして、お金を出した人にも喜んでもらえたわけですから。出資金は最終的に全額、出資者約600名に返しました。その際、「ありがとう、よく頑張ったね」と言ってもらえました。本当に良かったと思います。最初のころの焦げ付きも、寄付金がかなりあったので、それと相殺して、何とか運営資金も出ました。誰にも損はさせませんでした。
(聞き手は 藤井良広)
(2024年の授賞者インタビューはこれが最後です)









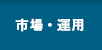




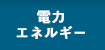







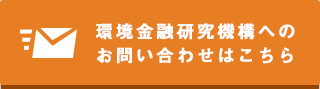










 Research Institute for Environmental Finance
Research Institute for Environmental Finance