(上図 は、人類起源のGHG排出量の増加状況。グラフは下から、化石燃料と産業からのCO2排出量、土地利用の増大等によるCO2吸収量の減少、メタン(CH4)、一酸化2窒素(N2O)、Fガスの各排出量=Climate Change Trackerのデータより)
トランプ米政権をはじめ、気候懐疑論が再び台頭しているが、世界の気候科学者による観測データに基づく最新の評価報告では、「地球は現在のCO2濃度の水準が続けば、パリ協定が抑制目標とする産業革命前以来の気温上昇の「1.5℃」水準を、あと3年で突破する恐れがあることを指摘している。このままではトランプ政権の任期中に、「1.5℃突破」が現実化する可能性があるわけだ。発言修正・言いかえ等を頻繁に繰り返すトランプ氏が、「1.5℃突破」による気候災害の激化に直面した際、どう対応するだろうか。
世界の著名な気候科学者60人以上による共同執筆の報告書「2024年グローバル気候変動指標:気候システムの状態と人間の影響に関する主要指標の年次更新(indicators of Global Climate Change 2024 : annual update of key indicators of the state of the climate system and human influence)」と題する論文が指摘した。同論文は19日付の気候科学論文サイトの「Earth System Science Data(EESD)」に掲載された。https://essd.copernicus.org/articles/17/2641/2025/
それによると、世界の約200カ国が2015年にパリ協定で、世界の平均気温の上昇を産業革命前から「1.5℃」までに抑制する目標で合意し、各国は排出削減政策に取り組んでいる。だが、依然、石油、天然ガス、石炭などの化石燃料への依存度が高いほか、大気中のCO2の吸収源である森林等は伐採の進行を続けている。
人類の経済活動から排出されるGHG排出量の推移(Climate Change Tracker)
今回の報告書の筆頭著者で、英リーズ大学プリーストリー気候未来センター所長を務めるピアーズ・フォースター(Piers M. Forster)教授は、「すべてが間違った方向に進んでいる。前例のない気温上昇の変化だけでなく、地球の温暖化や海面上昇の加速も確認されている。(これらの変化は)以前から予測されていたもので、非常に高いCO2の排出量が直接的な原因であることは明らかだ」と指摘している。
科学者らは2020年初めの段階での「気候変動指標」の分析で、地球の気温上昇を「1.5℃」に抑制できる可能性を50%に保つためには、人類が排出できるCO2量(カーボンバジェット)はあと5000億㌧と試算していた。ところが最近の研究では、2025年初めには「残りのバジェット」は1300億㌧にまで縮小していることが判明している。現在の年間約400億㌧という高水準のCO2排出量が続いた場合、残された1300億㌧の炭素予算は、約3年で使い果たしてしまう計算になる。
カーボンバジェットの急激な縮小は、主にCO2やメタンなどの人類の活動起源による温室効果ガス(GHG)の排出が過去最高を更新し続けていることに加え、科学的な推定精度の向上によるとされる。その結果、昨年2024年の世界の平均気温は、観測史上初めて、19世紀後半の気温の水準から1.5℃以上となった。
ただし1年(12カ月間)だけの気温の上昇だけでは、パリ協定の目標を正式に逸脱したとは見なされていない。また2024年の記録的な高温には、東太平洋海域でのエルニーニョの発生等の自然の変動による気象パターンの変化の影響も加わったとみられる。しかし、今回の研究論文では、24年の世界全体での高温の主因は人為的な温暖化で、その影響による気温の上昇は、産業革命前に比べ、1.36℃の上昇に寄与したと推計している。
また現在の地球全体での気温上昇のスピードは、10年あたりで約0.27℃とみられる。これは、これまでの地質学的な記録の中でも異例の上昇ピッチとされる。このままのピッチでCO2排出量が増大し続けると、地球の平均気温は2030年ごろに1.5℃の上昇に達する見通しで、パリ協定で定められた抑制目標の水準を突破することになる、としている。
気温上昇が「1.5℃」水準を超えた後も、大気中の大量のCO2を吸収・除去すれば、長期的には気温上昇を抑えることが理論上は可能とされる。このため世界中の高炭素排出産業の企業は、大気中からCO2を直接吸収する「DAC」技術等のCO2除去技術の実用化に関心を示している。だが、報告書は、こうした野心的な技術を「免罪符」とすることに警鐘を鳴らしている。実際には、気温上昇が「1.5℃」を大きく超過した場合、DAC技術を導入しても、温暖化の進行を逆転させることは困難との見方が科学者の間で大勢を占める。
今回の報告書では、地球の気候システムに余剰熱が蓄積される速度を表す「地球のエネルギー不均衡」の進展が指摘されている。過去10年ほどの間に、この加熱の速度は1970年代~1980年代の2倍以上となり、2000年代後半から2010年代にかけての水準と比べても約25%高くなっていると推定されている。
同不均衡の増大は、基本的にはGHG排出量の増加に加えて、エアロゾルと呼ばれる微小粒子による冷却効果の減少も影響しているとされる。余剰熱の増大は、陸地を温め、気温を上昇させ、氷を解かすなどの形で影響を及ぼす。その後、約90%は海洋に吸収される形になり、海洋生態系に影響を及ぼすほか、海面上昇要因にもなる。海水が暖かくなると、体積が増えるほか、氷河の融解によって海に流れ込む水も加わるためだ。
世界の海面上昇の速度は1900年代以降で22.8cmの上昇と、年間0.18cmのペースとなるが、最近10年でみると4.3cmの上昇で年間0.43cmの上昇となる。上昇率が倍以上にアップしている計算だ。海面上昇ピッチの早まりは、世界中の沿岸地域に住む数千万人にとって洪水リスクの上昇につながっている。
海面上昇の推移=同上 一方、報告書ではクリーン技術の導入が進む中で、排出量の増加ペースが鈍化している兆しも見られるとの指摘も含んでいる。報告書は、そうした対策の効果を含めて、「迅速かつ厳格な」排出削減が、これまで以上に重要だと強調している。
パリ協定の目標は、気温上昇幅が2℃に達した場合、1.5℃と比べて気候変動の影響がはるかに深刻になるという明確な科学的根拠に基づいて設定されている。したがって、これらの目標はしばしば、1.5℃未満なら「安全」で、1.5℃を超えると「危険」という風に単純化されてみられがちだが、実際には、これらの気温水準での、わずかな上昇でも異常気象や氷河の融解、深刻な海面上昇の影響等が生じることになり、すでに地球全体が「危機的ゾーン」に入っているといえる。
(藤井良広)
https://essd.copernicus.org/articles/17/2641/2025/#&gid=1&pid=1
https://climatechangetracker.org/igcc
https://essd.copernicus.org/articles/17/2641/2025/
https://climate.leeds.ac.uk/6058-2/meet-our-cop28-team/cop28-delegates-piers-forster/











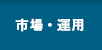




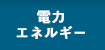








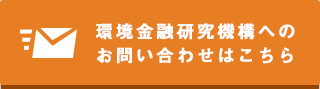










 Research Institute for Environmental Finance
Research Institute for Environmental Finance