第10回サステナブルファイナンス大賞インタビュー④地域金融賞。横浜銀行。自治体のSDGs認証制度と連携した「ソーシャル定期預金」開発。企業の社会的参画ニーズとビジネス支援(RIEF)
2025-02-05 21:23:40

(写真は、サステナブルファイナンス大賞の授賞式で、授賞内容を説明する横浜銀行の松上崇志氏)
横浜銀行は、横浜市のSDGs認証制度と連携したソーシャル定期預金を開発し、サステナブルファイナンス大賞の地域金融賞に選ばれました。地域の中堅・中小企業のSDGs取り組みを、自治体と連携して、市のイベントへの参画につなげることで、預金をする企業の社会的参画ニーズに応えるとともに、ビジネス面での機会創出を支援する仕組みです。横浜銀行営業戦略部グループ長の松上崇志(まつがみ・たかし)氏に、同取組の特徴と手ごたえを聞きました。
―― 横浜銀行のソーシャル定期預金を地域金融賞に選んだのは、横浜市のSDGs認証制度と連携して公平性を確保しながら、企業がSDGsに取り組むうえでの実利性につなげた点を評価しました。今回の仕組みに取り組んだきっかけを教えてください。
松上氏 : われわれの担当領域は銀行の法人部門全体になります。最近は部門全体でも、サステナビリティ戦略に力を入れています。今回のソーシャル定期預金は、1年半ほど前に「これから金利が上がるだろう」という金融情勢を踏まえ、アセットビジネスへの注力と同時に、源泉となる預金戦略を見直したことがきっかけです。当時、横浜銀行単体としては、十分に預金はある認識でしたが、子銀行含めたコンコルディアフィナンシャル・グループ全体での成長を踏まえると、それほど潤沢ではないと判断し、何らかの形で新たな預金の取り組み出来ないかと考えました。
その時点で、横浜銀行ではグリーンボンド原則に基づく、フレームワーク型の外貨建てのグリーン預金はありました。しかし、環境分野を強調した預金集めだと、われわれのメインターゲットである中小企業の顧客の中には、専門用語に少し戸惑ってしまう企業も出るなどして、課題も出ていました。そこで、新たな目線で預金商品を考え、競争力のある高い金利を付けるという方向ではなく、新たな仕組みを提供できないかと考えました。
その際、地域に根差した「ソーシャル」という視点のほうが、幅広い取り組みにつながるのではないかと考えたのです。先行してソーシャル預金を展開していた他地域の信用金庫と情報交換したところ、テリトリーを限定した地域において、法人も個人も、みんなで盛り上げていこうという地域性の取り組みを実践されており、その活動に感銘を受けたこともあります。そこで、より地域性に拘った商品性に仕立てました。

――他業態の信用金庫から学ばれたということですね。
松上氏 : 横浜銀行は地銀で一番大きいので、メガバンクに近い大きな取り組みをやっていると思われることが多いです。地方や地域のことはあまり考えていないのではないかと、誤解される方もいらっしゃるのではと思いますが、そんなことはないのです。このソーシャル預金はまさにその地域に立脚した預金であり、他地域の信用金庫の取り組みを参考にしながらも、横浜の銀行らしく、神奈川県の金融機関らしい面を盛り込もうと考えて、このスキームにたどり着きました。
――地域性を重視したということですね。顧客と銀行との距離感を埋めていくということですか。
松上氏 : 横浜銀行も地域顧客のリテラシー(理解力や能力の向上)を、銀行と顧客が一緒になって、少しずつ引き上げていくことを目指しています。その一環で、顧客へのエンゲージメント活動に力を入れています。ソーシャル預金もこのエンゲージメント活動の一環として、総合的に取り組むことにしました。
――横浜銀行のソーシャル預金で特徴的なのは、横浜市の公的な認定制度を活用したところだと評価しました。同市との連携はスムーズにいきましたか。
松上氏 : 横浜市はSDGsへの取り組みにおいて、某シンクタンクと連携をし、「Y-SDGs」と言う高度な認証制度を設けています。われわれ横浜銀行は、SDGs全体への取り組みもさることながら、スコープを「脱炭素経営」に絞って、顧客企業のエンゲージメント活動を進めております。横浜市が開発した「Y-SDGs」は「ESG+地域」であり、環境分野に限定した取り組みではない点で、正直、それまでは、なかなか連携が取れておりませんでした。しかし、周りを見渡すと、社会の流れは脱炭素一本ではなく、もう少し幅広いソーシャル分野への配慮も増えていることから、より幅広いスコープで進める方向性を判断し、横浜市の認証制度とコラボする方向で進めていきました。
――銀行が単独でやるよりも、公的な自治体と連携するほうが、企業の方も信頼性が高まりますね。
松上氏 : 他の自治体にも、SDGs登録制度等を導入しているところも多く、そこに登録することで登録バッチ等をもらえる仕組みをとっているところも相当数あります。しかし、横浜市の制度が少し違うのは、申請後に厳格な審査を行う点です。「環境、社会、ガバナンス、地域」の4分野、30項目を、横浜市の外郭団体が客観的に審査して、申請企業を訪問のうえ、申請内容をチェックしています。インセンティブの設定もあります。例えば、認証レベルに応じて、公共工事の入札時の評点が加点をされるという仕組みもあり、非常に多くの地元の企業が申請をしています。
――そうした自治体のニーズと、銀行のニーズがうまく組み合わさったということですね。
松上氏 : そうですね。今回、サステナブルファイナンス大賞の地域金融賞を受けたことは、横浜市にも大変喜んでいただいております。
――去年4月から同預金の受け入れを始めて、ほぼ1年ですが、成果はどうですか。
松上氏 : 預金の実績としてはまずまずです。預金企業は、横浜市が展開する企業マッチングイベントでのブースに出展できるメリットを設定しているため、預入条件を狭めてこの一年取り扱いを進めてきました。次年度は諸条件を見直して、より多くの企業から預け入れてもらえることを期待しています。

――預金の受け入れは2026年の3月31日までとなっていますが。
松上氏 : 横浜市からも、この預金制度を続けてほしいというオファーをいただいています。SDGsイベントも、ビジネスへのつながりがあり、さらに他社のサステナビリティへの取り組みを学ぶという面もあります。当行における多くの顧客企業から、ソーシャル預金を通じて、同イベントに参加できる仕組みの継続への期待とニーズがあると思っています。
――金利が少し上がってきました。金利がついてきたことでこの商品への反応に変化は出てきそうですか。
松上氏 : 個人顧客の場合、金利条件が最優先で判断されると思います。一方で、企業顧客の場合は、金利だけですべてが動く訳ではありません。もちろん、一部の宗教法人や学校法人などは、運用を重視されるので金利条件も重要ですが、一般企業の場合は、金利を含め、預金を預けることによって地域の企業を応援する、ということに賛同してくれるところが、少しずつ増えてきたと感じています。
ーー 個人顧客からも「ソーシャル預金」を出してほしいという声はないですか。
松上氏 : 当初は個人顧客も対象にしようと考えていました。ただ、この預金の一番のメリットは、市が主宰するマッチング・イベントに参加することだと思います。個人顧客に広げると、イベント会場のインフラの課題もありますので、現在は法人に限定した商品設計にしています。
個人顧客にはイベントへの出席ではなく、金利の上乗せや、別の利点を付与することなどが考えられます。横浜銀行の個人顧客はプロ野球の「横浜ベイスターズ」のファンが多いので、今は、ベイスターズが勝つと金利が上がる、負けると下がるという「ベイスターズ定期預金」が人気です。野球の力はすごい、ということを改めて感じています。
ーーコンコルディアフィナンシャル・グループ企業間の連携、あるいは提携先との連携の広がり等の展開もありますか。
松上氏 : 一例として、「カーボンオフセット型私募債」があります。これまでは、顧客企業が私募債を発行する際に銀行へ支払う手数料の一部を、様々な環境団体、自然保全団体等に寄付する仕組みが一般的でした。この私募債では、その次のステップとして、国内で初めてカーボンオフセットを自治体に寄付するスキームとしました。手数料の一部で、クレジットや非化石証書等を購入し、神奈川県や横浜市に寄付をして、公的なイベント等の際に使ってもらうのです。
この商品については、わが行と連携協定を締結しているの広島銀行や、ほくほくフィナンシャル・グループでもすでに商品化しています。ソーシャル定期預金も、当行が取り扱いを開始した際には、スキームを教えてほしいといった問い合わせが連携行以外を含めて、多くの銀行からコンタクトがありました。
――ソーシャル預金は今後も続けていくとのことですが、「ソーシャル」以外の「サステナビリティ預金」にするとか、あるいは今後の工夫の余地はどうですか。

松上氏 : サステナブルファイナンス大賞で、メガバンクがインパクト預金で優秀賞を受賞されましたね。われわれも最終形として、そうした社会へのインパクトを意識した商品性をイメージしています。現状は、銀行としてのインパクトについて具体的な数値を用いた整理している段階です。今後、適切なプロセスを経て、実現できればと思っています。
――預金や融資の新商品開発以外で、横浜銀行が力を入れているのはどういう点がですか。
松上氏 : 銀行全体で力を入れているのは、エンゲージメント戦略です。セクター別にエンゲージメント戦略を分けて展開しています。特に、神奈川県は日産自動車のお膝元なので、自動車部品分野に力を入れています。自動車分野のトランジションについては、課題解決の一つとして認識しています。
自動車業界は主に二つの課題に直面していると思っています。一つが温室効果ガス(GHG)排出量の可視化、二つ目がトランジション対応です。後者については、例えば、これまではエンジン回りを作っていたが、電気自動車(EV)になると、これまでの部品・技術等が不要になります。ただ、こうした課題に向き合っていくのは、銀行だけではマンパワー的な点を含めて容易ではないので、公益財団法人の神奈川産業振興センター(KIP)と連携して進めているところです。
国際原則に基づくトランジションスキームは、中小企業にとって取り組みのハードルは高いですが、技術的な「トランジション」を、KIPに認めてもらう認定書のようなものを作ってもらい、それを元にわれわれがファイナンスをつける取り組みを、昨年9月にスタートさせました。
――自動車に絞ったトランジションと言うことですね。おもしろいですね。
松上氏 : トランジションの方法が顕在化してくれば良いのですが、実際は潜在化している段階です。サプライヤー企業の多くは、「何かしなければいけない」と理解はしているものの、新たな技術を開発するのが怖いという声もあります。そこで、KIPのような公的な機関が企業の相談先になり得ると思います。サプライヤーが能動的にEV部品を作れるようになると、自ら上位サプライヤーに売り込む活動も出てくるかもしれません。当行としては、実際に融資に直接つながらなくても、そういった形で能動的に動き始めるサプライヤーを支援して、企業が自ら考える機会を創出することが、地域金融機関として必要な活動だと思っています。そうした仕組みを活性化させていきたいです。
――そうした仕組みは、自動車産業以外の他のセクターでも可能ですね。発電所とか、鉄鋼、化学、セメントなど。
松上氏 : 様々な部分に応用していければいいかもしれません。銀行にはそうした技術の専門人材はいないので、外部の信頼できる機関とうまく連携することが大事です。KIPは、実質的には神奈川県の公的機関なので、ここでも官民連携の仕組みを作ったわけです。
トランジションは不確実な部分が多いので、自動車業界のサプライヤーにとっては死活問題です。そうした中で、金融機関は中間的に同セクターのサプライヤーをサポートしていくのが大事な役割だと思います。
ソーシャル預金に話を戻すと、サステナビリティの領域においては、現状は、能動的に動けていない企業が大半だと思います。そこで預金をきっかけに、全体のリテラシーを上げていけるような取り組みになればいいと思って、あえてフレームワークや国際原則とかに基づかないものを作りました。同預金をきっかけに、様々な企業がお互いに高めあい、地域でつながっていって欲しいと思います。
(聞き手は藤井良広)









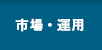




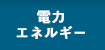







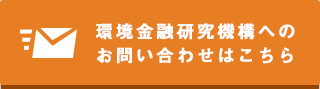










 Research Institute for Environmental Finance
Research Institute for Environmental Finance