第10回サステナブルファイナンス大賞インタビュー⑨地域金融賞。滋賀銀行。グリーン預金と再エネ投資向け融資を「つなぐ」仕組みで、地域のサステナブルな資金循環を高める(RIEF)
2025-02-25 09:40:17

(写真は、サステナブル大賞の授賞式で、取り組み内容を説明する滋賀銀行のサステナブル推進グループ長の宇佐見剛氏)
滋賀銀行は再生可能エネルギー事業を展開する同行グループのエネルギー事業会社向けの投融資資金に充当するグリーン預金を展開することで、環境分野での調達と運用の資金の流れを地域で循環させる仕組みを手掛け、実践していることから、第10回サステナブルファイナンス大賞の地域金融賞に選ばれました。同行総合企画部サステナブル戦略室サステナブル推進グループ長の宇佐見剛(うさみ・たけし)氏に聞きました。
――地域で集めた預金を原資として、再エネ事業等の環境分野へ投融資をする金融の仕組みについては、以前にも似た商品を出そうとした際に、外部から導入預金に似ていると難色を示す声が出るなどの苦労があったと聞いたこともあります。今回、改めて商品化しようと考えた背景を聞かせてください。
宇佐見氏 : 確かに、かつてはいろいろ議論もあったと聞いています。今回、われわれが開発したスキームは、当時とは別物です。導入預金の場合、特定の貸出先に融資するという前提で、その関係先から預金を受け入れる仕組みとされます。今回、開発したものは、そうしたものとは異なります。法人、個人の両方の顧客を対象としたグリーン預金を原資として、太陽光発電、風力発電等の再エネ事業を対象とする事業全体に投融資資金を提供する商品です。個々の預金の資金が、特定の再エネ事業に結びついているわけではありません。2024年4月に滋賀銀が設立した100%子会社の「しがぎんエナジー社」の事業を中心に、再エネ事業に広く融資する仕組みです。
わが行は環境金融取り組みを2000年前後から続けています。当初、想定した環境の範囲は、脱炭素一辺倒ではありませんでした。最初は生態系保全でしたし、現在の第8次中期経営計画では、幅広く環境・社会分野のサステナビリティを設計する「サステナビリティデザインカンパニー」になることを掲げています。ただ、地域のサステナビリティを高めていこうとすると、やはり脱炭素をその中心にしっかりと据えないとだめだろうと考え、今回、改めて脱炭素にフォーカスした仕組みづくりを始めました。
そういう意気込みの一方で、地域のカーボンニュートラル(脱炭素化)は、われわれ単独では当然、できないという課題があります。銀行だけが突っ走っても地域全体が付いてきてくれないと意味がありません。そこで「しがぎんエナジー」を立ち上げ、同社の取り組みを地域が支持してくれる仕組みを考えたのと、地域とファイナンスをつなげることを考えました。特にグリーンの領域では、われわれの足元で、預金のチャネルがなかったことから、その問題を解決する形で展開したいということで商品化を進めました。
――滋賀銀が日本で初めて「環境銀行」を名乗って環境金融に取り組まれた2000年前後から四半世紀を経て、環境分野での調達と運用の資金の流れを地域で循環させる仕組みを手掛けられた点で、滋賀銀の環境金融に対する「熱意」を感じました。

宇佐見氏 : グリーン預金については、サステナビリティを重視する預金のチャネルと資金循環の観点から検討しました。ただ、グリーン預金だけだと、他行もやっており、あまり変わらないものになります。ということで、地域での資金循環を推進するため、「しがぎんエナジー」向けのローン全体をグリーン預金の資金使途先にするという方向性で進めました。
滋賀県内等の太陽光発電所はほとんどが固定価格買取制度(FIT)を踏まえて開発されたものです。ですが、FITの期間終了が迫るという「卒FIT」を展望すると、投資収益があまり見込めないとして、事業をやめてしまう投資家が結構多いのです。しかし、地域にとって太陽光発電所がなくなってしまったら、FIT制度をやった意味もなくなってしまう。
そこで、FIT電源を、卒FIT後もしっかりと地域に残すために、われわれでエネルギー会社を立ち上げ、県内および滋賀銀の営業区域である、大阪、三重、義務、愛知等の各府県でFIT電源を買い取るビジネスを展開することにしたのです。「しがぎんエナジー」の設立後の半年間で、買い取ったFIT太陽光電源は2万kW超に達しています。地域全体のカーボンニュートラルを実現するには、グリーン預金と、しがぎんエナジー向け融資をつなぐ必要があると判断して、両方を推進しています。
――エネルギー子会社が展開する再エネ事業へのファイナンス融資がグリーン預金の使途先ですか。
宇佐見氏 : それだけではありません。銀行の市場部門が運用しているグリーンファイナンスも充当対象になり得ますし、地域内での通常のグリーンローンをはじめ、再エネ事業に投資する融資なども要件さえ満たせば、資金充当先にできるようになっています。ただ、中心になるのは「しがぎんエナジー」向けのファイナンスです。これによって、地域の企業や個人もグリーン預金を通じて、間接的に地域の再エネ発電の維持に貢献できるほか、地域にエネルギー事業を根付かせるための投資を、預金のチャネルを通じてやれます。こうした金融商品はわが国では、おそらくあまりないと考えています。
――「しがぎんエナジー」の活動は卒FITの太陽光発電事業の買い取りが中心ですか。
宇佐見氏 : 現状で投資しているのは太陽光発電のみです。今後は、風力発電やバイオマス発電なども、検討していければと思います、ただ、バイオ系は燃料の問題で難しい面があります。滋賀県には山林は多いのですが、琵琶湖の水源保全のための保安林が多く、あまり森林に手を入れることができず、間伐材も限定的です。風力については風があまり吹く状況ではないのと、琵琶湖はラムサール条約の保護区に指定されており、風力の開発にも制限がかかります。なので、まずは太陽光から進めていくことになります。太陽光のスペースは県内及び周辺県でもまだあります。
仕組みづくりでは、すでに運用済みの太陽光発電事業を、われわれがアセットとして保有する形としました。それによって地域の再エネ事業と、われわれの調達資金との間で資金循環が起きることを重視しました。

――グリーン預金は円建てと外貨建ての両方があるのですね。どれくらい集まっていますか。
宇佐見氏 : 昨年10月に募集を開始し、円建て預金は当初100億円と設定しました。しかし、ほどなく募集枠に到達したので、12月に追加で募集額を増やし、今は200億円の枠です。外貨建てのほうはまだ追加にはなっていませんが、当初募集額の100億円(円貨換算)はすでに超えています。
――法人と個人の両方が対象とのことですが、個人の客層はどういう方々ですか。
宇佐見氏 : 個人の預入額は円建ての場合、1000万円の下限があります。ですので、それなりの資産を保有している方が多いと思われます。企業向けの場合も、1000万円以上としているのと、預入して趣旨に賛同してくれた企業については、銀行のホームページで協力者として名前の一覧リストを出しています。企業の社会貢献活動を外部に知らせる効果も果たしています。法人預金の場合は、大口も多いです。地域金融機関が今、置かれている状況を考えると、銀行を支援する形での預金(粘着性の高い預金)の拡大は必要なので、同預金はそうした役割も果たしているといえます。
――グリーンで脱炭素を重視した形ですが、今回、同じく地域金融賞の対象に選ばれた横浜銀行のソーシャル預金の例では、ソーシャルな分野に対する預金者等の貢献意識が都市部等で高まっていることを反映した形です。滋賀銀でもソーシャル分野に向けたサステナブルファイナンスの商品化は今後、考えられますか。
宇佐見氏 : わが行では、ソーシャル分野での具体的な取り組みがまだ多くないのは確かです。ソーシャルローンは複数回、地域の顧客に対して組成しましたが、なかなか地域全体に社会的なインパクトを与えるような事業を前提とした対応ができているかというと、ソーシャルローン以外には今のところありません。今後、もう少し取り組みを進めたいと思っています。
ESG全般を含めて取り組みの件数は確かに増えていますが、滋賀県全体の比率でみると、非常に大きいというわけではありません。まだまだ環境分野を含めて、育てていかなければならないと思っています。ESGへの取り組みはしないといけないだろうな、でも何していいかわからないという企業も多く、そうした企業を対象としたサービス「未来よしステップ」を昨年10月に始めています。
わが行は取引先企業のESG評価を実施しています。大企業も同じ尺度で評価できる方法です。その結果、規模の小さい中小企業の評価は、大体、低い配点になってしまう傾向があります。そこで中小企業に評価をあげるために取り組み改善を奨めても、(大企業ではないので)そんなことはできない」などとなりがちでした。そこで「未来よしステップは、そこを改善し、低評価の中小企業の場合は、評価項目を細かく設定して企業側が選べるようにしてスコアアップにつながる工夫をするとともに、企業の「意識づけ」と年1回の評価の見直しや、目標に対してどう取り組んだかなどへのエンゲージメントサービスをする仕組みを提供するものです。
目標達成した企業には銀行の支店長がサイン入りの評価書と、当該企業の社長のサイン入りの行動宣言書をセットで渡します。これにより、対象企業の目標とその達成の「見える化」が進むので、企業からも喜んでもらえていると思います。
――企業は自社がESGに取り組んでいることが社会に評価され、かつ企業自身もそれを確認できることになるわけですね。
宇佐見氏 : 従業員に対しても、なぜ環境・社会関係の取り組みをやるのかということを伝えられます。なかなか社会への貢献ということを言語化することは難しい面がありますが、そこをわれわれがお手伝いをしていこうとしています。
実はこの取り組みには、わが行にとっても重要なテーマがあります。支店の営業への効果です。われわれは早くから環境経営を実施していますが、従業員全員が、サステナビリティやESGを語り続けられるわけではありません。サステナブルファイナンスに取り組む顧客は一定以上の融資額になりますが、わが行では少額のファイナンスでも実行できるファイナンスに広げているので、取引先の融資規模が小さい比較的若手行員も、こうした商品を顧客に提案して、ESG評価についての対話ができることになります。その結果、行員もESGを実践的に学べるし、顧客もESG経営に入り易いことになります。
――地銀の間では、滋賀銀から学ぶという声もあります。メガバンクを含めて他行が滋賀銀をみている、という意識はありますか。
宇佐見氏 : 正直、あります。ESGファイナンスのチームは、比較的若くて調査役クラスを中心にしたチームだが、彼らの意識は非常に高く、恥ずかしい案件は作ってはいけない等と考えています。そうした場合、当然、われわれ自身が恥をかくだけでなく、同時に顧客にも恥をかかせることになってしまうからです。なので、しっかりとした形のファイナンスを作ろうという意識が非常に高い。ただ、その結果、どうしても工数が増えたり、質を求めすぎる面もある。そのバランスをとる必要もあると思います。
――今、金融界はESG、サステナブルファイナンスの分野では、競合の声も聞かれます。滋賀銀では、他行がそこまでやるなら、うちはもっとやらないと、といった意識もありますか。
宇佐見氏 : われわれは常に先頭を走ってきたという自負があるので、いろんな取り組みを進めたいと思う一方で、実際には、他行とも幅広く、いろいろと話をしています。「ESGは非競争領域」と認識していますので、情報を共有化してそれぞれの地域でレベルが上がっていけるのならば、日本全体のことを考えれば、それでいいだろうということでやってきています。ただ、だいぶ他行にも追いつかれているなという認識も当然あります。
―――日本の環境金融分野の今後の変化はどうみていますか。
宇佐見氏 : 地域金融機関が提供するメニューは、非常に増えてきたと思います。都道府県レベルで、サステナブルファイナンスを利用できないところは今ほとんどないのではないでしょうか。供給側の体制はかなり浸透してきたと思います。普及促進のためのファイナンスだったり、質を重視したファイナンスだったりと、差はあるかと思いますが、形は何であれ、供給側はかなり充実してきたかなと思います。一方で、利用者、顧客側がどんどん使う時代になっているかとなると、こちらはまだまだ普及の余地はあると思います。どう取り組んでいいかわからないという企業等を、どう後押しするかという課題もあります。
国際的なガイドライン等への適合の評価などには、当然コストもかかります。ただ、必ずしも国際原則にこだわる必要があるのかと考えると、目的はどうやって社会にインパクトを与え、サステナビリティを高めるかがゴールだと思いますので、そこはあまり形にこだわらずなくてもいいかと思っています。
今後ですが、しばらくはサステナブルファイナンスが、顧客への浸透が進む、あるいは浸透を進めることが、第一の優先課題と思っています。いろんなものを組み合わせたようなファイナンススキームやサービスはまだ必要かと思います。たとえば、カーボンニュートラル、サーキュラーエコノミー、ネイチャーポジティブの3つの流れのうち、カーボンニュートラルだけをテーマにしたファイナンスでは今の世の中では結構難しいと思います。そこで、これら3つを組み合わせることで取り組み易くなる、もしくは意識を少しでも向けてもらえるようなサービスとすることは大事だと思います。
個人的意見としては、地域金融は広義のサステナブルファイナンスそのものと考えています。地域の持続可能性をあげていかないと、われわれは成長できない。なので、われわれが行うファイナンスは、当然、サステナブルファイナンスでなければならない、という風に思っています。その辺の考え方については、どうしても狭義に考えてしまう部分がありますが、この辺での境目というのがなくなってくれば、一番いいと思うし、そうしたサステナブルファイナンスは、まさに地域金融のあり方そのものじゃないかと思っています。
(聞き手は 藤井良広)









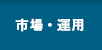




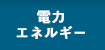







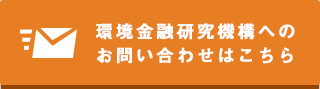










 Research Institute for Environmental Finance
Research Institute for Environmental Finance