第10回サステナブルファイナンス大賞インタビュー⑪地域金融賞。兵庫県信用組合。取引先企業のSDGs取り組みの支援活動。兵庫県の取り組みと連動し企業の「CSR宣言」を後押し(RIEF)
2025-02-28 11:46:08

(写真は、サステナブル大賞の授賞式でスピーチする兵庫県信用組合の橋爪理事長)
兵庫県信用組合は、地域の取引先企業による国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」への取り組みを推進・支援する活動を展開してきたことを評価されて、第10回サステナブルファイナンス大賞の地域金融賞に選ばれました。同信組理事長の橋爪秀明(はしづめ・ひであき)氏にお話を聞きました。
――今回の受賞は地域の事業者に対して国連のSDGsへの取り組みを、金融機関として推進する活動を展開してこられたことを評価するものです。最初に、SDGs取り組み普及促進に取り組んできたきっかけを教えてください。
橋爪氏 : われわれのような、小さな金融機関の地道な活動に光を当てていただき、ありがたく思います。われわれの信用組合は、融資額が2600億円ほどですが、その88%は取引先の中小企業、零細企業への事業性融資です。信用組合としての活動を始めて、この3月で74年になりますが、歴代、中小事業者の取り組みに注力してきました。そしてさらに中小事業者の活動を支え、伸ばしていこうというのが、われわれの基本的な取り組み姿勢です。
兵庫県の企業の特徴は、業種が広く分散している点です。われわれの取引先をみても、製造業が一番多いですが、それ以外にも卸小売、建設、さらに、ズラッと多様な業種の企業が並びます。こうした業種が多様化している地域経済の特徴から、他県の地方銀行等も、かなり進出しているほか、県内には、信用金庫が11金庫、信用組合が6組合、さらにメガバンクや地銀等が競い合っています。ですので、預金を預かって融資をするという競争では、どうしても規模の大きい金融機関には勝てないことになります。このSDGs活動も、そうした金利競争に巻き込まれないようにするためには、どうしたらいいかというところからスタートしています。
われわれは、手間もかかり、時間もかかるが、金利だけでなく、取引先の企業に必要な情報を、しっかり提供することを重視しています。そうした情報の提供に基づいて、取引先の様々な疑問や需要を掘り起こし、さらに答えを示していくことを意識しています。われわれがわからないとか出来ない場合は、社会保険労務士や中小企業診断士などの専門家につないで、顧客企業の疑問を解いていきます。こうした取り組みによって、取引先から「『けんしん』は、金利よりも、いい情報を提供してくれるし、親身になって対応してくれるから取引をしようか」と考えてもらうようにすることが、われわれの基本的なスタイルです。
――それがSDGs取り組みにつながるわけですか。
橋爪氏 : そうです。取引先が抱える課題の中にSDGsの取り組みがあるわけです。兵庫県は都道府県の中でも、SDGsの普及に力を入れており、県としての認証事業を積極的にやっています。実は、われわれは県よりも前の2022年に、企業にとってSDGsへの取り組みは避けられない、と判断して、独自で企業のSDGs取り組みを評価する「SDGs診断ツール」を導入し、企業への提供活動を始めていました。
企業にとってSDGsへの対応が避けられなる課題だ、と考えたのには二つの理由がありました。一つは、社会的な要請もありますが、大企業や中堅企業が、脱炭素やSDGsの取り組みをしている以上、その下請け、孫請けに相当する、われわれの取引先が、そうした取り組みをしっかりと理解していないと、サプライチェーンから外されてしまう、という理由です。われわれの取引先企業は、ほとんどが他の企業の下請け、孫請けです。ですので、SDGs対応ができていないと、仕事がなくなるということを意識しないとダメですよ、ということです。これは避けて通れない時代の流れですので。

もう一つは人材の確保です。人手不足の世の中で、今の学生は、ほとんどすべてが大学や高校でSDGsを学んでいます。ですから、自分が就職する企業を選ぶ時に、SDGsに取り組んでいる企業と取り組んでいない企業を見る目を、ある程度持っています。取り組んでいない企業は若者たちの就職先の対象から外れてしまう可能性が高くなる。だからこの2点からSDGsへの対応は絶対必要ですよと、取引先企業に説明しますと、企業の理解力は高まります。
――兵庫県信組が採用しているSDGs診断ツールはどういったものですか。
橋爪氏 : 40のチェック項目に答えてもらいます。ただ、県が実施している診断よりは答え易いものにしています。県の診断ツールは、最終的に認証、登録する仕組みで、補助金等にもつながるので、ハードルは高い。しかし、われわれのツールは、割と入り易い。項目に答える際にも、われわれが横について操作の仕方等も教えながら記入してもらいます。診断ツールでは、回答結果が評価されるとともに、回答企業のSDGsに対する「強み・弱み」が把握できます。さらに回答に基づいて当該企業の「SDGs宣言」が作成されます。診断は、SDGsへの意識を持ってもらう「入口」に当たるものですので、スコアが低くてもダメということではありません。
昨年12月末時点で、363社が診断ツールを利用していただき、そのうち223社が「SDGs宣言」をしています。チェック項目は、SDGsの基本的な取り組みの説明などに加えて、企業が取り組んでいる、あるいは取り組みたいといった紹介事例も聞くようにしています。たとえば、ペーパレス化に取り組むとか、清掃活動に取り組むとか、節電をしようとか、そういう身近な活動から入ってもらうようになっています。作成した「宣言」は企業内で公開してもらったり、企業のホームページに掲載してもらったりすることで、企業の意識を改革することに主眼を置いています。もっとハードルの高い兵庫県の「診断」が欲しいという企業には、県の登録制度へ申請するよう案内します。
全国で25の府県が同類のSDGs宣言事業を行っていますが、兵庫県の認証企業数は直近で235社で、件数ではダントツで全国トップです。そのうちの約21%に相当する51社がわれわれの信用組合の取引先企業なのです。「SDGsの入口」の部分から丁寧な説明を、地道に重ねてきた周知活動の成果だと思っています。
――そうした取り組みの結果として、診断を受けた企業はSDGsとつながる新しい事業分野を開拓したり、そのための設備投資をしたりといった実務面につながる効果はどうですか。
橋爪氏 : 診断を受けて「宣言」をした企業や、SDGsへの積極的な取り組みを行っている事業者向けに「けんしんSDGsサポートローン」の取り扱いを行っています。これはSDGs関連事業等の設備資金等を提供するもので、昨年の12月末で100件21億4700万円となっています。従来の企業向けの融資に追加する形です。
――企業のほうも、診断ツール等を使う過程を通じて、SDGsへの取り組みに手応えを感じたのですね。自分の会社にとってのSDGに関連する重要なポイントを見定めるほか、それにサプライチェーンでの位置付け、人材確保等の面で手応えが得られる企業が確実に増えてきたということですね。
橋爪氏 : 企業にとって、手応えは確実にあると思います。周りが自治体も含めて、SDGsのどういう取り組みをされていますか、といった話が自然に出てくるというか、話の前提になっている感じもします。また兵庫県がいろんな形でSDGsに力を入れているので、それもあって企業もスムーズに取り組みに入っていけると思います。兵庫県の取り組みでは、認証企業に登録されると、特典として、借り入れに際する保証協会の保証料が安くなったり、SDGs認証企業として、名前を公表してもらうこともできます。商談会にも優先して参加できるなどのメリットがあります。

われわれの信組の顧客は、平均すると従業員10人ぐらい。少ないところは5人以下の零細企業も多いです。これらの企業は、SDGsの情報に関心があっても、それをどういう風に自分の企業で活用していいのかがわからない。それをわれわれがその企業に合った提案をすることで、非常にためになったと喜んでいただいています。これはわれわれの経営上の戦術の一つです。中期経営計画でも、われわれの戦略として、地域との関わりを強化するとしており、その中で、SDGsの取り組みを戦術として取り組んでいくと明記しています。
企業に対するSDGs支援の取り組みは、行動宣言を作成することへの支援だけではなく、SDGs以外の補助金の申請の支援や、企業内の働き方改革、他の取引先とのビジネスマッチングなども手掛けています。そうしたサービスを取引先に提供するため、50以上の専門家や専門企業等と連携しており、われわれで提供できない専門的知識やサービスについては、連携先と協力して提供しています。その連携の軸になるのが、われわれの一番の特徴です。
――SDGsには17の目標が設定されています。取引先企業の関心が集中するのはどの目標ですか。
橋爪氏 : 業種的には製造業が一番多いので、SDGs目標の7番目の「エネルギーをみんなにクリーンに」と、12番目の「作る責任使う責任」を選ぶ企業が多いです。自社にとってのSDGs目標を設定した企業には、われわれが提供する「サポートローン」を積極的に活用していただき、設備の購入や、運転資金に利用してもらうニーズを提供できています。
――ローンを借り入れる企業の資金使途はどういうものが多いですか。製造業なら設備投資が多いでしょうが。
橋爪氏 : たとえばですが、エネルギー関係では、太陽光発電事業をしたいとか、働き方改革で効率化を図るための設備を導入したい、あるいは女性活躍を促進するため就業規則を改正するなどのために運転資金を利用したいとか、多様な使途があります。
――企業もそうですが、従業員の方にもSDGsに取り組むメリットは及んでいますか。
橋爪氏 : 従業員も、学生たちが、できればSDGsに取り組んでいる企業に就職したいと思うのと同じで、従業員も自分の会社が時代の流れに遅れることなく、SDGsに取り組んでいるということは自分たちの励みにもなるようです。
――給料さえ高ければいいということではなく、遣り甲斐、働き甲斐が大事ということですね。
橋爪氏 : われわれは、あちこちで取引を開拓するというやり方はしていません。まずは事業先からの取引を「入口」として始めます。取引先に対して補助金取引が始まるとか、融資取引が始まるとかを踏まえて、企業とわれわれが職域提携に関する覚書を結びます。企業の代表者、家族、従業員のためには、福利厚生のための金融商品として、個人向けの融資や預金などを奨めることを広めていきます。取引先企業もそうですが、その従業員にも取引に応じて、それなりの特典を付与する仕組みを提供しています。
――他の信組のほか、多くの金融機関は、それぞれ事業を通じてSDGsの促進にも力を入れていると思いますが、他の金融機関のSDGs取り組みについても意識されますか。われわれのほうがいいといった感じで。
橋爪氏 : 周知力はうちのほうが、私はあるのではと思っています。個々の中身はまた別として、こういうことが大事ですよということは絶えず、顧客に周知していますので。情報提供という点がうちの取り組みの「カギ」だと思っています。そこのところはよそとは違うかなと思います。2カ月に一回、「サポート通信」を配布して、社会の情報、助成金、補助金とかの情報提供もしています。人件費をあげないといけないでしょ、人件費をあげたら助成金がこれだけ降りるとかの情報を、顧問になってもらっている社労士の先生からの情報を情報を出しているのです。そういう金融機関は他には、ないと思います。

――「けんしん」自体のSDGs取り組みはどうですか。今回やられていること自体が、SDGs取り組みでもありますが、17項目の中で特に力を入れているのはどれでしょうか。
橋爪氏 : SDGs取り組みは多様ですが、われわれが、つい最近取り組んだことは、SDGsの1番目にある「貧困をなくそう」という目標を踏まえて、「フードドライブ活動」に取り組みました。また11番目の「住み続けられる街づくり」の目標でも、県内の地場産業である「播州織」を利用したワイシャツやブラウスを製造企業から調達して、われわれの信組の全職員に支給しました。私が今、着ているワイシャツも播州織です。うちの従業員は約420人いますが、全員に播州織のワイシャツとブラウスを定期的に支給することで地場産業を支えています。
播州織は県内の西脇市の伝統的な地場製品ですが、最近は、需要が減ってきて、製造する事業者も少なくなっています。しかし、同生地を使った製品の質はいいと評判です。われわれも少しでも地場産業の維持に、お役に立てるならと始めています。ワイシャツはわれわれにとって、仕事着ですから。全員に支給させてもらい、かつ、大体、5年ごとに制服は変えていくので、更新需要も生じます。
――播州織の製造企業にとっては、「けんしん」が一つの顧客になったわけですね。
橋爪氏 : そうです。われわれとしても、少しでも地域にお金が回るような取り組みをしています。そうしたことにも取り組んでいかないと、われわれ自身が取引先企業から選んでもらえないということにもなります。大手銀行は効率化を図ってどんどん最高益を出せます。ですが、われわれはそういうわけにはいかないので、顧客のために、時間はかかりますが、しっかりと事業と社会への「お手伝い」をすることが基本です。
石破首相が「地方創生」を掲げておられます。首相も、そうした取り組みには、地域に根差した金融機関である信用金庫、信用組合の役割が大事だ、と明言されています。メガバンクのような大きな銀行には、メガとしての役割があり、地銀には地銀の役割があるように、信金、信組にも、地域を守る使命があるのです。
(聞き手は 藤井良広)









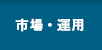




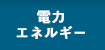







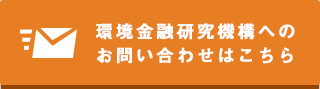










 Research Institute for Environmental Finance
Research Institute for Environmental Finance