第10回(2024年)サステナブルファイナンス大賞インタビュー①最優秀賞(大賞)。太陽光発電サイトの草地化クレジット創出の「ナチュラルキャピタルクレジットコンソーシアム(NCCC)」
2025-01-25 19:20:24

(写真は、右から2人目が馬奈木俊介教授)
第10回(2024年)サステナブルファイナンス大賞の最優秀賞(大賞)は、太陽光発電のメガソーラーサイトを草地化して、CO2吸収源として活用する新たな自主的カーボンクレジット(VCM)創設の仕組みを開発した一般社団法人ナチュラルキャピタルクレジットコンソーシアム(NCCC)に決まりました。日本発の新たなVCMの仕組みは、地球温暖化防止に貢献するとともに、メガソーラーの土壌侵食の防止、生物多様性保全にも資すると期待されます。同仕組みを開発・推進するNCCC理事長で九州大学教授の馬奈木俊介(まなぎ・しゅんすけ)氏に聞きました。
――今回のVCM創出に取り組んだ背景を教えてください。
馬奈木氏 : 私は研究者として国連が提唱する新国富指標開発の取り組みに世界の代表として10年間、取り組んできました。同指標の開発は、地球の自然資本を、人工資本や人的資本と並んで、包括的な指標として経済活動に反映させることを目指した画期的な取り組みです。自然資本が、実際の経済活動で位置づけられ、その価値が数値化されるような社会になってほしいというのが、私の一番の思いです。ただ、インフラの価値や人的資本の価値は比較的広範囲に知られて、企業も使ったりしますが、自然資本は国連や国際的な民間組織や、各国などが使うぐらいで、概念も、計測手法も十分に理解されていません。企業にとっても何の関係があるの、といった感じで言われる。
私はそうじゃない風にしないといけないと思います。それでカーボンを含め、生物多様性の価値なども含めて、こういう自然関連の価値を増やすことが社会にプラスになり、そこに企業の投融資や、場合によって初期段階は公的な資金も入れながら、取り組んでいくことが、地域にも、国際的にも還元されると思っています。そうするために、カーボンクレジットの価値も内包した意味で、自然資本を評価する仕組みを産学官で作って、普及できれば、実際に社会が変わることになると思います。国連だけでやっているのではダメで、学者だけでやっていてもダメです、というのが、そもそものモチベーションで、民間の方々や役所の方々にも入ってもらい、産官学の形で進めています。
――自然資本の価値化ですね。そうした取り組みの中で、太陽光発電施設の敷地を草地化するという発想はどういう経緯で生まれ、そこからクレジットを生みだす取り組みに至ったのですか。

馬奈木氏 : われわれが取り組むカーボンクレジットの創出方法は、太陽光発電施設の未利用スペースを草地化し、その草地が大気中のCO2を吸収し、土壌中に蓄積する土壌有機炭素(Soil Organic Carbon : SOC)を科学的に測定する手法を確立したものです。その測定の信頼性を高めるため、データ収集・分析システムを衛星画像やAI技術等を活用して、データの透明性を確保しつつ、信頼性の高い評価基準を実現できます。
草地化クレジットのポイントの一つは、われわれのメンバー企業の一つである大分県宇佐市の辻田建機が開発した浸食防止効果と緑化を兼ね合わせた「ユニティグリーン」と呼ぶ独自の緑化工法を採用する点です。 太陽光発電のメガソーラーサイト敷地の土地は、土砂の流出や、地域に固有の生物多様性の喪失問題等が指摘されます。同社の工法で草地(芝草を軸)を広げることでCO2の吸収源となるほか、土壌の安定、生物多様性の確保が可能となります。従来のメガソーラーサイトだと、設置した太陽光パネルの下の土は弱くて、台風等による土砂滑りを引き起こしたり、生態系を破壊してしまうような問題がありましたが、そうした問題を防ぐとともに、安定的な吸収源として地域での収入増にもなるのです。
――地域での太陽光発電等への地元の批判も各地で起きていますね。
馬奈木氏 : 2021年7月に熱海で、豪雨により太陽光発電サイトの土砂崩壊で大きな犠牲が出ました。ああいう問題に対応しないと、太陽光発電そのものが批判されたり、そうした発電に取り組んだ地域そのものが批判されたりします。そうした問題に、きちんと対応していこうということが、この技術開発と普及の基本にあります。われわれはサイトでの草地化技術の効果を踏まえたうえで、同技術によってCO2も吸収することを測定・評価することで地域での価値向上にもつながるということを確認し、推進することになりました。メンバー企業が知恵を出し合って、やろうということになったのです。
――そうした取り組みを始めたのはいつころですか。
馬奈木氏 : NCCCを設立したのが1年半前です。
――辻田建機が緑化工法を開発した当初の目的は、太陽光発電の地盤の強化や安全性の向上という視点だったわけですね。それにクレジット化を加えたと。

馬奈木氏 : そうですね。岡山県赤磐市に設置した太陽光発電施設で、約49ヘクタールの未利用地を草地化する取り組みを実施しました。同パイロット的取り組みの結果、環境面では、2021年から23年の2年間で最大86㌧(CO2換算)のSOC固定化を達成しました。これを年間ベースで推計すると、年間最大169㌧の固定化が可能という結果になります。草地による土壌侵食の低減、地域の生態系の多様性向上への寄与も確認できました。
技術面では、われわれが独自に開発した土壌中のSOC測定プロトコルによって、吸収量の科学的評価基準を進展させました。また別途設立した大学発のベンチャー企業(株式会社aiESG)との協業によって、AIを活用したESG評価システムを活用し、対象プロジェクトの透明性と信頼性を向上させることができました。また衛星画像を使ったモニタリングによって、CO2吸収の進捗状況などを効率的、正確に把握できるようになっています。
さらに、社会的にも、地域コミュニティとの協働体制を確立することで、地元のサステナブルな発展に寄与する効果も明確になりました。
――自然資本を使った吸収源はこれまでも熱帯林などでのREDD事業などがありますね。アイデアとしてはいいのですが、実際の吸収量の測定が大変という課題がありました。辻田建機の工法で草地による吸収量を確保できるのは、すごいと思いますが、草地による吸収量は森林に比べると少ないように思えます。
馬奈木氏 : 確かに森林の吸収力よりは、少ないです。その一方で、メガソーラーの建設場所は広く、地域での合意形成が、普通の森林に比べると簡単にできるメリットもあります。対象となる土地の所有権が太陽光パネルを保有する人、または土地を保有する人に限定されるので、公的機関との合意もそれほどいらない。岡山での事例では、対象地域での発電量は約1万3000世帯分の電力量を出せるくらい広い場所です。そうすると、草地でのクレジット化だけですごい環境ビジネスになるわけではないのですが、年間770万㌧分のカーボンクレジットを創出できるので、クレジット事業としても十分にやれると思いました。
――馬奈木先生は、それまで吸収源分野の研究をしておられたのですか。

馬奈木氏 : 森林のほうをやっていました。海外での学術論文も出しました。衛星画像から森林によるCO2吸収量を推計する手法を日本全国でやったりもしました。今回の土壌中のSOCの測定は、土壌でCO2を測定する器具などを複数活用して実用化を進めました。そういう意味では、土壌中SOCの測定手法の確立は、われわれが初めてやったといえます。
――吸収源クレジット市場では、数年前からREDDプロジェクトの価格が暴落しました。最大の課題は、どれだけ吸収したかという測定法に問題があったとされます。測定の明確化は、吸収源に限らず重要だと思いますが、草地化の測定の場合、森林に比べてどうですか。
馬奈木氏 : 測定自体は、自然系、ネーチャーベースドである限り、やはり難しいですね。ただ、将来は簡易になるという予想はあります。現状では、土壌中のCO2を計測する器具を入れて測定します。森林プロジェクトの場合は、人間が森林中に入りこんで測ったり、ドローンのような物を使ったりします。そういう意味で、測定の技術はあるのですが、現状は手間がかかるというのが実態です。将来はもっと簡易なものが開発されると思うので、長期的には、測定問題の解決の可能性はみえていると思います。
自然系のVCMが優れている点としては、VCM化することで相対でマーケットが成り立つ点です。他のクレジットに比べて、自然系は、クレジット価格が㌧当たりで5倍になったりもします。以前は、クレジットは、安ければいいだろうという感じで買われていましたが、そうした場合、安いから買ったとか、意味なくインド、アフリカから買ったということになると、ある種の「グリーンウォッシュ」だと、叩かれたりもします。現在は、クレジット化にもストーリーが求められるようになっています。
クレジット価格の暴落や批判が大きかったのはまさにその通りですね。VCMに限らず、国が認めているJクレジット等のようなものでも、数年前までは、実際には吸収量などを、ちゃんと測れていなかったのです。これまでの世界のプロジェクトでも9割が何らかの問題を抱えて、「吸収量はウソだった」といった論文を、最近になって学者が書いたりもしています。そうした論文がメディアで引用され、世界中でニュースになり、クレジットへの批判が高まったというのが、この2~3年の大きな流れです。
問題点は、二つです。本当はちゃんと計測できていなくて、上手くいってない場合、評価をダウングレードして報告するべきだったのが、そこがわかってなかったという点です。もう一つが、バイオマス化を含めて、地域の雇用、人権問題などでの別の人権問題等を起こして、ある種のESG問題が生じた点もありました。正確性と、ESGサプライチェーン対応をしっかりしていなかったという、この二つの問題が解決できていなかったというのが過去の問題です。
――草地化の場合は、その二つの課題はクリアできる仕組みになっているというわけですね。
馬奈木氏 : そうです。データについては衛星画像で把握できる仕組みを作ることで、一つ目の課題を解決しました。二つ目のESGのサプライチェーン問題については、われわれが設立したaiESG社によって対応しています。岡山でのプロジェクトでも、同社がESGサプライチェーンの評価を実際に計測し、問題を起こしていないことを証明する仕組みをとっています。こうした自然系クレジットが過去に直面した難題の二つを、ともに解決できる仕組みを盛り込んだのが今回の取り組みの新しい点でもあります。
――SOCの測定の特徴を教えてください。
馬奈木氏 : 当初は計算機を使い、生育ソフトによって測定しようとしましたが、あまりうまくいきませんでした。それで、農機具メーカーが使うような土壌の測定器の仕組みを使い、ヘクタール当たりどれくらいCO2が蓄積しているかを計算することにしました。草が育つと、その育つ段階でCO2を排出しますが、その後枯れて土の中に入ります。土が土壌中の微生物を含めて呼吸すると、またCO2が外に出ますが、そうでない限りは土中での蓄積が続きます。そうした蓄積する増加分を計算し、それをクレジットに相当するものとして計算します。われわれのプロジェクトでは、蓄積できるカーボンはヘクタール当たり3.4㌧です。
――土壌中のCO2の貯蓄量は永続的ですか。

馬奈木氏 : はい。常時、草が生えている地域はいいのですが、草が一年後に全部枯れてしまうものはダメです。そうした草地の管理を継続的にする必要があります。パイロット事業では、対象草地の8年分をまとめてクレジット化としました。草地が枯れたらもう一度植え替えないといけない。
――ゴルフ場のようなグリーンが維持されると、吸収力も維持されるということですか。
馬奈木氏 : そうです。辻田建機は緑化工法について特許をとっていますが、われわれが開発した測定手法は、クレジットの仕組みが普及するようにしたいので、特許化せず、他の企業とも共有化できる仕組みにしています。
――草地クレジットとは別に、森林プロジェクトにも取り組んでおられるのですか。既存の森林クレジット等とは違いがありますか。
馬奈木氏: Jクレジットでも、現在、森林クレジットは認めています。しかし、計測方法のレベルに課題があると思います。Jクレジットは長年知られた、これならできるという簡易手法を国が認めるやり方です。しかし、それだと新技術が入り込めないという課題があります。企業からすれば、コスト面や測定面で有利な新技術を活用することで、ビジネス化へのインセンティブが生まれる。そうではなく、だれでもやれるものでないと手法が認められないとすると、収益も十分生まれない。われわれが今、森林でやり始めているのは、ドローンよりも遠くに飛び、かつ細かく測定できる機器を使い、森林のCO2吸収量をより厳密、かつ広範囲で測れる仕組みを作ろうとしています。
――草地化クレジットの手法をJクレジット化する考えはありますか
馬奈木氏 : 例えば、大手の銀行や企業の場合は、売買に際して、国が認めたというのが大事なので、われわれも、将来は、国から認めてもらってJクレジット化したい。もう一つは、海外の機関投資家にすれば日本でしか認められないJクレジットはどうでもいい。われわれとしては今回の岡山案件を海外向けの学術論文で紹介して、海外の認証機関に認められ、海外の投資家に活用してもらえればいい。今後は、両方の方法がやれるようにしたいと思っています。
――VCMへの需要も、日本国内よりも海外の投資家のほうが大きいですよね。
馬奈木氏 : はい。アジアが一番多いと思っています。日本と植生も近いし、そう意味で普及し易いのが東南アジアや南アジアを含め、アジア市場だと思っています。日本の課題としては、森林クレジットも、今回の太陽光サイトの敷地もそうですが、長期的にみると、ほとんどすべての場所で人口減少が起きています。今後、実際に人が住みにくい場所が増えると思います。そこを少人数で、かつ技術で管理ができ、さらに収入がちゃんと入る仕組みを作れれば、その中で農林水産業をやろうとする人たちに、お金が回ることになり、地域の土地を維持することが出来ると思います。
そういう意味での価値の循環は、自然資本ほどできるし、いろんな大企業や地場の企業を含めて、そうした循環に貢献できる仕組みができると、今後の日本社会の持続可能性に合致してくると思います。さらに、自然と人間社会の循環的な課題は、どこの国にもあるので、そうした取り組みにカーボンクレジット、自然資本クレジットが貢献できると思っています。
NCCCは、私が理事長を務めていますが、産業界の方が自分たちの新しい技術を各地域に入り込んで実践し、それを支援する仕組みという意味では、本来は、産業界が中心なのですね。また受け手が土地の場所のある基礎自治体であったりもします。大学や研究者の役割は、どうやってクレジット量を測ったらいいかとか、どういう仕組みならば、新しいクレジットとして認められるか、手続きはどうすべきかなどの部分を支えることにあります。そういう意味での民間主導の取り組みが海外では普及しています。しかし、日本では常に国の方、公的な方向ばかりをみている感じがする。産業界、企業が中心になって進め、それを最終的に国が認めるという、いい形の産学官連携による仕組みを定着させていきたいと思っています。
(聞き手は 藤井良広)









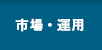




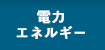







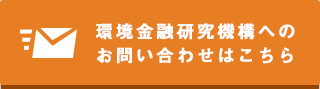










 Research Institute for Environmental Finance
Research Institute for Environmental Finance