日本鉄鋼連盟等が主導して、「マスバランス方式」での「グリーン鋼材」化を国際的基準に盛り込む運動を展開することに、国際的な市民団体や環境NGOら30団体が、公開書簡で懸念表明(RIEF)
2025-06-09 16:45:44

日本鉄鋼連盟等の日本の鉄鋼業界が主導する形で、鉄鋼の脱炭素化を進める「グリーン鋼材」の定義に、「マスバランス方式」を盛り込もうと働きかけていることに対して、国際的な市民団体や環境NGO30団体が、同提案を国際基準に盛り込まないよう求める公開書簡を発表した。同方式では、鉄鋼メーカーが削減プロジェクトで得たCO2削減量を、任意の鉄鋼製品に割り当て、その製品のCO2排出量を低減またはゼロとして扱う考え方だ。これに対して市民団体等は、「同方式は(鉄鋼製品の)買い手の誤解を生み、気候変動への説明責任を弱め、鉄鋼業界での実質的な脱炭素化を推進するための市場インセンティブを損なう恐れがある」と警告している。
市民団体などは作成した公開書簡を、日本政府を含む各国政府、ISO等の基準設定機関、鉄鋼製品の買い手企業等に対して送付した。日本の業界団体などは、同方式を使うことで、実際には石炭を燃料とした鋼材でも、低排出または「グリーン鋼材」等として販売できることを、国際基準として認めることを求める「日本からの提案」を示しており、各国、各基準団体に対して、そうした提案を拒否するよう求めている。
鉄鋼製品の脱炭素化を進める上で、「グリーン鋼材」化が課題となっている。主要な鉄鋼メーカーなどは、鉄鋼製造工程での燃料に、石炭の代わりに水素などを投入して「グリーン鋼材」を製造する方式への転換を目指している。だが、日本の鉄鋼メーカー等は、マスバランス方式による製品も、「グリーン鋼材」として国際的に認定されることを目指しているという。
同方式では、ある特性を持つ原料(例えばバイオマス原料)と、そうでない原料(例えば石炭)を混合して鉄鋼を製造する場合、各特性を持つ原料の投入量に応じて、製品の一部に対してその特性を割り当てる方法をとる。この場合、バイオマス原料が100で石炭が100だとすると、合計200燃料で製造される鉄鋼は全量で「排出量50%削減」だが、同方式では、うちバイオマス原料分の100ついて「排出量100%削減のグリーン鋼材」として販売できる(残りの100は排出削減ゼロのダーティ鋼材)ことになる。
公開書簡によると、この「マスバランス方式」を正当化しようとする提案が、日本国内の鉄鋼メーカーと業界団体により提案されようとしていると指摘。標的となっているのが、科学的根拠に基づく目標イニシアティブ(SBTi)や、国際標準化機構(ISO)、世界鉄鋼協会でのCoC(チェーンオブカストディ)の手法に関する協議等となっているという。
日本では、国内の鉄鋼業界によるロビー活動によって、今年初頭の政府のグリーン購入法基本方針の改定で、日本鉄鋼連盟が定義する「マスバランス方式」による鋼材が優先調達の対象となっている。また自動車分野においても補助金(CEV補助金)等を通じた同「グリーン鋼材」への需要形成が進んでいる、と指摘。
同書簡では、日本の鉄鋼メーカー等の動きは、こうした国内制度での「正当性」の成功によって、さらに国際的にも同方式を拡大しようとして、各基準作成機関や関係国等に働きかけているという。日本政府(経済産業省)もこうした業界の動きを後押ししているとみられる。
書簡は「(鉄鋼メーカーは)政府の支援を追い風に、『排出量の見え方』そのものを国際的に再定義しようとしている。同方式は、企業が生産方法を抜本的に変えることなく気候変動への貢献を主張できる『抜け道』をもたらす。さらには、国際社会が目指す気候目標の信頼性や実効性を根本から揺るがしかねない」と懸念を示している。
グリーン水素を利用した直接還元製鉄(H2-DRI)などの革新的技術は、2020年代後半には商業化される見込みだ。ただ、高コストとなることが課題だ。日本流の「マスバランス方式」は、こうした高コストを負担せず、一部の製品を「グリーン鋼材」として売り出せるメリットがある。しかし、実際の排出量削減効果は極めて限られている。
書簡は、高コストと高リスクを抱えるグリーン水素等の開発普及を進める先行企業にとって、より公平な競争条件を確保するためにも、「グリーン・プレミアム」のように、真の低排出鋼材とグリーンウォッシュによるものとを明確に区別する必要があるとしている。
書簡の署名団体のうち、「スティールウォッチ」エグゼクティブ・ディレクターのキャロライン・アシュレイ(Caroline Ashley)氏は「石炭への依存度が高い鉄鋼メーカーは、自らの影響力を使って炭素の算定方法を都合よく変更することで、抜け道を作ろうとしている。それは自らの脱炭素に向けた変革が遅いためだ。証書上での仮想的な削減を理由に、石炭を主原料とする排出量の多い鋼材を『グリーンスチール』として販売することを許容すれば、気候変動目標を台無しにし、市場の信用を失墜させかねない。ニアゼロエミッションの鋼材は、帳簿上で主張するものではなく、実際に製造されてこそ意味がある」と指摘している。
韓国の気候団体SFOC (Solutions for Our Climate) グリーンスチール担当のヘザー・リー氏は「韓国のPOSCO社による『マスバランス方式』を採用した低排出製品『Greenate』は、グリーンウォッシュという公の批判を受け、環境庁からの指導を受けた。Greenateには実際の排出量を算定するための明確で透明性のある基準が存在しない。鉄鋼メーカーが、石炭を使用する高炉を稼働し続けながら低排出製品を謳い販売することは、その製品の実態と根本的に矛盾しており、容認されてはならない」としている。









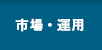




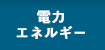







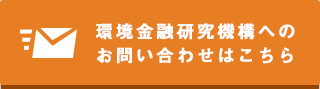










 Research Institute for Environmental Finance
Research Institute for Environmental Finance