|HOME
|【チェルノブイリ報告】 原発30キロ圏内に暮らす「サマショール(帰って来た人たち)」(田中龍作ジャーナル) |
【チェルノブイリ報告】 原発30キロ圏内に暮らす「サマショール(帰って来た人たち)」(田中龍作ジャーナル)
2012-10-23 10:42:00

チェルノブイリ原発から30キロ圏内(10キロ圏内は含まない)の立ち入り禁止ゾーン。事故から26年たった現在も、このエリアに入ることは厳しく制限される。事前登録が必要でパスポートもチェックされる。退出の際は、全身の放射能チェックを行い、高い数値が出た場合は、服を洗濯するケースもある。

74歳のバレンティナさん。「足が悪いので掃除が大変」と苦笑した。=チェルノブイリ、写真:諏訪撮影=
事故直後、放射能の影響で木々が枯れ、「赤い森」が出来た。一度枯れた木々は、ほとんどがもとには戻らなかった。取材車から見える森には、赤い木々を切り倒した後に植えられた若木が、生え揃っていた。
立ち入り禁止ゾーンにはおよそ100人の人々が暮らしている。ウクライナ語でサマショール「自ら帰って来た人たち」と呼ばれる。一般的に知られている「わがままな人たち」という訳は間違いだ、とベテランガイドは説明した。
しかし当時、政府から住居を支給されたにも拘わらず30キロ圏内に戻って来たことに対して、メディアの批判があり、自分の家を持っていない人々の嫉妬を買った。そのような背景から「わがまま」と言われてしまったのかもしれない。
チェルノブイリ原発から西に20キロほどの所、すっかり色づいた広葉樹と針葉樹が入り混じる地帯に廃屋が点在する。そこにバレンティナさん(74歳・女性)の小さな家があった。まるで山小屋のようだ。
薪を燃やした香りが辺りに漂っていた。私たちが自宅に着くと、前掛けをしたバレンティナさんは少し驚いた表情で出迎えてくれた。
「掃除中だったのよ。家が汚いけど、悪く思わないでちょうだい」。通された家の中からは、質素な生活が伺えた。調理は薪を使ったオーブン。小柄な猫2匹は共に目の周りが汚れていた。
辺りは鬱蒼とした森だ。電気は通っているが、夜は漆黒の闇と恐ろしいほどの静寂が包むのだろう。
「どうしてここに戻ってきたのですか?」。
「原発事故が起きた時、すぐにキエフに避難した。でも、キエフは住みにくくて、血圧が200まで上がってしまった。医者から家に帰る事を勧められたんだよ」。バレンティナさんは、わずか一週間の避難生活で、立ち入り禁止ゾーンに戻ってきたという。
実際に、避難した事で病気になったり、亡くなったりした人が多かったことは確かだ。放射能による知識が無かった当時は、汚染地帯から来たという事でひどく差別されることもあったという。
避難先から戻った彼ら「サマショール」は、ほとんどが中高年だった。福島の広い土地で生活していた人々が、避難先の小さいマンション生活で息苦しさを訴えることが多いのと同じだ。
以前、取材でお話を伺った南相馬市から避難しているおじいさんの言葉が思い出される。「コンクリートの箱に閉じ込められている」と東京でのマンション暮らしを表現していた。
土地の物を食べ、隣人とつながり合いながら生きてきた人々にとって、都会の孤立した生活は、拷問とも言えるのだろう。年老いたバレンティナさんが、言外に語っているようでならなかった。
◇ ◇ ◇

筆者らが訪れた日は東京の冬を思わせる寒い日だったが、ヴラジミールさんは半袖だった。=チェルノブイリ、写真:田中撮影=
バレンティナさんの息子のヴラジミールさん(59歳)は、母親の面倒を見るために月の半分以上この立ち入り禁止ゾーンに住んでいる。キエフには支給された家があり、家族もいるが、こちらの生活の方がいいと言う。
「キエフに居てもやる事がない。こちらの暮らしの方がいい。この間、山で大きな鹿を見たよ。夜はフクロウがよく鳴いている。ウクライナの絶滅危惧種のコウノトリもたくさん帰ってきたんだ」。自然の中での生活を、目を輝かせながら話してくれた。
ヴラジミールさんは、リクビダートル(※)の一人だ。原発事故があった時は、溶接工として働いていた。
「体の調子はどうですか?」
「私は元気だよ。でも、仲の良かった友達6人の内、生き残っているのは2人だけ。この2人も心臓の病気がある。私は前向きだし体が丈夫だからね」。
そう言って、おどけてみせるヴラジミールさんだったが、優しい笑顔が何とも寂しそうだった。
サマショールはほとんどの食料を自給している。バレンティナさんの畑でも、じゃがいも、玉ねぎ、キュウリなど何でも作っている。魚は近くの川から、きのこも山から取ってくる。
「放射能の汚染は心配ないのですか?」。
「畑の土は87年に検査した。きのこも魚もどんなものが悪いか分かるようになったから大丈夫」。
30キロ圏内で森への立ち入りは禁止されている。「放射能マーク」の立て札が至る所にある。その森から採れるきのこが汚染されていないとは信じがたい。
ガイドの説明では、30キロ圏内の食品は厳重な管理下にあるとの事だった。十分とは言えない年金で食料をすべて買う事はむずかしい。何よりも、大地の恵みを存分に受けて生きて来た彼らから、その生き方を奪う事は出来ないのだ。
「今の生活はさみしくないですか?」筆者はバレンティナさんに聞いた。
「・・・どうしても家に戻りたかったから。周りに友達もいるし、教会には神父もいるよ。孫も遊びに来るんだ」。
孫のことを嬉しそうに話すバレンティナさんだったが、息子のヴラジミールさんに尋ねると、「子どもは来たがらない」と明かした。
時間に追われながらの一時間程度の訪問だった。取材を嫌がるサマショールもいる中、彼らは突然現れて質問を浴びせる筆者らを温かく迎えてくれた。
「福島第一原発で、また問題があったと聞いたよ。大丈夫なのか」。ヴラジミールさんは、3号機の水漏れのニュースを心配していた。
チェルノブイリ原発事故によって一度は故郷を離れたものの、街に適応できずに居住禁止区域に戻ってきた2人は、同じ境遇に苦しむ福島の人々を深く気にかけていた。
帰り際、車が見えなくなるまで手を振る年老いた母と息子の姿が、今もまぶたに焼き付いて離れない。
http://blogos.com/article/48884/?axis=g:0

事故直後、放射能の影響で木々が枯れ、「赤い森」が出来た。一度枯れた木々は、ほとんどがもとには戻らなかった。取材車から見える森には、赤い木々を切り倒した後に植えられた若木が、生え揃っていた。
立ち入り禁止ゾーンにはおよそ100人の人々が暮らしている。ウクライナ語でサマショール「自ら帰って来た人たち」と呼ばれる。一般的に知られている「わがままな人たち」という訳は間違いだ、とベテランガイドは説明した。
しかし当時、政府から住居を支給されたにも拘わらず30キロ圏内に戻って来たことに対して、メディアの批判があり、自分の家を持っていない人々の嫉妬を買った。そのような背景から「わがまま」と言われてしまったのかもしれない。
チェルノブイリ原発から西に20キロほどの所、すっかり色づいた広葉樹と針葉樹が入り混じる地帯に廃屋が点在する。そこにバレンティナさん(74歳・女性)の小さな家があった。まるで山小屋のようだ。
薪を燃やした香りが辺りに漂っていた。私たちが自宅に着くと、前掛けをしたバレンティナさんは少し驚いた表情で出迎えてくれた。
「掃除中だったのよ。家が汚いけど、悪く思わないでちょうだい」。通された家の中からは、質素な生活が伺えた。調理は薪を使ったオーブン。小柄な猫2匹は共に目の周りが汚れていた。
辺りは鬱蒼とした森だ。電気は通っているが、夜は漆黒の闇と恐ろしいほどの静寂が包むのだろう。
「どうしてここに戻ってきたのですか?」。
「原発事故が起きた時、すぐにキエフに避難した。でも、キエフは住みにくくて、血圧が200まで上がってしまった。医者から家に帰る事を勧められたんだよ」。バレンティナさんは、わずか一週間の避難生活で、立ち入り禁止ゾーンに戻ってきたという。
実際に、避難した事で病気になったり、亡くなったりした人が多かったことは確かだ。放射能による知識が無かった当時は、汚染地帯から来たという事でひどく差別されることもあったという。
避難先から戻った彼ら「サマショール」は、ほとんどが中高年だった。福島の広い土地で生活していた人々が、避難先の小さいマンション生活で息苦しさを訴えることが多いのと同じだ。
以前、取材でお話を伺った南相馬市から避難しているおじいさんの言葉が思い出される。「コンクリートの箱に閉じ込められている」と東京でのマンション暮らしを表現していた。
土地の物を食べ、隣人とつながり合いながら生きてきた人々にとって、都会の孤立した生活は、拷問とも言えるのだろう。年老いたバレンティナさんが、言外に語っているようでならなかった。
◇ ◇ ◇

バレンティナさんの息子のヴラジミールさん(59歳)は、母親の面倒を見るために月の半分以上この立ち入り禁止ゾーンに住んでいる。キエフには支給された家があり、家族もいるが、こちらの生活の方がいいと言う。
「キエフに居てもやる事がない。こちらの暮らしの方がいい。この間、山で大きな鹿を見たよ。夜はフクロウがよく鳴いている。ウクライナの絶滅危惧種のコウノトリもたくさん帰ってきたんだ」。自然の中での生活を、目を輝かせながら話してくれた。
ヴラジミールさんは、リクビダートル(※)の一人だ。原発事故があった時は、溶接工として働いていた。
「体の調子はどうですか?」
「私は元気だよ。でも、仲の良かった友達6人の内、生き残っているのは2人だけ。この2人も心臓の病気がある。私は前向きだし体が丈夫だからね」。
そう言って、おどけてみせるヴラジミールさんだったが、優しい笑顔が何とも寂しそうだった。
サマショールはほとんどの食料を自給している。バレンティナさんの畑でも、じゃがいも、玉ねぎ、キュウリなど何でも作っている。魚は近くの川から、きのこも山から取ってくる。
「放射能の汚染は心配ないのですか?」。
「畑の土は87年に検査した。きのこも魚もどんなものが悪いか分かるようになったから大丈夫」。
30キロ圏内で森への立ち入りは禁止されている。「放射能マーク」の立て札が至る所にある。その森から採れるきのこが汚染されていないとは信じがたい。
ガイドの説明では、30キロ圏内の食品は厳重な管理下にあるとの事だった。十分とは言えない年金で食料をすべて買う事はむずかしい。何よりも、大地の恵みを存分に受けて生きて来た彼らから、その生き方を奪う事は出来ないのだ。
「今の生活はさみしくないですか?」筆者はバレンティナさんに聞いた。
「・・・どうしても家に戻りたかったから。周りに友達もいるし、教会には神父もいるよ。孫も遊びに来るんだ」。
孫のことを嬉しそうに話すバレンティナさんだったが、息子のヴラジミールさんに尋ねると、「子どもは来たがらない」と明かした。
時間に追われながらの一時間程度の訪問だった。取材を嫌がるサマショールもいる中、彼らは突然現れて質問を浴びせる筆者らを温かく迎えてくれた。
「福島第一原発で、また問題があったと聞いたよ。大丈夫なのか」。ヴラジミールさんは、3号機の水漏れのニュースを心配していた。
チェルノブイリ原発事故によって一度は故郷を離れたものの、街に適応できずに居住禁止区域に戻ってきた2人は、同じ境遇に苦しむ福島の人々を深く気にかけていた。
帰り際、車が見えなくなるまで手を振る年老いた母と息子の姿が、今もまぶたに焼き付いて離れない。
http://blogos.com/article/48884/?axis=g:0






















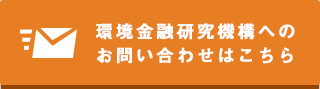










 Research Institute for Environmental Finance
Research Institute for Environmental Finance