「アジアのカーボンマーケット最前線」――日本・中国・香港・シンガポール・インドネシア・マレーシアの動向(白井さゆり)
2025-06-22 21:50:47

アジア各国は、脱炭素と持続可能な経済成長の両立を目指して取り組みを進めている。その中で、国内外の資金を動員しつつ気候変動対策を加速する手段として、カーボンマーケット(炭素市場)が注目を集めている。足元では、自主的炭素市場(VCM)の信頼性を高めるために、国が関与する事例も目立っている。アジア域内でカーボンマーケットを拡大していくためには、ある程度の標準化に向けた協議が不可欠であり、日本の役割も重要になる。本稿では、国際的な議論の現状とアジア地域の最新動向を紹介した上で、日本への示唆を考えたい。
カーボンマーケットの3類型
炭素市場は、大きく次の3類型に整理できる。第一に、各国・地域の公的機関が温室効果ガス(GHG)の排出枠を設定・管理し、企業がそれを取引する「コンプライアンス市場」(規制市場)である。代表例として、EUの排出量取引制度(ETS)が挙げられる。
多くの場合、電力や製造業といった多排出産業を規制対象とし、排出枠を各企業に無償または有償で割り当てる。排出量が枠を超過した企業は、余剰枠を持つ他社から市場で排出枠を購入することなどで義務を履行する。
第二に、パリ協定6条に基づく「国際炭素市場」である。これは、先進国と発展途上国が共同で排出削減プロジェクトを実施し、途上国で創出された削減量(ITMO=国際移転可能な緩和成果)を先進国が取得することで、自国の削減目標達成に充当できる国際協力の枠組みである。日本が推進する「2国間クレジット制度」(JCM)はこの枠組みの一例である。この制度には、各国が2国間で比較的自由にクレジットを発行・移転できる仕組みに加え、共通ルールの下で国際連合が運営するグローバルマーケットも含まれる。
最後に「自主的炭素市場」である。GHG排出について規制等に基づく義務のない企業や組織が、自主的に排出削減の取り組みを進めるためにカーボンクレジットを売買する市場である。クレジットは民間の標準化団体が認証基準を定め、特定のプロジェクトに基づき発行され、レジストリで記録・管理される。この団体としては、「ヴェラ」(Verra)や「ゴールドスタンダード」(Gold Standard)などの主要な国際基準機関が知られている。
国際的には、インターコンチネンタル取引所(ICE)やシカゴ・マーカンタイル取引所(CME)、シンガポールのエアカーボン取引所(ACX)などが存在感を示す。これらの市場では、特定の排出枠やカーボンクレジットの先物取引が行われている。韓国でも将来的な先物市場の導入に向けた準備を進めており、炭素市場の金融商品化・国際化が進展している。
市場間の相互関係と制度的な接続性
これら三つの市場は、必ずしも独立しているわけではない。例えば、中国、韓国、カリフォルニア州などのETSでは、企業が自社の排出義務の一部を、自主的炭素市場で取引されるカーボンクレジットで代替することが認められている。多くの場合、企業が保有するカーボンクレジット全体のうちの5%程度まで代替できる。
また、国際民間航空機関(ICAO)が運営する「国際航空のためのカーボン・オフセットおよび削減制度」(CORSIA)では、参加する航空会社がICAOの認証を受けた自主的カーボンクレジットを活用し、排出目標の達成に充てることができる。
将来的には、パリ協定6条に基づくITMOについても、コンプライアンス市場やCORSIAにおいて、一定の条件の下で活用できるようになると見込まれている。なお、どの種類のクレジットが活用できるかは制度の運用期間や国際交渉の動向に左右されるため、すべてのITMOが容認されるわけではないことには留意が必要である。
一定規模以上のGHG排出に対して「炭素税」を課す制度を導入している国もある。例えば、シンガポールは2024年、炭素税を1㌧当たり5シンガポール㌦(約560円)から25シンガポール㌦へと大幅に引き上げ、30年までに50〜80シンガポール㌦まで引き上げる方針を示している。この制度では、基準を満たしたカーボンクレジットの購入によって、企業は税額の最大5%を相殺できる。
自主的炭素市場の質の向上が課題に
20年代の初頭以降には、自然由来ベースのクレジットに関して「対象プロジェクトが実際に気候変動の緩和にどれほど貢献しているか」と、算定方法に疑義を呈する学術論文が相次いで発表された。他にも、関連プロジェクトが先住民族の権利を侵害しているとする訴訟も提起されるなど、カーボンクレジットの信頼性に対する懸念が一気に広がった(詳細は、Shirai [2025a])。
また、企業がカーボンクレジットを利用することで「自社およびバリューチェーンを通じたGHG排出削減の本格的な取り組みが後回しにされるのではないか」という疑念も根強い。
そこで、信頼性の高い自主的炭素市場を育成するため、国際組織ICVCMは、カーボンクレジットの発行主体(供給側)を対象とする「コア・カーボン原則」(CCP)を策定している。CCPは情報の透明性、取引および所有権の記録と追跡など10項目から成る。
なかでも特に重視されているのが「追加性」の原則である。これは「カーボンクレジットの販売収益がなければ、そのプロジェクトによる排出削減または除去は実現しなかった」と証明する必要があることを意味する。
ICVCMは2024年から、CCPに準拠したクレジットに対して「CCPラベル」を付与している。ラベルの付与は、2段階の認定プロセスから成る。具体的には、まずクレジットのプログラム全体が「CCP適合」の認定を受け、そのプログラム内の個別カテゴリーが「CCP認証」を受ける必要がある。
すでにVerraやGold Standard等の多くの国際基準機関がCCP適合と認定されており、一部カテゴリーでは認証も取得している。CCP認証を受けたクレジットは、将来的にはより信頼性の高いものとして評価されるだろう。
ICVCMが供給側の原則を示すのに対し、別の国際組織VCMIは、需要側である企業がカーボンクレジットを活用してネットゼロを目指す際の行動基準を定めている。ICVCMとVCMIは互いに連携しながら、自主的炭素市場全体の信頼性を高めるため、明確かつ一貫したガイダンスの提供に取り組んでいる。
炭素市場の発展を目指し改革を進める中国
カーボンクレジットは、気候変動対策プロジェクトへの資金を呼び込む手段としてアジアでも急速に関心を集めている。こうしたなか、近年は各国で自主的炭素市場の育成に向けた動きが活発化している。
まず中国については、自主的炭素市場の信頼を高めるために、中央政府が関与して再稼働させた点が非常に興味深い。
中国では、12年から北京市や上海市を含む全国7省・市でそれぞれ個別の自主的カーボンクレジットの取引(CCER制度)を開始したものの、17年3月以降にプロジェクトの登録およびクレジット発行を停止した。理由として、需給がバランスしなかったことや、取引規模が小さかったことが指摘されている。プロジェクトやクレジットに関する方法論(算定・報告・追跡等)が各省・市で統一されていないため信頼性が低く、需要が増えなかったという「質」の問題もあったとされる。
その後、中央政府がCCER制度の再始動に向けて一連の制度整備を進めた。23年末に新制度の下で初めてのプロジェクト登録がなされ、24年初頭にはクレジットの発行も再開された。中国政府は、このCCERによって、全国レベルのETSで最大5%まで排出量をオフセットできるようにする意向である。
25年には、カーボンクレジットの検証・認証機関の承認リストや、詳細な取引規則が公開された。クレジットは自主的な利用行動に任されているため、自主的炭素市場と見なされている。現時点では、発行体も購入者も中国本土に限定されており、香港の自主的炭素市場とは独立して運用されている。
高品質の炭素市場を目指すアジア
香港取引所(HKEX)は、2022年に自主的カーボンクレジットの取引プラットフォーム「コア・クライメート」(Core Climate)を創設した。コア・クライメートは、世界にオープンな市場を目指している。ヴェラの認証規格に準拠したカーボンクレジットの取引において、香港ドルと人民元の決済を提供する唯一の市場であり、ゴールドスタンダード認証のクレジットも取引されている。ただし取引規模は小さく、中国本土との連携が必要になりそうだ。
シンガポールでは、2021年にグローバルに自主的カーボンクレジットの供給・流通を担うCIX取引所が設立された。23年にはヴェラやゴールドスタンダードなどの認証基準を満たしたクレジットを一括で取引できるようになった。前述のとおり、シンガポール政府は一定条件を満たす国際的なクレジットを活用して炭素税の一部を代替できる制度運用を開始している。また、パリ協定6条に準拠したカーボンクレジットの取引促進に取り組んでいる。
東南アジア諸国連合(ASEAN)の中では、シンガポールに続き、マレーシアが自主的炭素市場の育成に積極的に取り組んでいる。22年には、マレーシア証券取引所が世界初のシャリア(イスラム法)準拠のカーボン取引所BCXを開設した。BCXは、標準化された契約を通じてカーボンクレジットや再生可能エネルギー証書の取引を可能にするプラットフォームである。ヴェラやゴールドスタンダードの認証を受けたクレジットを取り扱っている。24年には、マレーシア初の自然由来カーボンクレジットがサバ州のクアムット熱帯雨林保全プロジェクトから発行され、オークションが実施されている。
インドネシアでは、2023年にインドネシア・カーボン取引所が正式に開設され、ETSの下で取引される排出枠と、自主的カーボンクレジットの両方を取り扱う市場が立ち上がった。国際的な基準の認証を受けた自主的カーボンクレジットや、国際認証で扱っていないカテゴリーについては、政府が主導して独自の方法論を構築し、自主的炭素市場を育成する計画である。
日本のJークレジットの世界的認知度向上への戦略を
日本では、一定以上の排出量がある企業は「地球温暖化対策の推進に関する法律」(温対法)に基づく温室効果ガス排出削減計画の下で、排出削減目標を設定し達成状況を報告する義務がある。この際に、企業がGHG排出削減目標を達成するための手段として、J-クレジットを利用して排出削減の不足分をオフセットできる。
J-クレジット制度は、その基準の設定・発行・監視を政府が主導しており、今後、政府が創設する全国ETSにおいても一定程度、活用を容認する予定である。温対法など義務的な特徴も一部有しており、発行体としての地方自治体の積極的な関与も大きい。従って、自主的炭素市場と見なされるのかは明確ではない。
いずれにせよ、J-クレジット制度は国内の排出削減努力を支える有効なインフラとして、国内では信頼を集めている。一方、日本独自の基準の下で開発・運用されてきたため、「追加性」を始め、CCP等の国際原則に必ずしも準拠していない点が指摘できる。世界では、国際的な原則に合わせた自主的炭素市場を育成しようとする国が多い。国際的にオープンな市場とする観点から、日本政府には国際基準との整合性を高めるための制度改革に向けた議論を主導する役割が期待される。
例えば、CCPとのギャップ分析を行い、日本の仕組みが優れているのであれば国際基準の改善を提案する、あるいは国際基準に歩み寄りを示すことが考えられる。これにより、日本の制度が世界市場で受け入れられる道を開くことができるだろう。
仮にJ-クレジット制度が日本国内でのみ流通する仕組みにとどまれば、国際的に事業を展開する日本企業にとって、他国とのクレジット相互承認やオフセット認識の不一致が障壁となるリスクがある。また、国際的な資金動向や新しい計測・認証技術へのアクセス機会を失う可能性もある。制度の国際的な整合性の確保は、日本企業の競争力確保と、カーボン市場を通じた成長機会の獲得という観点からも喫緊の課題である。
アジアでは各国が独自に制度設計を進めているが、それぞれ異なる認証基準や市場設計を採用すれば、市場の分断化が進み、結果として世界の資金がアジア全体に十分に流入しない事態も懸念される。こうした中で、ASEAN諸国を中心に域内の最低限の標準化に向けた意見交換が始まっている。制度設計が初期段階にある今だからこそ、日本が積極的に関与することで、アジア全体の整合的な市場形成を先導することができる。
筆者は今年2月に、炭素市場についてアジア域内の12の金融当局を対象にアンケート調査を実施し、その結果等をアジア開発銀行研究所の論文として公表している(Shirai 2025b、白井2025a, 2025b)。今年3月には、アジア各国の金融当局間での非公式会合も開催した。
同調査と会合の意見交換からは、比較的多くの金融当局が、企業の情報開示の一環としてカーボンクレジットの特徴・種類(例えば、自然由来なのか技術由来なのかなど)について開示を進めようとしていることが明らかになった。質を高めるための工夫を行う当局も多く、予想以上に炭素市場への理解が高いことが確認されている。日本は制度運営の実績や民間技術の蓄積を生かし、国際整合性のある炭素市場の発展に貢献する責務と機会があるといえよう。
(本記事は、『週刊金融財政事情(2025年6月10日号)』に掲載された筆者の論考「国際的議論の進展とともにアジアでも広がる炭素市場の将来像~日本でも世界標準に準拠したカーボンクレジット制度を検討せよ」を、一部加筆・修正したものを、筆者の了解を得て掲載しました)
参考文献
・白井さゆり、2025年a、 「アジアサステナブルファイナンス。金融規制当局への調査からの最新動向(下) カーボンクレジット市場も動きだす。高まる「質」への意識」 RIEF(環境金融研究機構)ブログ、4月6日掲載 https://rief-jp.org/blog/155882?ctid=33
・白井さゆり、2025年b、 RIEF(環境金融研究機構)NEWS 「アジア各国の7割は、ISSM基準の国内基準化を義務的に取り組むとともに、排出量取引制度にも7割が取り組み。アジア開発銀行研究所が12ヵ国の金融当局対象の総合調査」、私の調査報告書を紹介しています、4月6日掲載 https://rief-jp.org/ct5/155766
・Shirai, Sayuri. 2025a. Survey Findings: Asian Financial Regulators on International Sustainability Standards Board Standards and Voluntary Carbon Credits, Asian Development Bank Institute Policy Brief, No. 2025-7. https://www.adb.org/publications/survey-findings-asian-financial-regulators-on-international-sustainability-standards-board-standards-and-voluntary-carbon-credits
・Shirai. Sayuri. 2025b. The Role of Carbon Markets in Facilitating Carbon Neutrality, Asian Development Bank Institute Policy Brief, No. 2025-6.
・https://www.adb.org/publications/the-role-of-carbon-markets-in-facilitating-carbon-neutrality
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

白井さゆり(しらい さゆり)
慶応義塾大学総合政策学部教授。アジア開発銀行研究所客員研究委員兼サステナブル政策アドバイザー。コロンビア大学経済学博士。元国際通貨基金(IMF)エコノミスト。2011~16年日本銀行政策委員会審議委員として金融政策決定に関与









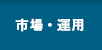




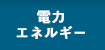







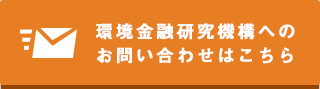










 Research Institute for Environmental Finance
Research Institute for Environmental Finance