|HOME
|10.電力・エネルギー
|明暗! 最悪事故の「福島」と避難所「女川」(現代ビジネス) |
明暗! 最悪事故の「福島」と避難所「女川」(現代ビジネス)
2012-04-06 19:54:25

 最悪の原発事故を起こした東京電力の福島第1原子力発電所と同様に東日本大震災に襲われながら、深刻な事故を招かなかったばかりか、3ヵ月にわたって364人の被災者の避難所の役割を果たした強固な原発がある。宮城県の牡鹿半島にある東北電力の女川原子力発電所だ。(町田徹)
最悪の原発事故を起こした東京電力の福島第1原子力発電所と同様に東日本大震災に襲われながら、深刻な事故を招かなかったばかりか、3ヵ月にわたって364人の被災者の避難所の役割を果たした強固な原発がある。宮城県の牡鹿半島にある東北電力の女川原子力発電所だ。(町田徹)
現地視察も含めて取材したところ、女川原発が無事だった背景には、過剰と思われた基本設計に安住することなく、事故防止の努力を積み重ねてきた事実があったことや、原発を十把一絡げにして福島第一並みに危険と決め付けることの不条理が浮かび上がってきた。
原発の運転凍結が続く中で、政府はこのところ、強引に、大飯原発(福井県)や伊方原発(愛媛県)の運転を再開しようと躍起だ。
しかし、電力の安定供給というフィルターをかけると、本当に深刻なのは東日本大震災と昨年7月の新潟・福島集中豪雨のダブルパンチを浴びた「被災地・東北」である。現状では、東北が今夏、突発的な大規模停電に襲われない保証はない。そういう停電が起きれば、それは人災だ。
もし、我々が、電力不足という人災を防ぐため、例外かつ緊急的に1つだけ、原発の運転再開を認めざるを得ないとしたら、それは地元の懸念を払しょくできない大飯や伊方ではなく、強固な女川原発にルーツを持つ東北電力の最新型原発である東通原発ではないだろうか。
福島第一が不気味な煙を出して放射性物質を撒き散らしていた1年前、筆者は、にわかには信じ難い情報を耳にした。それは電力各社にも太い人脈を持つ通信技術のプロから寄せられたもので、「同じ原発でも、女川は、福島第一とまったく状況が違ったらしい。非常用電源を失うことなく、安全が守られ、関連施設のボヤ程度で済んだらしい。草創期に安全にうるさい頑固者の技術者が強硬に主張して、高いコストを払って約15mもある高台に建設しておいたのが効を奏したようだ」という内容だった。それ以来、筆者は、なんとかして、その情報の真偽を確かめたいと思い周辺取材を続けてきた。そして、信頼できる取材先の紹介で東北電力の東京支社と交渉し、ついに先週、女川原発の見学と取材の機会を得た。
そびえ立つ城壁
3月29日朝、東京の自宅から始発電車で出発。昼過ぎに、ようやく東北電力の女川原子力発電所に辿り着いた筆者の目に最初に飛び込んできたのは、威容を誇る巨大堤防の上を大型ダンプカーが行き交う突貫工事の風景だった。
枯れた雑草が張り付いた以前からの堤防の上に、セメントを混ぜた白っぽい土砂が新たにぎっしりと積み上げられ、上部と下部では色が違う。くっきりとツートンカラーを織りなす堤防が完成しつつあった。
数10分後の女川原発幹部に対する取材でわかったことだが、東北電力は、ただでさえ巨大な堤防をさらに3.5mかさ上げして17mの高さにする補強工事を急いでいたのだ。
女川原発は、マグニチュード9.0とわが国観測史上で最大規模を記録した東日本大震災の震源地(牡鹿半島の東南東沖130km)から距離的に最も近い場所にある原発だ。
目の前の巨大堤防は、福島第1原発に襲いかかったのとほぼ同じ高さ13mの津波が襲いかかったにもかかわらず、ビクともせず、女川原発という砦を守り抜いた城壁である。
あの大震災の日の夕方から夜にかけて、この城壁が守ったのは、原子炉などの原発施設だけではない。東北電力によると、避難してきた周辺の住民を、何度も押し寄せた津波から救ったのも、この防潮堤だった。
最初の巨大津波の襲来から30分あまり経過した3月11日の午後4時過ぎ。原発に隣接する一般見学者向けPRセンターを、原発南側に位置する鮫浦地区の区長ら数人が訪ねていた。「『避難所にしていた建物まで含めて、すべてが流されたので助けてほしい』と訴えられた」のだという。周辺で土木工事に従事していた作業員らも加わり、その日のうちに避難者は40人に達した。
ずぶ濡れの人もいたが、PRセンターは停電で暖房が使えなかったため、女川原発所長の判断で、原発サイト内の事務棟(旧館)や体育館での受け入れを決めて、バスを出して避難者に移動して貰った。ニューヨークやワシントンを襲った911の同時多発テロ以来、警備強化の一環で、外部からの見学を厳しく制限しているポリシーの例外扱いとしたのだ。
道路が寸断されて、女川原発は陸の孤島になっていたが、専用の通信回線が威力を発揮。早くも翌12日朝には、仙台市内の本店から水、食糧、毛布など被災者のための物資を満載したヘリコプターが原発に到着した。ヘリは帰路、酸素吸入が必要な高齢者や間近に出産を控えた妊婦を仙台市内に搬送する任務も果たした。
救難活動に熱心だった背景に、東北電力ならではの企業カルチャーがある。社員の95%が地元・東北の出身者で、地元との共存・共栄が染みついているというのだ。日頃は、周辺の集落の飲み屋で、住民と社員が肩を並べて酒を飲むことも珍しくない。親しくなると、社員たちは住民に「原発は頑丈だ」と自慢し、「あなたの家が地震で倒れて困ったら、原発に避難しておいで」と陽気に話すことが多かった。「親、兄弟の多くが東北に住む社員にとって、周辺住民の苦難は他人事ではなかった」(相沢敏也 東北電力広報・地域交流部副部長)という。
危機に備える鋼の精神
その後も女川原発への避難者は増え続けた。3月14日にはピークの364人に達している。そして、女川原発の体育館は、6月6日まで3ヵ月弱にわたって、臨時の避難所の役割を果たしていた。
だが、東北電力は、原発と被災者を守り抜いた、この防波堤を十分と考えられなかった。大震災によって牡鹿半島の地盤が1m沈下した事態を重く見て、3.5mかさ上げすることにしたのだ。冒頭で触れたのが、このかさ上げ工事だったのだ。突貫工事によって、補強は来月中に完成する予定だ。
防潮堤は、ほんの一例だ。
事前のリサーチや今回の現地取材を通じて、東北電力が原発の安全に猛烈な拘りを持っていることが随所で確認できた。
その第一は基本設計である。女川原発の1号機は1984年6月に営業運転を開始した。その16年前の1968年のこと。東北電力は、学識者を交えた社内委員会「海岸施設研究委員会」を設置して、明治三陸津波(1986年)、昭和三陸津波(1933年)の記録や、貞観津波(869年)、慶長津波(1611年)の文献調査に着手した。結果として、当時、想定された津波の高さは3m程度だった。
しかし、東北電力は当時、女川原発の敷地の高さをほぼ5倍の14.8mに設定した。このことを本コラムに先んじて報じたのは、3月7日付の東京新聞だ。同紙は特集記事で「社内では12m程度で十分とする意見もあった。だが、平井(弥之助)氏は譲らず、社内の検討委員会も15mと結論づけた」と記している。
この平井弥之助氏(1902~1986年)は東大を出て、当時の5大電力のひとつ東邦電力に入社した。戦後の電力再編の立役者である松永安左エ門氏の肝煎りで、日本発送電、電源開発、東北電力(常務取締役、副社長を歴任)、電力中央研究所などを渡り歩いた人物だ。東北地方の水力発電所の開発に多大な貢献をしたほか、電力中央研究所の技術研究所長時代に「海岸施設研究委員会」のメンバーに名を連ね、女川原発の敷地を15mにするよう主張したという。
平井氏は、海岸線から7km以上離れた千貫神社(宮城県岩沼市)の側に実家があった関係で、三陸地方の津波の恐ろしさを熟知していた。この千貫神社のすぐそばまで慶長津波が押し寄せたという仙台藩の記録を根拠にして「貞観津波クラスに備える必要がある」と力説したとされる。
当時の平井氏の主張について、東北電力では「いずれも社内の伝承として残っている程度の話であり、文書として記録が残っているわけではない」(前述の相沢副部長)としているが、経営もこうした声に賛同して敷地の高さを海抜14.8mに決定したのは間違いのない事実だ。福島第1原発を襲った津波について、「想定外」というコメントを繰り返した東京電力とは、なんと対照的なことだろうか。
何重ものバックアップ
安全への拘りの第2が、想定や現状の見直しとそれに応じた対策を、何度も積み重ねてきたことだ。
女川原発は、1995年に2号機の営業運転を開始したが、その設置許可申請に向けた調査で、想定する津波の高さをそれまでの3.1mから9.1mに引き上げた。地質調査で貞観地震の実態が浮き彫りになったためで、東北電力は1990年にこの事実を論文にまとめて発表した。
さらに、2002年に3号機の営業運転を開始した後も、土木学会手法による津波評価が13.6mで、当時の女川原発の敷地(14.8m)より低かったことを確認して安堵したという。
その一方で、高さは十分でも、津波の引き波で堤防を削り取られることを防ぐため、9.7mの高さまで格子状にブロックを敷き詰める堤防の補強工事を実施した。今回の津波でも、十分な高さとブロックで補強した構造が威力を発揮、上から海水が浸入する事態も、引き波で堤防を削り取られることも防いだ。十分な高さを持つ各地の堤防や防波堤が引き波によって破壊されたのと対照的なのだ。
繰り返すが、東京電力が様々な論文やデータ、同業の東北電力の対応などをことごとく無視して、福島第一原発の襲来する可能性のある津波の高さを最大5.7mと甘く見積もり、敷地の高さを10mで建設していたのとは基本設計から大きく異なっていた。加えて、常に改良を怠らない真摯さもあった。
東北電力は、原子炉を冷やすための電源の確保にも万全を期していた。
発電所が外部と電気をやりとりする高圧線網は4系統のところが多いそうだが、女川原発は5系統を備えていた。東日本大震災の強い揺れで、このうち4系統がダウンしたものの、最後の1系統は正常に機能し続けた。
一方、外部電源のダウンに備える非常用のディーゼル発電機は、2号機の一部で停止したものがあったものの、2号機の別系統や1、3号機のすべてが正常で、相互に融通できる状態にあったという。何重にもバックアップができていたのだ。
対照的に、福島第一原発では、外部電源がすべて失われたうえ、非常用の発電設備を原子炉建屋と海岸線の間の地下に敷設していたため、こちらまでダウンして原子炉を冷やせす手段を失い、メルトダウンや水素爆発という重大事故に繋がった。大きな違いは、ここにもあった。
「これで十分ということはない」
東北電力は、細部にも様々な対策を施してきた。例えば、女川では、1号機の運転開始時から、原発の制御盤の前面に頑丈な手すりが取り付けてある。激しい揺れに襲われた時に、誤って操作ボタンを押すことを防ぐための工夫だ。
6年前には、様々な配管の補強を1本の棒で支える構造から、逆V字型にパイプを足して3方向から支える仕組みに改めた。このタイプの補強は実に6600ヵ所に及ぶ。
半年かけて、4階建ての古い事務棟の3階までの外壁に鉄骨を貼りつける補強工事を行ったのは、3年前のことだ。建設が決まっていた新しい事務棟の完成を待つだけでは怠慢だと考えたのだ。
安全策の第3は、今回の大震災の教訓を踏まえた対応だ。
女川原発の遠藤淳一所長代理は、技術者らしい朴訥とした口調で「これで十分ということはないんです。今回の震災でも足りないところが見つかりました」と、いくつもの補強に取り組んでいる事実を明らかにした。
その中には、冒頭で紹介した防潮堤だけでなく、新たな非常用の大型ディーゼル発電機3機を発電所の裏山の海抜60m地点に設置するというものもあった。
そのほか、1.防潮堤の外側に設置してあったため、津波で倒壊した重油タンク(建屋などの暖房用の燃料を貯蔵していた)の設置場所の変更、2.ボヤの原因になった1号機の高圧電源盤内の遮断機の設計の変更、3.2号機の地下3階への海水の浸入を許す原因になった潮位計の取り付け箇所のパッキンの補強—といった対策も含まれている。
このうち2の遮断機の設計変更や、3のパッキンの補強は、以前から順番に改修を進めているものだ。他の個所では補強が終わっていて、今回の震災でトラブルを回避できただけに、遠藤所長代理は「対応が遅れたとの反省がある」と話していた。
女川原発での取材を終えて、その帰路で、筆者が改めて考え込んでしまったのは、あの震災で震度5強以上の揺れに襲われた原発が東北・関東の太平洋側に5つ(北から東北電力東通原発、同女川原発、東京電力福島第1原発、同福島第2原発、日本原子力発電東海第2原発)あったが、このうち震災に敗れて人類史上最悪の原発事故を引き起こしたのは、福島第1原発だけだったという現実だ。
今回、訪ねた女川原発は、福島第一原発の120km北方に位置しており、3つの原子炉を持つ。昨年3月11日の14時46分に東日本大震災が発生した時、その46分前に定期点検を終えて起動したばかりだった2号機を含めて、3機そろって瞬時に運転の自動停止機能が働いた。
それから3分後の14時49分に2号機が、いわば第2段階の冷温停止(原子炉内の温度を摂氏100度以下に下げて安定させること)を達成した。続いて1号機が翌日未明の0時58分に、さらに3号機が同じく1時17分に冷温停止を果たしている。
その後は、放射線モニタに異常値が検出されることもなく、放射性物質の閉じ込めの成功が確認された。原発の重大事故予防の3原則(止める、冷やす、閉じ込める)が円滑に成し遂げられた例と言える。
女川原発の北、青森県下北郡に位置する東通原発は震度5強の揺れに襲われたが、海抜13mの高さに立地しているうえ、あの日は定期点検中だったことも重なり、これといった被害は皆無だった。津波もまったく問題にならなかったが、東北電力は今後3年程度かけて13mの敷地のうえに、2メートルの高さを持つ防潮堤を建設する方針だ。
野田首相の目は節穴か?
東通や女川と比べると、首の皮1枚でなんとか踏みとどまった印象が強いのが、福島第1から南に12kmの地点にある福島第2原発と茨城県にある日本原子力発電の東海第2原発だ。福島第2では4つの原子炉のすべてが冷温停止に達するのに、また東海第2も原子炉を冷温停止にするのにそれぞれ3日以上の時間を必要とした。女川が3つの原発を冷温停止にするのに半日もかからなかったのと比べると、その悪戦苦闘ぶりは否定できない。
ただ、福島第1原発の事故以来、新聞やテレビでは、どの原発でも事態が深刻だったという報道が続いている。しかし、冷静に見ていくと、福島第一以外の4つの原発は、収束までのプロセスにかなりの差はあるものの、結果としてそろって重大事故を起こさなかった。
執念のように安全を追及する女川原発の現場を目の当たりにして、原発と言えば、すべてが凶器であるかのように報じることが、いかにバランスを欠いているか痛感したのだ。 そして、問題なのが、大飯や伊方といった西日本の原発の再開に拘る野田佳彦内閣の姿勢だ。こうした対応は国民感情を逆撫でするだけで、何のメリットもないだろう。
国内の商業用の原子炉には冷却水の使い方によって2つのタイプがあるが、政府は昨年来、大事故を起こした東電が採用している沸騰水型(BWR)の原子炉ではないタイプ、つまり、関西、四国、九州、北海道の各電力会社が採用している加圧水型(PWR)の運転再開に躍起になってきた。ちなみに、やらせ事件で運転再開が暗礁に乗り上げた九州電力の玄海原発もPWR型である。
あまり論理的な主張とは思えないが、福島第1原発事故の直後から、PWR型を採っている一部の電力会社が「福島とは原子炉の型が違うから安全だ」とキャンペーンを張っており、野田政権がその尻馬に乗った格好なのである。
しかし、このコラムで縷々述べてきたように、原発の安全性で大事なのは、徹底的にそれを追求する誠実さがあるかどうかである。そのことは、女川と福島第一のあまりにも大きな差を見てもおわかりいただけると思う。
多くの国民は、福島原発事故を機に、これまでのような闇雲に原発への依存度を拡大するエネルギー戦略と決別したいと考えているはずだ。
だとすれば野田政権はこの肝心の視点を欠いていると言わざるを得ない。
というのも、東北電力は、東日本大震災前には平均で1430万kw程度の電気を供給していたが、太平洋側の主力火力発電所や原発が震災の直撃を受けて800万kw強相当を失ったからだ。加えて、昨年7月下旬の新潟・福島集中豪雨の直撃を受けて、主力の水力発電所もダウンし、100万kw相当の供給力も喪失した。要するに、一時は、3分の1しか供給できなくなった、深刻な被災地なのだ。
もちろん、東北電力は、全力で被災した電源の復旧、緊急電源の新設、老朽化した設備の再稼働などに取り組んでいる。
それでも、昨年夏の電力需要のピーク時には8月8日のように供給余力が2%を割り込み、他社から追加融通を受けるほどのひっ迫した状況に陥った。事態は改善されておらず、今冬のピークでも、2月2日のように5.3%を割り込み、やはり他社から電力融通を受けざるを得ない状況が続いた。
復興のために科学的な視点で
この夏に向けて、リスクはさらに大きくなりかねない。経済が復興すれば、昨年夏、今年冬とは比べ物にならない電力需要が出てくるからだ。
東北電力は「精査中です」と慎重姿勢を崩さないが、依然として東通、女川の2原発が運転を休止しているうえ、火力発電で主力の原町発電所(福島県南相馬市)の復旧も困難で、今夏も綱渡りは避けられない。製造業の本格的な生産再開や流通業の営業本格化といった復興の足を引っ張ることにもなりかねない。
もし、政府が真剣に被災地の復興を考えるのならば、すでに昨年暮れにBWR型として初めてのストレステストの第1次評価書の提出を終えている東通を店晒しにすることを即刻やめるべきである。
政府が現在の方針に拘り、地元の強硬な抵抗が根強い大飯や伊方の再開を優先しようとすれば、西日本を中心に、原発への国民の不信感が増幅されて、東通の再開論議が宙に浮きかねない。幸い、東通の地元、青森県や下北郡の基礎自治体に、東通原発へのアレルギーはほとんどない。対岸の函館に丁寧な説明を行い、理解を得ることは、大飯や伊方の再開強行より遥かに現実的なはずである。
繰り返すが、東通は明らかに復興のために必要だ。しかも、営業運転の開始が2005年7月と、東北電力の原発の中では最新鋭。東日本大震災に堪えた女川原発に技術的なルーツに持ち、「女川のノウハウをすべて注ぎ込んである」と東北電力が胸を張る東通こそ、最優先で緊急の運転再開を認めるべき原発のはずである。
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/32200






















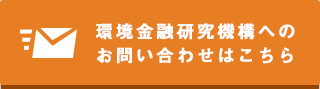










 Research Institute for Environmental Finance
Research Institute for Environmental Finance