財務省は14日、初のトランジション国債となる「クライメート・トランジション利付(CTB)国債」の入札を実施した。入札結果は、最高落札利回り0.74%と事前の市場予想(0.7%)を上回った。注目されていたESG債の利回りが通常債よりもプレミアムがつく「グリーーアム(ESG債のプレミアム)」は1bp(0.01%)。事前予想では1~2bpから6pbの強気予想まであったが、投資家はCTBが抱える「移行リスク」を極めて冷静に受け止めたといえる。
(CTBの「グリーニアム」については、当初14日午前中の入札時に「0.05bp=0.005%」と報道されたが、その後、0.01bp=0.01%に修正されたことから、本記事も2024年2月23日時点で更新しました)
CTBは、岸田政権が推進するグリーン・トランスフォーメーション(GX)戦略の軸となる新型国債。初回の今年度の発行額は27日の発行分を含めて1兆6000億円。今後、2030年までに、毎年2兆円規模で合計20兆円を発行する予定だ。https://rief-jp.org/ct4/142731
財務省が今回入札したCTBは期間10年債。入札前の需要動向を反映する発行日前(WI)取引では13日に0.655%付近で推移していたが、14日午前の相場下落で需要が減退した格好になった。金融機関の応札は2兆3212億円だった。予想よりも需要が減退した背景では、日銀の金利引き上げ観測が再び高まったことも影響したとの見方もある。投資家需要の強弱を反映する応札倍率は2.9倍で、通常の10年債の直近入札(3.65倍)を下回った。
再エネ事業や省エネ事業等を資金使途先とするグリーン国債の発行は欧州諸国を中心に広がっている。だが、温室効果ガス(GHG)多排出産業や、削減困難産業の脱炭素化を支援するためのトランジションボンド(移行債)での国債発行は、今回が世界でも初めて。このため日本政府は「世界初」と内外の投資家にアピールした。
しかし、民間企業のトランジションボンド発行も、日本政府の奨励で一部の日本企業が取り組んでいる程度で、グローバル市場ではほとんど発行されていないのが実態だ。トランジションボンドに対する投資家の需要が低い最大の理由は、将来の「移行リスク」が高い点だ。GHG多排出産業や、削減困難産業の脱炭素化に活用が期待されるCCUS等については技術リスクが大きいほか、政府の支援策自体が途中で変わる政策リスク等の不確定要素を抱えている。
このため、財務省は、特に欧州の投資家等から「石炭使用の延命策では」との疑問の声が多い「アンモニア混焼石炭火力発電」については、GX政策の支援対象に含めているものの、今回の資金使途先とはしない措置をとった。また、1月後半から2月初めにかけて、欧米4カ国で機関投資家等に直接、投資を「勧誘」する海外「ロードショー」も開催した。
メディアの報道では、同ロードショーでは約40社の投資家と会合を持ち、CTBの資金使途等について説明したという。理財局の担当者の「日本のトランジション戦略への関心は予想以上に高いと感じた」とのコメントが紹介されている。
ESG債発行に対しては、これまで通常の投資リターンに加えて、ESG投資を重視する欧米の機関投資家等が積極的にESG評価を加味して投資する「グリーンプレミアム(グリーニアム)」がつくケースが多い。特にグリーン国債等に対しては投資家は積極的に政府のグリーン投資に期待することから、かなりのグレニアムがつくこともある。このため「世界初」と銘打ったトランジション国債についても、市場の事前のグレニアム予想では1~2bpから最大6bpとの見立てもあった(Reuters報道)。だが実際は最終的に1bpにとどまり、通常の国債よりも「人気薄」となった。
投資家の反応が予想以上に慎重だった背景には、いくつかの要因が考えられる。一つは、懸念されていた「アンモニア混焼石炭火力」を資金使途先から除外したものの、GX戦略の基本方針から除外したわけではなく、今後、対象に加えられるのはほぼ間違いないとの見方から、「除外」ではなく「アンモニア混焼『隠し』」ではないか、との疑念を生んだ可能性だ。
また今回の資金使途先には、鉄鋼大手3社が取り組む「クリーンスチール:製鉄工程の水素活用」に2564億円を配分するとしている。だが、同技術自体、コスト面を含めて実現リスクを依然、抱えており、電炉転換への選択肢との違いが不透明という「移行リスク」に投資家が疑問を持った可能性もある。財務省が証券会社等を通じて大手運用会社等に「オールジャパンの投資」を働きかけたとされる点でも、多くの投資家が「役所に『踊らされる』時代ではない。『お付き合い程度』にとどめる」と冷静な評価をした面もあるようだ。









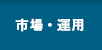




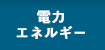








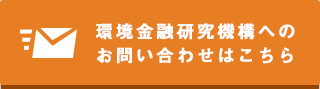










 Research Institute for Environmental Finance
Research Institute for Environmental Finance