2018年(第4回)サステナブルファイナンス大賞受賞企業インタビュー⑦グリーンボンド賞に三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)年3回発行で発行額も最大(RIEF)
2019-03-05 21:52:35
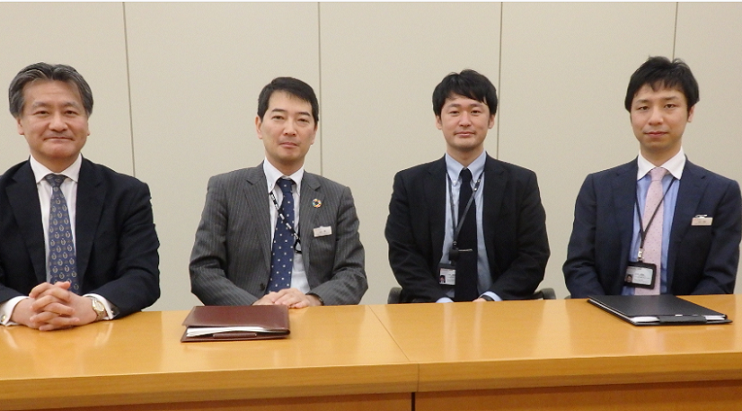
三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)は、2018年を通じて、3回にわたってグリーンボンドを発行、合計の発行額も国内発行体として同年最大の規模で、日本の機関・企業発行のグリーンボンド市場の拡大と流動性の供給に貢献しました。同グループとしては、3年連続の入賞ということになりました。MUFG執行役員で財務企画部CFO室長の山本慎二郎氏らにお話を聞きました。
(写真は、左から山崎周、山本慎二郎、小林亮祐、山田潤世の各氏)
――2018年は年間3度のグリーンボンド発行ということで、日本市場あるいは日本銘柄のグリーンボンド市場の拡大、流動性供給に貢献されました。発行体としては資金需要を踏まえての発行ということだと思いますが、それぞれを振り返っていただけますか。
山本氏:2018年1月に発行したのはTLAC適格グリーンボンドでした。国際的な大手金融機関に課す新たな健全性基準「総損失吸収力(TLAC)」に対応する規制資本調達で、2016年9月の第1回ドル建てTLAC適格グリーンボンドに続いて、2回目です。今回はユーロ建てで5億ユーロ。TLAC規制はいよいよ、3月末に正式導入されます。同規制は金融機関が保有するリスクアセットに対して2019年3月末以降は16%を確保することが求められ、さらに2022年3月末以降は18%に引き上げられます。
したがって、われわれはこれに向けてしっかり準備をしてTLAC比率を高めていかねばなりません。われわれは定期的に市場でTLAC適格の社債発行を続けていくことで、規制水準を十分にクリアしていきたいと考えています。その中で、発行代わり金が三菱UFJ銀行に対する融資を通じて適格グリーンプロジェクトに充当されるグリーンボンドを盛り込んでいく考えです。

――昨年2回目以降のグリーンボンドもTLAC適格ということですね。グリーンビルディング対応も、3回目の国内外貨建て公募債も、同様ですか。
山本氏:いずれもTLAC適格です。年初からの計画に沿って発行していますが、投資家のニーズの多様化や、商品の多様化なども起きるなかで、われわれは安定的な資金調達基盤を確保していく必要性を抱えています。昨年の3回の発行はそれぞれ特色があります。バリューエーション的にはいずれもチャレンジングなものを加えました。その結果、グリーンボンドの商品性を多様化して市場の拡充にも貢献できたと思っています。
1回目のユーロ建てグリーンボンドは、ESG投資やグリーンボンドに強い関心を持つ機関投資家等が多い欧州市場向けでした。欧州の投資家は、ESGに非常に関心の高いプロフェッショナルな投資家が多い。その市場でわれわれとしては初めてユーロ建てグリーンボンドを出しましたので、できるだけ丁寧なIRや商品性を理解してもらうことに務めました。まずはこれを成功裏に収めたことが一つの大きな成果だったと思っています。
――欧州の投資家の手応えはどうでしたか。
山本氏:基本的にプロフェッショナルで、われわれのスキームについての関心や、細かい突っ込んだ内容の質問などに非常に熱心でした。われわれもそうした厳しい要求に、しっかり対応したことで、商品性などについてのご理解は深まったと思っています。
――TLAC適格のグリーンボンドは欧州にもありますか。

山本氏:TLAC適格の資金調達の中心はドルですが、「グリーン」ということになると欧州市場の活用が広がっています。欧州のG-SIBSの金融機関もTLAC適格のグリーンボンドを出しています。ですから、われわれのTLACグリーンボンドへの理解も進みました。
10月には同年2回目のグリーンボンドとして、資金使途にグリーンビルディング(J-REITが保有するグリーン適格不動産に相応する融資)を追加したものを発行しました。われわれにとってもグリーンビルディング対応のグリーンボンドは初めての商品でした。初のスキームへの投資家の理解が深まると、われわれにとっても発行余力が高まります。なので、ここで実績を作ることで、今後に向けて、これまでの再生可能エネルギー分野へのファイナンスの部分と、新たなグリーンビルディングへの投資資金供給という二つの活用が広がりますので、大きな案件だったと思っています。
――この資金使途にはJ-REIT向けの融資も入ってくるわけですね。グリーンビルディングは、比較的、グリーン性を評価し易いようにも見えます。
山﨑周氏(三菱UFJ銀行 ソリューションプロダクツ部 プロジェクト環境チーム 室長):そこを投資家に理解してもらうため、欧州各都市にIRに行き、いかにわれわれの資金使途先のグリーン性が高いかということを説明して回りました。特にグリーンビルディング認証では日本の不動産を対象にしているので、海外の認証制度であるLEED認証やBREEAM認証のほか、日本のCASBEE不動産認証(建設環境総合性能評価システム)や日本政策投資銀行(DBJ)のグリーンビルディング認証についても丁寧な説明を心がけました。

――資金使途が風力発電などの再エネ関連ではなく、ビルディングであるということで、投資家の反応に違いはありましたか。
山﨑氏:対象アセットとして、グリーンビルディングが適格かどうかという質問はありませんでした。すでに主要な対象アセットとして位置づけられています。もう一つ、投資家の反応が高かったのは、インパクトレポートの中で、CO2の削減効果について再エネ事業だけでなく、グリーンビルディングによる削減効果も入れた点でした。グリーンビルディングの場合は、エネルギー効率が高いことが前提なので、CO2排出量は平均的なビルと比べて少ないことを説明できました。
――欧州でも市場によって反応の違いはありませんか。
小林亮祐(CFO室資本政策グループ調査役):グリーンの本場のパリとドイツでは、確かに「グリーン性」についてかなり突っ込んだ質問等をもらいました。そこでも高評価を頂いたという印象です。スペイン、イタリアも回り、そちらでも数社のグリーン投資家と面談を行いましたが、グリーン投資家のすそ野の広がりという点では、パリ、ドイツに及ばない感じでした。

山本氏:ただ、今回、初めて南欧諸国にもIRを行ったことで、今までコンタクトのなかった新しい投資家を呼び込めたという利点はありました。グリーンボンドに対する関心はそれらの国々でも少しずつ高まっているので、そこでMUFGの活動を説明する機会を得たのはよかったと思っています。今まで米国市場で主に発行してきましたので、欧州市場への浸透を深めていく必要性もあります。同市場ではグリーンは注目度が高いということもあります。
――昨年12月には3本目として、初めて国内での外貨建て公募債を出されました。
山本氏:「サクラ債」とネーミングしました。ドル建てですが、われわれも日本の金融機関として日本市場でのグリーンボンド市場の拡大に貢献したいと思っており、主に日本の機関投資家向けに、外貨建てで発行しました。日本の機関投資家もSDGs投資等への割合を増やすことを表明しているところも増えており、今後さらに拡大していくと思います。特に2018年は国内市場のグリーンボンド発行市場の拡大が顕著に広がってきた実感を持っています。3本目は金額としては1億2000万㌦でそれほど大きくはなかったですが、国内外債としてはそれなりの規模で、投資家需要を喚起できたと思っています。
――円建てでなく外貨建てとしたのは低金利の影響ですか。
山本氏:その部分もあります。ただ、われわれとしての資金調達ニーズとして、外貨の資金を調達したいという点があります。

――国内外債の発行では、欧米の投資家と比べて、日本投資家の違いは感じられましたか。
小林氏:サクラ債のIRで、何社か日本の機関投資家を回りました。確かにESGに関する取り組みへの興味は示されていましたが、具体的にグリーンのどれをどう評価するか、何の指標を分析するかといった具体的な点は、これから真剣に取り組もうという段階だと感じました。
――日本の機関投資家にはそうした評価ができる人がまだ少ないとも言われますね。
小林氏:欧州では、面談の際に通常の運用担当者のほか、ESGを専門に分析する人が同席するケースが多くありました。投資を判断する際、一般的なクレジットリスクの観点からみるファンドマネジャーに加えて、ESGフレームワークが問題ないかを分析して、運用担当者にアドバイスする人もいるわけです。特に、ドイツやフランスの投資家にそうした体制をとっているところが多いように思いました。

――もっとグリーンボンドを発行してくれというような注文は投資家サイドからありますか。
山本氏:基本的に、市場全体では投資家の需要に対して、グリーンボンドの発行が足りていない状況にあります。とは言っても、一つの投資家に対して、発行枠の多くを任せると、グリーン適格性を満たしていても、クレジットに対して投資量が大きくなり過ぎ、それはそれで投資家にとっても問題になります。なかなかそのバランスが難しい。
欧州では機関投資家の中でグリーン専用のファンドを作るところが増えていますが、そのファンドの予算を消化しきれていないところが多発しているという状況のようです。グリーンの投資家だからといって、どんなグリーンボンドでも買うというわけでもありません。やはり信用力の要求水準を満たしたものでないと投資しづらいので、引き続き、発行が需要に追い付かない状況が続くとみています。
――去年のグローバルなグリーンボンド市場での発行額はあまり伸びませんでした。
山本氏:そうですね。発行体の信用力が投資家の目線に合っているかどうか。それに加えて、グリーンの中身を評価したときに買えるものになっているかどうか。ということだと思います。グリーンなら低クレジットでも買うというわけではありません。あくまでもクレジットの基準を満たしたうえで、グリーンへの投資を増やしたいという感じです。
――そういう意味では、やはり欧州の投資家は、日本の投資家より一歩先にいっている感じですね。

山﨑氏:将来には、ESG投資を資産運用額の100%にしようとしているファンドもあります。ファンドの中でのESG投資の比重があがってくるのは間違いないと思いますので、そこに応えられる発行体でないと、グリーンボンドを出しても買ってもらえないことになる可能性もあるかもしれません。
――今年はグリーンボンドの発行見通しは、戦略的にどうなりますか。
山本氏:TLACの発行金額は引き続きコンスタントに出していく見込みです。まだ明確に金額をどうするかは策定中ですが、引き続き安定的な発行になると予測しています。その中で米国市場と欧州市場をしっかり活用していくという戦略的な調達方法についても基本的には変わらないと思います。その際にグリーンもやるという重要度も変わらないと思います。
――日本市場での課題はどう考えていますか。
山田潤世(CFO室資本政策グループ調査役):欧州のあるESGのスペシャリストに、日本の市場について細かく聞かれたことがあります。投資家のグリーン評価が追い付いていない、と説明しましたが、そもそも日本は省エネなどが進んでいるのと、厳しいレポーティングをしなくても、各企業がどういう行動をとっているかということに対して周りの目も厳しくなってきており、たぶんきっかけさえあればグリーン市場は花開いていくと思っています。われわれ自身がグリーンのガイドライン等を出すことによって、それに基づくレポーティングなどは後から付いてくると思っています。

小林氏:新しくグリーンビルディングを資金使途とするグリーンボンドを作る中で、グリーンボンドフレームワークを作り直しました。海外の発行体だとグリーンビルディングは資金使途として一般的で、レポーティング等も形が出来ています。国内でも、これまでもグリーンビルディングは他発行体の資金使途の一つになっていましたが、しっかりとした定量的なレポーティングをするとなると、いろいろと実務的な苦労がありました。どこまで定量的なデータを資金使途のグリーンビルディングから得て、どこまで投資家に受け入れられるように開示できるかということを、主幹事のモルガン・スタンレーや三菱UFJモルガン・スタンレー証券と一緒に模索をしながら、グリーンボンドフレームワークを作りあげました。
通常のグリーンボンドに、「MUFG J-REIT向けESG評価 supported by JCR」というMUFG独自のESG評価制度を新商品として付け加えました。外部認証制度で一定評価を取得したものはすべて対象候補となりますが、その中でMUFGの独自のESG評価制度に照らして、点数の高いものから基本的には資金使途先に充当していきます。ですので、外部認証による評価を得ているだけではなく、さらにその中で、よりグリーンの貢献度の高いものを選んでいく仕組みにしています。
ーー単にグリーンボンド原則(GBP)準拠だけではないと。
小林氏:資金使途対象として選定したJ-REITについては、具体的なJ-REIT名を当社HP上で、毎年のレポーティングのタイミングで開示していくことを想定しています。そうなると、僭越ながら当社HPのレポーティング上で載ることがJ-REITとしてのアピールにつながるようになることを期待しています。今後、当社のESG評価制度で評価を取得したJ-REITが三菱UFJ銀行から借入を行い、グリーンボンドの発行代わり金に充当されるという評判が広がれば、よりグリーンの開示に対する意識も高まり、国内でのグリーンビジネス自体も広がっていくのでは、と期待しています。
(聞き手は 藤井良広)









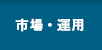




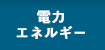







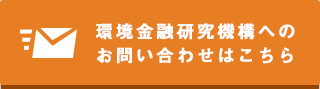










 Research Institute for Environmental Finance
Research Institute for Environmental Finance