|HOME
|福島第1原発、朝日の「吉田調書」報道取り消し後も ナゾ残す東電の「全員撤退」。東電社長の電話で官邸は「撤退」の認識(滝順一編集委員:日経) |
福島第1原発、朝日の「吉田調書」報道取り消し後も ナゾ残す東電の「全員撤退」。東電社長の電話で官邸は「撤退」の認識(滝順一編集委員:日経)
2014-09-29 21:31:59


東京電力・福島第1原子力発電所の事故で現場の事故対応を指揮した吉田昌郎元所長(昨年7月死去)の聴取結果書(吉田調書)が公表された。
事故が起きた2011年の夏から秋にかけて政府の事故調査・検証委員会(畑村洋太郎委員長)の13回に及ぶ聞き取り調査にこたえた。政府は吉田元所長の調書と合わせて、当時首相官邸などで対応にあたった菅直人・元首相ら18人の調書も公開した。事故当時の状況を振り返ってみたい。
■大筋で辻つま合う
一連の調書の内容は、12年7月に公表された政府事故調の最終報告書や、国会の事故調査委員会(黒川清委員長)の内容と大筋で辻つまが合っている。当然のことではあるが、2つの事故調は吉田氏らからの聴取結果を十分に尊重して報告書をまとめたのだと受け取れる。
事故発生から4日目(11年3月15日)朝に「所員の9割にあたる約650人が吉田氏の待機命令に違反し、10キロ南の福島第2原発に撤退していた」とした朝日新聞社の報道(14年5月20日付朝刊)については、すでに同社が誤りを認めている。確かに調書からは「命令違反」があったと読み取れない。
吉田氏は、事故対応に不可欠な人員以外を第1原発敷地内、あるいは近隣の放射線量が比較的低い場所に一時的に遠ざけ待機させるつもりでいた。しかし所員らは第2原発にまで退避した。これは吉田氏にとっては想定とは異なる事態だった。調書のなかで吉田氏は「考えてみれば、2F(第2原発)に行った方がはるかに正しいと思ったわけです」と述べ「命令違反」とは認識していない。
この問題がことさら注目を集めるのは、その前夜(3月14日)から首相官邸で議論になった第1原発からの「全員撤退」問題とからむためだ。「命令違反」とした報道が誤りだったとしても、全員撤退をめぐるナゾは依然として残っている。
経緯を振り返ってみよう。

14日夜、2号機の原子炉の水位が下がり核燃料がむき出しの状態になっているらしいことがわかった。第1原発の現場では注水を試みようとしていたが、炉内の圧力が高すぎて消防車による注水ができず、そのままでは原子炉格納容器が破裂する事態が予測された。
このため東京電力は現場からの退避基準と手順書の作成を始めた。当時の清水正孝・東電社長は寺坂信昭・原子力安全・保安院長や海江田万里・経済産業相、枝野幸男・官房長官らに順次、電話を入れ、「退避」の意向を伝え始めた。吉田氏も細野豪志・首相補佐官(当時)に電話し、厳しい状況を伝えた。
清水氏からの電話を受けた海江田氏や枝野氏は、東電はすべての人員を第1原発から撤退させ事故対応を放棄するつもりであると受け取った。海江田氏らは15日未明、就寝中だった菅氏を起こして報告した。
菅氏は「撤退などあり得ない」と即時に判断、清水氏を首相官邸に呼んで、考えを伝えた。清水氏はこのとき反論などを一切しないで「わかりました」とだけ答えた。午前5時すぎに菅氏らは東電本店に行き、政府と東電の統合対策本部をたちあげた。
■第1原発、退避始まる
第1原発で退避が始まるのは、この後である。15日未明に消防車による注水ができるようになり、現場ではわずかだが愁眉を開いていたのだが、午前6時すぎに2号機で「異音」がしたとの報告が吉田氏のもとに上がった。後にこの音は4号機建屋で起きた水素爆発だったとわかるが、吉田氏らは心配していた2号機格納容器の破壊の可能性を念頭に、必要な人員以外の退避を指示した。
現場には約70人が残ったとされる。海外メディアによって「フクシマ・フィフティーズ(福島の50人)」と名付けられる人々である。
第1原発敷地内の放射線量が懸念されたほど上昇しておらず、2号機の格納容器が爆発していないことがわかると、第2原発に退避した所員らは現場に復帰し始める。
こうした一連の経過の中で、吉田氏は一貫して「全員撤退」は考えの外だったと語り、清水氏も東電のテレビ会議の記録画像で全員撤退を打ち消す姿が残るほか、国会事故調が公開で実施した聴取で「全員撤退」の判断はなかったとしている。
ただふしぎなのは清水氏の電話を受けた官邸の政治家らはそろって清水氏が電話で「全員撤退」の意向を打診してきたと受け取っていることだ。
調書によると、海江田氏は最初に電話で耳にした表現は「撤退」ではなく「退避」だったとする。電話を受けた海江田氏はそばにいた人物に「(所員らが)第2原発に行ったらどうなるのか」と尋ね、「第1原発が5、6号機も含め爆発する」と聞いて、清水氏に(退避は)無理だと答えたとしている。そばにいた人物は保安院付(当時)の安井正也氏と思われる。
「退避」が「撤退」という言葉に変わったのは深夜になって枝野氏や細野氏らと議論を始めてから、とも述べている。言葉の違いはともかく、海江田氏は当初から東電が第1原発の放棄を打診したと受け取っていたとする。
同様に清水氏から電話があった枝野氏も認識は同じだ。深夜に官邸5階の総理応接室に集まった関係者はみな認識を共有していた。
細野氏は、班目春樹・原子力安全委員長(当時)がもう手はないから「撤退やむなし」と話し、東電の武黒一郎フェロー(当時)も「もうだめだ」と話していたと証言している。また海江田氏には経済産業省の松永和夫事務次官(当時)からも撤退の意向が伝えられていたのではないかとの推測も述べている。
この点に関連し、朝日新聞の連載記事(12年1月7日付)は、海江田氏が「(松永次官は)撤退を言いに来ている」とつぶやいていたとする寺田学・首相補佐官(当時)の証言を紹介している。しかし調書では海江田氏はこれを否定、松永氏の来訪は「計画停電かエネルギーか何か、その関係」とオフサイトセンターの撤退に関連してであって、第1原発の撤退とは関係がないとしている。
清水氏は14日夕から深夜にかけて経産相や官房長官、首相補佐官(細野氏は電話に出なかった)に次々と電話している。並行して東電本店は退避基準づくりを始めていることは東電も認める。必要不可欠な人員を残しての退避だったのなら社長自らわざわざ電話する必要があったのだろうか。社長から直接の電話であったことが関係者をして重大事だと受け取らせた可能性はある。
この点について、清水氏は国会事故調のヒアリングで「(現場には自衛隊もおり)一部の人間といいましてもそれなりの人数がサイトから動くということが一つの動きでございますので、これはやはり所管大臣それから保安院長の方にはお伝えしておくという私の判断」であると説明している。
■「全員撤退」は誤解か
「全員撤退」は電話のやり取りから生じた誤解にすぎなかったのか、あるいは東電トップの清水氏の胸中には公式の議論とは別の思いがあったのか。様々な証言から前者とみるのが妥当かもしれない。事実、国会事故調は東電に全員撤退の意思はなかったと認定した。
ただ明確に結論づけるにはどこかすっきりしないものが残る。官邸も東電も混乱し客観的な記録が少ない。公開された調書はごく一部にすぎず、関係者が後から都合の良い話をしている可能性も否定できない。
ひとつ興味深いのは、海江田氏が「よくわからない」との前提条件付きながら「(第1原発から)間違って全員出ようとしたとかいう話もまたあるのですね」と聴取で話している点だ。15日朝の退避が事前の意図と異なる形だったらしいとの情報が早い時点で関係者の耳に入っていたことをうかがわせる。
危険な現場に部下とともに残った吉田氏からすれば、東電の全員撤退を菅氏が止めたとの見方は大いに異議があるところだろう。ただ全員撤退問題をきっかけに政府は東電との統合対策本部を置いた。このときの菅氏の判断が事故対応のやり方を大きく変え、事態を改善に向けたのは間違いがない。15日の朝は間違いなく福島原発事故の転換点だった。
吉田調書には、親分肌で責任感の強い現場指揮官とは異なる吉田氏の一面がうかがえる部分もある。
事故の前に想定を超える津波の可能性が指摘されていたことについて、吉田氏は福島第1だけが津波対策の不備を問われるのに納得がいかない。
津波で1万人以上が亡くなったが、マグニチュード9の地震が起きるとわかっていたのなら、なぜ政府や自治体も真剣に対策を打たなかったのかと問い返し、「論理飛躍して、東京電力のここの話だけにもってくるのはおかしいだろう」と反論する。ここはどうしても言い訳がましく聞こえる。
福島第1原発の設置許可時点に想定していた津波の高さは60年に起きたチリ地震津波の約3メートルだった。その後土木学会による津波評価見直しなどがあり、東日本大震災が起きた時点では6.1メートルを想定し、6号機の非常用海水ポンプのモーターをかさ上げするなどの対策を講じていた。
問題は2002年に政府の地震調査研究推進本部が、福島沖も含む三陸から房総沖の海溝沿いのどこでも地震が発生する可能性があるとの「見解」を公表した後だ。東電は見解を受ける形で福島沖でマグニチュード8を超える大地震が発生した場合の津波高さを試算し15.7メートルという値を得ていた。これに対してはすぐに対策を講じないまま震災を迎えた。
■打てたかもしれない対策
吉田氏はこのとき本店の原子力設備管理部の部長で、福島沖の大地震の津波評価を改めて土木学会に依頼した。
「土木学会がこうおっしゃるんだったら、例えば15メートルと言われれば、至急それに対応した対策を当然するということは、間違いなくそう思っていました」と対策を怠ったり先送りしたりするつもりはなかったことを強調する。何百億円もの多額の追加投資が必要な対策をうつにはそれなりの根拠が必要だったと説明する。
確かに防潮堤のかさ上げなどの大工事ならそうだろう。しかしより小さな投資でも対策は打てていたのではないか。
調書で吉田氏はこんなことも話している。「あれはものすごく大きいトラブルだといまだに思っている」と言う1号機の海水漏れ事故のことだ。
1991年に1号機のタービン建屋内の配管に腐食のため穴があき、海水が漏れた。その結果「冷却系はほとんど死んでしまって、DG(非常用ディーゼル発電機)も水につかって動かなかった」という。
まさに建屋内に水があふれる怖さを思い知らせる事故だった。東電はこの事故の後、空冷の非常用ディーゼルを3台増設したが、肝心の電源盤は地下に置いたままだった。そこまでは3.11前には思いが至っていないのだ。
「溢水(いっすい)というものに対する備えというか、津波というより溢水なんですね。溢水対策というところをどういうふうに考えるかということだと、今になって思います」と吉田氏は語っている。
溢水で電源盤や非常用の電機機器をぬらさない。そうした対策なら防潮堤のかさ上げなどよりずっと安上がりだったろう。柏崎・刈羽原発が被災した07年の中越沖地震以降、かさむ安全対策費をこれ以上増やしたくない、あるいは時期的に柏崎対応の後にずらしたいという心理が当時の東電幹部のひとりとして吉田氏の判断をゆがめてはいなかっただろうか。今となってはかなわないが、本人に尋ねてみたいところだ。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFK24H2B_U4A920C1000000/






















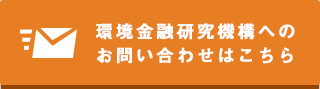










 Research Institute for Environmental Finance
Research Institute for Environmental Finance