トヨタ、出光、ENEOS、三菱重工の4社が、合成燃料(e燃料)の導入・普及で「協働」。「製品ライフサイクル全体での排出削減」をアピール(RIEF)
2024-05-27 17:07:36

(写真は、合成燃料でレース出場も可能)
トヨタ自動車、出光興産、ENEOS、三菱重工業の4社は27日、電気自動車(EV)とは別に、現行のガソリン車などの内燃機関車(ICE)の脱炭素燃料となる合成燃料(e燃料:「カーボンニュートラル(CN)燃料」と命名)の導入・普及に向けて協働すると発表した。合成燃料は水素とCO2を原料として製造することから脱炭素になるほか、現行のガソリン車等の走行を可能にすることで、脱炭素と、自動車製造システムの継続性を保つことができる。EUも2035年以降、EVとともに「e燃料」で走るICE車は認める方針に切り替えている。
4社は共同プレスリリースにおいて、「合成燃料」について、「製品ライフサイクル全体においてCO2排出量を抑えられる。特に液体のCN燃料は、エネルギーを『ためる』『はこぶ』点で優位性があり、輸送可能なエネルギー源として適している」と強調している。
主な協働の対象は2つの分野となる。①日本の自動車市場におけるCN燃料の導入シナリオやロードマップ、市場導入に必要となりうる諸制度について、議論・検討する②日本におけるエネルギーセキュリティ等の観点から、製造の実現可能性を調査する、としている。
4社それぞれの役割では、まず、出光興産は中期経営計画で表明した3つの事業領域の1つとして合成燃料を、多様で地球環境に優しい「一歩先のエネルギー」と位置付けて、その社会実装に向けて、内外の様々な企業と連携しながら、合成燃料やバイオ燃料などのCN燃料の早期導入・普及を目指すとしている。
ENEOSは、グループの長期ビジョンで「エネルギー・素材の安定供給」と「CN社会の実現」との両立への挑戦を掲げている。水素や再生可能エネルギーの活用を推進し、合成燃料などのCN燃料の事業開発を進めるとしている。
トヨタはCNに向け、マルチパスウェイを軸として、EVや燃料電池車(FCV)などの電動車の普及だけではなく、エンジン搭載車両のCO2排出量削減にも取り組んでいると強調。2007年には、ブラジルでフレックス燃料車(バイオ燃料とガソリンの混合燃料で走る自動車)を導入したほか、今後も、保有車を含むエンジン搭載車両のCO2削減に取り組み、合成燃料の普及に貢献するエンジンの開発も検討していくとした。
三菱重工グループは2040年までにCNを達成すると宣言している。そうした目標達成のために、CO2エコシステム、水素エコシステムの構築などに取り組んでいる。こうしたCO2削減関連の製品・技術・サービス、世界中のパートナーとの新しいソリューション・イノベーションによって、CN社会の実現に貢献していくとしている。
合成燃料の開発・普及には、ドイツ車等の欧州の自動車メーカーも力を入れている。現行のエンジン技術を生かせるほか、製造プラントも維持できるメリットがあるためだ。一方で、合成燃料製造の軸となる水素の製造には、水を電気分解する必要がある。その際にCO2排出のない電力として、再エネ電力を活用することになる。そのため、再エネ電力で走行するEVに比べて、合成燃料使用のエンジン車は、水素製造コスト分、高くなるのが最大のネックだ。
合成燃料の価格は水素価格に大きく依存しており、製造コストは1㍑当たり300〜700円とされる。水素の製造コストを下げ、もう一つの原料となるCO2については、火力発電等からの排出CO2を活用することで、どれだけ効率化を高めることができるかが、合成燃料実用化のカギといえる。









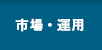




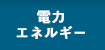







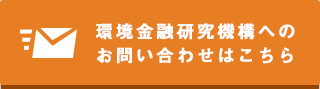










 Research Institute for Environmental Finance
Research Institute for Environmental Finance