天然ガスと原発のタクソノミー参入のEU欧州委案。「トランジション・ファイナンス」の定義を明瞭化。原発は「二重のトランジション」に(藤井良広)
2022-02-08 13:13:58

EUの欧州委員会がサステナブルファイナンスのタクソノミーで、天然ガス火力発電所と原発を対象に加えたことがグローバルに議論を呼んでいる。「原発はサステナブルファイナンスになじむのか」「天然ガス火力発電から排出されるCO2量は妥当か」。一方で、欧州委の決定は、あいまいさの漂う「トランジション(移行)・ファイナンス」についてのクライテリアを明確化したとの見方もできる。
EUはすでにEUの法律としてタクソノミー規則(TR)を制定している。今回の欧州委が決定したタクソノミー案は、補完的委任法(CDA)と呼ばれる。TRに基づいて、対象となるサステナブルファイナンスの経済活動のうち、気候変動関連の事業をリスト化する委任法(DA)はすでに1月から施行されている。気候緩和事業は9部門88事業、同適応事業 は13部門94事業を網羅している。https://rief-jp.org/ct5/122095?ctid=71
これに対し、CDAは同分類の議論において、意見がまとまらなかった天然ガスと原発をDAから分離し、欧州委が別建てでの取りまとめを進めていた。すでにその経緯等については、RIEFの記事で何度も取り上げているので、そちらを参照していただくこととし、2月2日に欧州委が発表したCDAの最終版の評価に絞って論じる。https://rief-jp.org/ct5/121851?ctid=71
https://rief-jp.org/ct5/121830?ctid=71
https://rief-jp.org/ct6/121595?ctid=71
https://rief-jp.org/ct8/121497?ctid=71
EUはこれまで、サステナブルファイナンスのタクソノミーの対象事業として、①企業の経済活動自体が気候変動緩和・同適応等の6分野のどれかに該当する場合(再エネや省エネ等:Own Performance)②環境目標に資する経済活動を支援する事業(風力発電事業の風車プレート等の製造業等:Enabling Activities)③技術的・経済的理由で低炭素の選択肢ではないが、気候ニュートラルへの移行に資する事業等 : Transition Activities)ーーの3分類を示してきた。

これまで、③については一般に「薄いグリーン」と呼ばれてきた。この分野は幅広い産業をカバーしており、例えば炭素集約型産業の一つである鉄鋼業についても、技術スクリーニングクライテリア(TSC)として、①ホットメタル(溶融状態の銑鉄)= 1,331112 tCO2e/t②焼結鉱= 0,163113 tCO2e/t ③コークス(リグナイトコークス以外)= 0,144114 tCO2e/t等が設定されている。
同じく炭素集約型産業のセメントや化学品等も、トランジションの「薄いグリーン」としてTSCを設定している。これらの産業については、①同産業あるいはセクターで最も技術レベルの高い温室効果ガス(GHG)排出量であること②低炭素の代替技術・設備の開発と普及を妨げない③それらの長期稼働によって炭素集約型資産を固定(lock-in)させない、という3つの条件が付されている。
ただ、こうした基準に合致しているからといって、「薄いグリーン」の企業がタクソノミー準拠のグリーンボンドを発行しても、投資家が投資してくれるかどうかは不明だ。実際にも、EUではこうしたトランジションファイナンスは低調だ。投資家にすれば、投資対象の産業・セクターで、さらなる低炭素技術が開発されたり、排出規制が導入されたりすれば、トランジションファイナンスの対象とした使途資産が座礁化(Stranded)するリスクがあるためだ。
今回の欧州委のCDAは、天然ガスと原発を、こうしたタクソノミー対象の③の事業に分類した。天然ガスは化石燃料だが、石炭に比べてCO2排出量が少ないというのがその理由だ。その場合の条件となるTSCとしては、エネルギー全体の基本的排出量の100gCO2e/kWh未満に加えて、2030年末までに建設許可を得た事業については270gCO2e/kWh未満あるいは年間のGHG排出量が20年間で平均550kgCO2e/kWhを超えない、という基準を設定した。
さらに天然ガス火力を既存電力設備と代替する場合は、再エネ事業の代替については認めず、石炭火力あるいは天然ガス・石油火力の代替に限定する。新規天然ガス火力発電による発電量は、既存発電設備より15%以上上回ってはならない(再エネの開発・普及を妨げない)。新規建設設備の稼働全期間のGHG排出量は、少なくとも55%の削減(EUの2030年公約に資する)につながるーー等の追加条件を付した。
つまり、建設が認められる新規の天然ガス火力発電事業は、「2030年55%削減目標」への寄与を基本とし、事業規模にも、排出量増加にも、一定の制限を付している。再エネ事業への転換を阻害しない範囲で、全体的な排出削減に寄与するトランジション(移行)という位置づけを示した形だ。
日本では経産省が「クライメート・トランジション・ファイナンス指針」を公表している。最近では住友化学グループが同指針に基づく天然ガス火力建設のためのトランジションローンを三井住友銀行から借り入れる方針を発表した。だが同社等の公表情報を見る限り、国が目標とする「2030年46%削減目標」への寄与の定量的な評価はなく、CO2排出量基準も明確ではない。EUがトランジションの明確化を進める一方で、日本のあいまいさが際立つ形だ。https://rief-jp.org/ct1/122192
原発の条件はさらに厳しい。欧州委は原発についても、再エネ主体までのトランジションエネルギーとの位置づけを与え、EU内外で物議を醸している。ただ、その条件をみると、ハードルは高い。対象となる原発は、2045年までに建設認可を受けるか、あるいは2040年までに操業期間延長のための修繕認可を受けることを前提に、①極低・低・中レベル放射性廃棄物の最終処分施設が稼働している②2050年までに高レベル放射性廃棄物の処分施設に関する詳細な計画を定めることをTSCとしている。
さらに、現行の原発(第三世代)の課題である使用済み核燃料廃棄物を出さない次世代原発(第四世代)についても、脱炭素と放射性廃棄物を最小化することに貢献するとしてTSCに記載した。第四世代原発は上記の①も②も排出しないコンセプトだ。
第四世代原発をTSCとすることで、世界中で現在稼働している原発(第三世代)が抱える、使用済み核燃料廃棄物の最終処分問題と事故リスク等を減少しきれない「もう一つのトランジション性」を指摘したともいえる。その結果、現行の原発には「二重のトランジション性」があることが浮き彫りになる。
第四世代原発をTSCに据えたことで、現在、原発開発国が注力し、日本政府も関心を高めている小型モジュール原子炉(SMR)への過度な期待の「縮小」効果も狙っている可能性もうかがえる。SMRは事故リスク対応での工夫はあるものの、仕組み的には第三世代とほぼ同じ。使用済み核燃料廃棄物も出る。つまり現行原発のトランジション性を明確にすることで、間接的にSMRも脱原発の手段とは言えず、トランジション原発の一つであることを示したことになる。この点で原発推進派は、「肩透かし」を食った形になる。

原発がサステナブルかどうかの論点のうち、EUでもっとも集中して議論されたのが、使用済み核燃料廃棄物の最終処分場問題だ。わが国でも現在、処分場は定まっていないが、それでも日本政府は原発の再稼働を目指している。最終処分場が確定しないままだと、放射性廃棄物の漏洩・汚染問題が解決せず、タクソノミーの基本原則の一つである「他の環境目標に重大な影響を及ぼさない(Do No Significant Harm : DNSH)原則」に抵触するリスクが大きい。
この点でCDAでは、2050年までに地下深層貯蔵設備が2050年までに現実化することをTSCとすることで、DNSH原則に抵触しないとした。そのための対応を確実にするため、放射性廃棄物マネジメントファンドや原発解体ファンド、もしくは両方を兼ねたファンドの設定をTSCの一つとして求めている。これらのファンドの費用は廃棄物排出者(原発運営の電力会社)が責任を持ち、さらに核廃棄物の第三国への輸出も禁止としている。
最終処分場については、実現性を別として、各国の原発計画上は設定されている。このため欧州委もその計画を踏まえざるを得ない。そこで、それを前提としてトランジションタクソノミーの対象にする一方で、処分場の整備をTSCに明記することで、処分場の設備が整わないとTSCを満たせないという条件を示したことになる。サステナブルファイナンスの投資家にとっても、実際の処分場の確保とその安全性を担保されないようだと、資金を投じる判断にはつながらない。
そうなると、原発の新規建設等はタクソノミーにリスト化されたとしても、TSCを満たせないと、先の鉄鋼の最先端事業と同様、サステナブルファイナンスの対象外になる。「絵に描いたた餅」ならぬ「絵に描いたタクソノミー」になりかねない。さらにCDAは、処分場問題だけにとどまらず、現行原発が抱える事故への耐性を強化するため、核燃料についても認証付きの事故耐性燃料を2025年から採用することをTSCに含めた。
原発の操業中の安全性については、地震を含め異常な自然災害に対しての耐久性を確認するストレステストの実施を求めている。加えて原発事業者は、操業寿命を迎える原発の廃棄・解体計画を含め、最終処分場対応や安全性対策等の情報について、最終投資家にもわかるような情報開示を求められる。情報開示に際しては、独立した第三者の検証を求める。第三者検証付きの情報開示は、天然ガス火力発電の新設・改修にも適用される。
ただ、原発の場合、最終処分場の妥当性や、安全性について、科学的知見を有し、将来の技術発展性や事故抑制等を見据えた信頼できる第三者検証を出せる評価機関が、現在、世界に存在するのかという疑問も出てくる。信頼される第三者検証が得られないと、タクソノミーも機能しない。
原発保有の加盟国は、原発関連のTSCに準拠した計画等の情報開示を5年ごとに欧州委に提出しなければならない。この点で加盟国は、最終処分場の妥当性を含めて、自国の原子力委員会の判断だけではなく、欧州委の「許可」を受けねばならなくなる。こうしたいくつもの設定されたTSCや条件を考えると、サステナブルファインスとしての原発新規建設は、原発推進派が想定したほどは簡単ではないようだ。
EUの原発関連企業で組織する業界団体「FPRATOM」事務局長のYves Desbazeille氏は「原発をタクソノミーに盛り込んだことは歓迎する。しかし、事故耐性燃料は現在、テスト段階であり、25年までに商業用に供給するのは不可能。原発をトランジションと位置付けるのも問題」として、不満を隠さない。SMRが事実上、トランジション扱いを受けることも想定外のようだ。https://rief-jp.org/ct5/122139
天然ガス、とりわけ原発について、「環境派」の反対を押し切る形でタクソノミー案に加えた欧州委だが、こうした詳細なTSCの設定や条件付けを見てみると、欧州委が「名を捨て、実を取る」政策を仕掛けた可能性もある。原発派優位のEU域内の政治情勢を踏まえると、欧州委レベルでは政治圧力に抗することはできない。
そこで、原発を受け入れるように見せながら、実際は明確な最終処分場の備えの無い原発の新規建設等について、サステナブルファイナンスとしては成立しない手順を盛り込んだ。とすればユーロテクノクラート(欧州委の官僚機構)は相当の仕掛人ということになる。あるいは、独仏等の主要国からの暗黙の了解も得ているのかもしれない。欧州委内からも「実際に原発でサステナブルファイナンスとして認められるのは、既存原発のアップグレードだけで、新規は無理」の声もあがっているという。

原発論議に隠れる形となった天然ガスのほうも欧州委の「政治判断」がチラついて見える。天然ガス火力の存続は、脱炭素に向かうEU全体、特にドイツを中心とした中東欧諸国にとって、再エネ電力に切り替えるまでの、まさに「つなぎ」のトランジション・エネルギーと位置付けられている。特に脱石炭化が強く求められる東欧諸国にとっては、原発か天然ガスか、という代替エネルギー源の選択は、必須の問題でもある。
東欧のエネルギー転換は、その向こうに側にいるロシアのエネルギー政策とも密接に関連する。ロシアの天然ガスを経済ベースで取り込むことで、ロシアの「政治的脅威」の緩和も目指そうとするドイツ等の対ロ戦略は、旧ソ連圏のウクライナ等も踏まえた対ロ政策を展開する米国とは異なる。各国の国内政治・政策調整が主である原発とは別に、天然ガスは内外の政治事情も含めた「高度な政治判断」を必要とするテーマといえる。
欧州委CDAを巡る原発論議の高まりは、こうした天然ガスに関するEUの政治事情から目をそらす狙いも含まれているかもしれない。天然ガス火力のTSCは年限を決めて明確に新規発電所の建設を前提としている。その点で、温暖化対策の強化を求めるサステナビリティ派との対立は続きそうだ。
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

藤井 良広(ふじい よしひろ) 一般社団法人環境金融研究機構代表理事。元上智大学地球環境学研究科教授、元日本経済新聞経済部編集委員、ISOサステナブルファイナンス専門委員、CBIアドバイザー等を兼任。神戸市出身。






















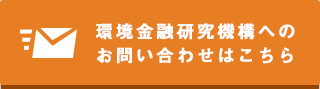










 Research Institute for Environmental Finance
Research Institute for Environmental Finance